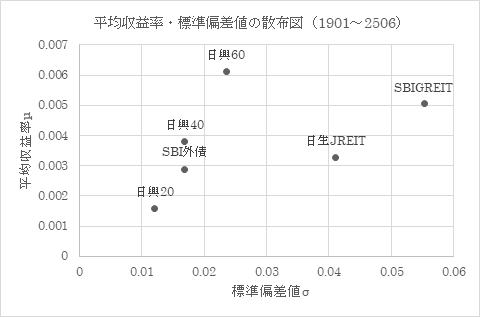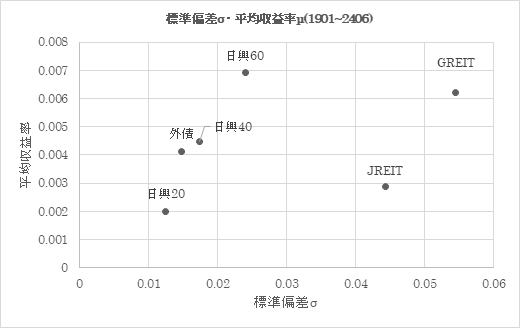資産形成論説明ノート2025年
ホームページへ戻る
2025年に引き続き、資産形成教室を4月7日から、7月14日まで15回の予定で、『資産形成論 2025年テキスト』を解説するために、このノートを掲載します。テキストは、昨年度のテキストに、2024年説明ノートを反映して、改訂中です。例年、6月になりますが完成したら、ホームページに掲載します。それまで、次の『資産形成論 2024年テキスト』を参考にしてください。
『資産形成論 2024年テキスト』24shisankeiseroni.pdf へのリンク
第15回目 2025年7月14日
要点 6.4.2 リバランス法の応用(第14回の続き)
1)海原氏の2024年7月~2026年3月の戦略
2)山川氏の2024年7月~2026年3月の戦略
3)高原氏の2024年7月~2026年3月の戦略
6. 5 次の半年の変動要因予想
・半年の変動予想方法
・本教室のまとめ
6.4.2 リバランス法の応用
資産形成論2024年版および今年度の資産形成論において、6投資信託の平均収益率・標準偏差を比較すると、下の表になる。これらをもとに、3世帯の2025年7月から2026年3月の戦略を考える。
平均収益率・標準偏差(2019年1月28日~2024年6月27日)
|
SBI外債
|
日興20
|
日興40
|
日興60
|
SBIGREIT
|
日JREIT
|
|
平均収益率
|
0.004128
|
0.001999
|
0.004475
|
0.006914
|
0.006203
|
0.002869
|
|
標準偏差
|
0.014877
|
0.012551
|
0.017448
|
0.024052
|
0.054488
|
0.044292
|
平均収益率・標準偏差(2019年1月~2025年6月)
|
SBI外債
|
日興20
|
日興40
|
日興60
|
SBIGREIT
|
日生JREIT
|
|
平均収益率
|
0.002881
|
0.001576
|
0.003798
|
0.006115
|
0.005052
|
0.003265
|
|
標準偏差
|
0.016913
|
0.012068
|
0.016902
|
0.023556
|
0.055292
|
0.041079
|
1)海原氏の戦略結果と次期の戦略
2024年7月~2025年3月の戦略
・ボーナス月、7月および12月、財形貯蓄として、日興-DCインデックスバランス(株式60)の購入する。
・iDeCoは、月1万円、日興-DCインデックスバランス(株式60)の購入する。
・個別株は、成長投資枠に、年間240万円投資上限があるから、成長分野で、好配当、企業投資額が大きい企業を選び、ボーナス月以降に、市場のトレンドを見つつ、購入する。
戦略の結果
ボーナス月、7月および12月、財形貯蓄、iDeCoは、日興-DCインデックスバランス(株式60)の購入することで、他の投信より、成績は良かった。
個別株は、成長投資枠に、成長分野で、好配当、企業投資額が大きい企業を選んだならば、2024年7月9日日経平均株価41580.17円、東証株価指数(TOPIX)2895.55から、2025年7月9日、日経平均株価(225種)39821.28円、東証株価指数(TOPIX)2828.16だった。2025年7月上旬まで、トランプ関税ショックはあったが、年間の変動差は少ない。
2025年7月~2026年3月の戦略
・ボーナス月、7月および12月、財形貯蓄として、日興-DCインデックスバランス(株式60)の購入する。
・iDeCoは、月1万円、日興-DCインデックスバランス(株式60)の購入する。
・個別株は、成長投資枠に、年間240万円投資上限があるから、成長分野で、好配当、企業投資額が大きい企業を選び、ボーナス月以降に、市場のトレンドを見つつ、購入する。
2)山川氏の戦略結果と次期の戦略
山川氏の教育資金は、7月と12月のボーナスをあてる。収支差額合計は、老後の安心と予備費にあてる。
・企業年金のiDeCoは、月2万円で、投資信託で運用する。
・教育資金437,500円は、7月と12月のボーナスをあてる。NISAの投資信託から選択し、運用する。
・老後の安心は、月3万円を、つみたてNISAとして、予備費は預金にする。
iDeCo、教育資金は、日興-DCインデックスバランス(株式60)、老後の安心は、SBI-EXE-iグローバルREITファンドにする。
新NISAは、資金余力があるので、個別株式、好配当株式投信信託、先進国成長株式投資信託を選ぶ。個別株式は、現NISA制度で保有株式は、5年間以内に、順次、売却する。現NISA制度で保有している証券は、期限が来るまで、非課税証券として保有できる。新NISA制度では、期限がなくなるので、好配当で底支え、成長期待の企業を購入する。株式投資信託の中で、日本株式の好配当投資信託は、バランス(株式60)より成績がよいものがある。
2024年7月~2025年3月の戦略
iDeCoは、日興-DCインデックスバランス(株式60)。教育資金は、SBI-EXE-i先進国債券ファンド。老後の安心は、日興-DCインデックスバランス(株式60)。
戦略の結果 教育資金のSBI-EXE-i先進国債券ファンドは、日興-DCインデックスバランス(株式40)に平均収益率と標準偏差が近く、よかった。iDeCoおよび老後の安心は、日興-DCインデックスバランス(株式60)でよかった。個別株式は、日本株式で、好配当株式の成長性の高い企業に投資すれば、株価の値上がり、高配当は稼げている。
2025年7月~2026年3月の戦略
・ボーナス月、7月および12月は、財形・iDeCoは、日興-DCインデックスバランス(株式60)。つみたてNISAで、教育資金は、SBI-EXE-i先進国債券ファンド、老後の安心は、日興-DCインデックスバランス(株式60)。NISAの成長枠で、個別株式は、好配当株式の成長性の高い企業に投資する。
3)高原氏の戦略結果と次期の戦略
高原氏は、68歳とする。高原氏夫妻は85歳でなくなるとする。テキストp.67の収支差額表から、高原氏の預金からの取り崩しは76万円である。高橋氏が亡くなると3年間、取り崩しは、年32万円である。高原氏が85歳の期末に現預金が716万円ある。高原氏の妻は、遺族年金と自身の老齢基礎年金が収入であり、不足分が毎年32万円の取り崩しになる。
元本が減少しない投資信託を半分以上、17年間、SBI-EXE-i先進国債券ファンドの投資信託で運用する。取り崩しが必要な前年、売却し、定期預金で保有する。残りは遺産になるが、バランス型(株式20)で運用する。死亡予定年より、2年早く、売却し、預金する方が、入院する場合もあるので、注意が必要である。高齢者の入院した場合、死亡まで4年は覚悟しないといけない。
高原氏は、69歳から85歳まで17年間、毎年、76万円取り崩しだから、現預金1292万円を引き出すことになる。1292万円は、SBI-EXE-i先進国債券ファンドで運用し、76万円は前年、その分売却し、預金する。遺産716万円は、15年間、日興-DCインデックスバランスは株式60を買い、2年前から、売却するタイミングを計り、SBI-EXE-i先進国債券ファンドの投資信託にスイッチする。
2024年7月~2025年3月の戦略
SBI-EXE-i先進国債券ファンドと日興-DCインデックスバランス(株式40)に案分する。
戦略の結果 この二つの投資信託は、日興-DCインデックスバランス(株式40)の平均収益率がSBI-EXE-i先進国債券ファンドより少し優るが、標準偏差も同じ位置にある。収益を増やす観点から、日興-DCインデックスバランス(株式60)とSBI-EXE-i先進国債券ファンドを案分するほうが、普段は、(株式60)の収益の成長を期待でき、現金化するときのリスクは、SBI-EXE-i先進国債券ファンドの方が低い。
2025年7月~2026年3月の戦略
夫婦で、退職時の累積運用資金NISAの総枠3600万円以内にあり、退職金は2000万円以下だろう。退職金を日興-DCインデックスバランス(株式60)とSBI-EXE-i先進国債券ファンドを案分する。個別株式は、まず、スーパー、ドラッグストアの日用品、JR・JAL・ANAの株式を単位株以上保有していると、株式優待制度がある。日用品は10%割引、交通系は、50%割引、1日無料などがある。
6. 5 次の半年の変動要因予想
・半年の変動予想方法
・本教室のまとめ
本ノート2025年5月19日 第7回目2025年「世界経済・政治の見通し」の再掲
IMFの世界経済見通し、OECDの加盟国経済見通しおよびADBの新興アジアの経済見通しが、経済成長率とインフレ率の2025年および2026年の予測値が公表されている。
ウクライナ戦争で、世界インフレがはじまり、中央銀行は、自国のインフレを押させるため、政策決定会議ごとに、政策金利を上げてきた。今年は、日本以外、インフレ率が、政策金利を下回り、消費需要のインフレ抑制が効いて、GDP伸び率が止まってきている。各見通しは、トランプ関税で、対米輸出が減少する国では、政策金利がインフレ率にならび、消費需要を回復させ、企業の金利負担を軽減する景気刺激策を取り出した。米国は、関税効果で、上乗せインフレは続き、FRBは政策金利を維持、4.5%の金利高は続くから、国内投資は縮小する。米国景気は、後退する。ユーロ圏・英国では、25年は、成長率は、トランプ関税で停滞する。他も、世界需要減で、資源安が働き、インフレが2%台に落ち着いても、成長率は下がると見ている。
石油需要予測は、IEA、OPECともに、25年は、需要が減少する。中国とインドの経済成長率が減少し、石油需要が減る。
1)IMF世界経済2025年、2026年の見通し
OECD
2025/4/14発表 2024 2025 2026 2025/3/17発表2025 2026
世界GDP 3.3 2.8 3.0 3.1 3.0
米国 2.8 1.8 1.7 2.2 1.6
ユーロ圏 0.9 0.8 1.2 1.0 1.2
英国 1.1 1.1 1.4 1.4 1.2
日本 0.1 0.6 0.6 1.1
0.2
新興・途上国 4.3 3.7 3.9
中国 5.0 4.0 4.0 4.8 4.4
インド 6.5 6.2 6.3 6.4 6.6
世界インフレ率 5.9 4.3 3.6 2.8 2.6
ADB(アジア開発銀行)の新興アジア経済見通し
2025/4/9発表 2024 2025 2026
新興アジア 5.0 4.9 4.7
中国 5.0 4.7 4.3
インド 6.4
6.7 6.8
新興アジアインフレ率 2.6 2.3 2.2
IEA石油需要予測
2025/5/15発表 2025 2026
需要日量 1億390万バレル 1億470万バレル
供給日量 1億460万バレル 1億560万バレル
OPECプラス石油供給 2025/4,5,6
2025/5/14発表 日量41万バレル増産
2)世界経済・政治の見通し
ウクライナ戦争経過
ロシア軍は、ドンバス地域を2023年5月9日の戦勝記念日まで、完全制圧を命令したが、その間目立った戦闘は、バフムート攻防戦に限定され、ワグナー会社と精鋭部隊を投入したが、制圧できなかった。6月ワグナー社は、バフムート市街を奪還、社員を撤退させ、ロストフ市ロシア軍司令部に帰還、モスクワまで進軍、プーチンと決裂、ベラルーシに移動した。その後、プーチンとの話し合いが不調、自家用機と共に、墜落した。
ウクライナ軍の反転攻勢は2023年4月からだったが、EU諸国の戦闘車、戦車、砲弾等軍備と乗員の訓練に遅れがあり、東部・南部の天候待ちで、6月からになった。ウクライナ軍が反転攻勢を開始したが、9月南部戦線で、第1防衛線を突破、ロボチィネ村まで到達したが、米軍の予算が成立せず、弾薬不足に陥り、他方、ロシア軍は北朝鮮から、弾薬、ロケット弾、ミサイルを調達、南部戦線は膠着し、東部のバフムートから、50㎞南、ドネツク市から15㎞のアウディイウカ陣地に、ロシア軍が猛攻をかけて来た。ウクライナ軍は、南部戦線の機械化旅団を救援したが、2024年2月で、すべての前線で、弾薬はつきて、シルスキー新総司令官は、アウディイウカ守備隊を完全撤退させた。6月からの反転攻勢は、失敗に終わった。その責任は、ウクライナ軍を3方向から攻勢させたこと、軍装備、弾薬も、3分散されたため、ロシア軍を圧倒、突破できなかった。
ロシア大統領選後、反対に、ロシア軍は、ハルキュウ州境とドネツク市間の東部戦線に戦力を集中、特に、2023年10月から、2024年3月大統領選の戦果としてアウディイウカ陣地陥落をめざし、兵力・軍装備と北朝鮮砲弾・ミサイルを飽和攻撃し、ウクライナ軍は負けて西方に撤退した。
2025年ウクライナ戦争見通し
ロシア軍は、2年目になる軍事目標である、ドンバス地域を2024年5月9日の戦勝記念日まで、完全制圧は達成できなかった。プーチンが新大統領に就任し、現在、新政府閣僚を任命している。ゲラシモフ総司令官は再任、ショイグ国防相は、ベロウソフ新国防相に交代した。ロシア新体制は、プーチンの演説から、特別軍事作戦の続行が、核心にあり、その作戦が終了するのは、クリミア半島、東南部4州を6年間、維持することだろう。その間、軍需産業を主体に、新たに、NATOに加盟したフィンランド・スウェーデンとの国境線から、バルト海、バルト3国・ポーランド・ウクライナ含め、ロシア連邦の熱い国境線防衛に、軍装備・施設を増強、毎年、予算を増やす必要がある。
2024年前半、ロシア軍はアウディイウカ陣地攻略と、ハルキュウ州まで、バフムートを含む北東部で、西進した。さらに、ハルキュウ州からベルゴロド州に、反ロシア軍事組織が頻繁に奇襲攻撃をかけてくるため、看過できず、5万人5個師団を投入、ハルキュウ州国境10㎞を確保するため、侵略を開始した。ウクライナ軍の軍資源の枯渇を見て、新たに、ベルゴロド州国境からハルキュウ州巾10㎞を侵略したことは、ロシア政府は、敵国がGDP10倍である限り、遠慮なく侵略する意思を示した。ロシア国境周辺国は、この政権がNATO諸国に軍資源で勝てば、問答無用で、侵略をすると、枯渇しないように、軍備を圧倒すべきである。今回のように、ロシア軍が国境を越えてくれば、NATOは、逆に、ロシア領に10km、保安措置で、進軍すべきである。今のロシア政府に、国際法に基づく主張は、聞く耳はもたない。
2024年後半、ロシア国防予算は、すでに、半分は消化、残り、5兆ルーブルを年末までに消化する。ロシア軍は、バフムート・アウディイウカ・ドネツク市を結ぶ線は、2年間で10兆ルーブルを費やし占領した。2年間で、兵士の戦死傷者30万人以上・陸海空軍装備・外国からの輸入軍装備を消耗した。戦時経済からみれば、流動費30万人は、戦時労働者として、消失した。固定費の海軍艦船、空軍航空機・防空システム、陸軍火砲、装甲車、戦闘車、戦車等を破壊された。プチーチンは、ウクライナ占領地に、新たに、兵士17万を投入するというから、年間、戦時労働者を損失した予測値15万と数値がほぼ一致する。破壊された固定設備は、2024年で、2023年で失われた分を、軍需産業に発注する。ロシア企業の生産能力から、艦船、航空機、装甲車、戦闘車、戦車・S400等、重量設備ほど、年間充足率は落ちる。軍事消耗品である砲弾、ミサイル、ドローンとちがって、艦船、航空機、装甲車、戦闘車、戦車・S400は、外国から購入は出来ない。
ウクライナ軍は軍重装備を、西側から供与を受けるから、ロシア軍より優越していく。ウクライナ徴兵と適性配属がすんなり、決まり、訓練がすむ2024年8月以降のウクライナ軍の反転攻勢は、第1次反転攻勢よりは、戦果が確実に見込める。ウクライナ戦争におけるウ・ロ軍装備の優劣が明白になり、NATOおよび日本は、軍重装備は、新装備に切り替えが必要になっている。GDP2%を防衛費に投入する方向に、コンセンサスができつつあり、ユーロ圏20カ国では、2023年名目GDPは、15兆5483億ドルである。その2%は、3109.66億ドル(46兆6449億円)となる。日本は2023年名目GDP591兆4820億円で、その2%は11兆8296億円である。
2024年後半、ウクライナ軍重装備は、占領地のロシア軍重装備より、優越していく。昨年秋から、ウクライナ軍は枯渇し、ロシア軍は調達できた砲弾、ミサイル、ドローンは、秋以降、両軍生産、ウクライナは供与を受け、量は1対1の互角になる。1000㎞のロシア軍防衛線は、南部をふたたび、第1次反転攻勢の3倍で進軍すれば、すなわち、5万以上の5個師団が、秋から、進軍すれば、南部の分断に成功し、東部ロストフ市およびクリミア半島からのロシア軍の兵站は遮断できる。しかし、F16の実戦配備があっても、昨年と同様な、数個旅団1万程度では、2重防衛線と、幹線沿い高地に陣取る火砲群の餌食になり、南部分断作戦は成功しない。
2024年8月、ウクライナ軍機動部隊は、クリコフ州スジャを越境攻撃した。モスクワまで、600㎞、1000㎢以上を占領し、主要な弾薬庫、空軍基地をドローン、中距離ミサイルで、攻撃、ウクライナへのドローン・ミサイル攻撃を国境から300㎞下げた。ウクライナ長距離ドローンが、1000㎞以上離れた、空軍基地、軍需工場、石油製品貯蔵所、発電・変電設備、ガス・パイプラインの攻撃を始めたことが新しい。
ロシア軍は、クリコフ州奪還に、東南部から部隊を移動させず、北朝鮮と交渉をし、北朝鮮契約兵を12月までに、1万2千人調達、北朝鮮製の砲弾、ミサイルを調達、2025年に入って、ロシア軍は、定期的な16万人徴集し、クリコフ州の奪還作戦を強行、2025年3月奪還に成功した。
2025年3月トランプ大統領が、ロシア・ウクライナ両国の停戦仲介に入った。5月16日トルコの仲介で、ロシア・ウクライナの直接交渉が、3年ぶりに開かれた。捕虜交換が成立しただけであった。ロシア側は、今年度は、東南部の完全占領、2024年5月越境10㎞のハルキュウ州、クリコフ州を奪還し、国境緩衝地域をスムイ州の必要性を痛感、両州の侵攻を主張した。
ウクライナ軍は、米国の軍支援が不確実となり、クリコフ州から撤退、東南部は膠着状態のままである。ウクライナ各地に対するミサイル・ドローン攻撃は、続いている。ウクライナ軍需工場は、EU軍需工場の進出で、砲弾等の消耗品生産、小型偵察、自爆ドローンの生産、年間400万機、射程100㎞の滑空ミサイルの増産によって、ロシア軍占領地内で使用する量は、ほぼ1対1になるようだ。ロシア軍を東部戦線の膠着状態に抑えているのは、現在、2対1になり、今年中に、EUからの供給も増加する。
日本自衛隊の高機動車は、昨年度、100台供与されたが、今年度は30台のようだ。むしろ、商業汎用車の中古車である、大型建機、ランドクルーザー、パジェロ、軽トラの方が、軍装備の運搬、1500kmへのアクセス兵站輸送路建設、偵察・自爆ドローンを撃墜、ジャミングする機動性をつける改造ができ、部品も豊富に供給できる。ロシア軍は、周辺国からの中古車両が手に入らなく、占領地での移動が不便になっている。
ガザと中東
2023年10月7日、ガザから、隣接したイスラエル領に、ハマスが奇襲をかけ、村と国際コンサート会場を攻撃し、1400人以上の死傷者と220人の人質をとって、ガザに引きあげた。イスラエル軍は、直ちに、30万人を召集、ガザ北部と南部を分断、北部市民を南部に避難させた後、空爆、市街地と地下トンネルを破壊した。南部と北部を建機で、分断、ハマスと人質解放をカタールおよびエジプトで、継続して、人質半数は、解放したが残りは、解放しない。現在、南部も空爆、エジプト国境ラファ検問所まで、北部と同様、空爆する状態にある。その間、南イエーメンのフーシ派のミサイル攻撃と紅海・アデン湾の商船をミサイル攻撃したが、欧米の艦船が、基地を同様にミサイル攻撃、商船の通航を護衛している。シリア・ダマスカスにあるイラン大使館にいたイラン革命防衛隊幹部をイスラエルが空爆した。イランは、300発ミサイル・ドローンによる、イスラエル報復攻撃後、レバノン・ヒズボラ、シリア・イラク・シーア派のイスラエル攻撃も収まっている。イスラエルのイランへの反撃は、規模が小さかった。
イスラエルは、南部を北部と同様、空爆で破壊、地下トンネルの基地を破壊するまで、作戦は続行するだろう。停戦できず、南部に潜むハマス隊員は脱出できず、人質は、交渉では、生存しては帰らないだろう。ハマスは、すでに、ガザ居住地はラファ近郊以外、灰塵に帰し、ハマス組織は、ガザ指揮部は壊滅した。ハマスの奇襲目的が、ガザ市民の居住地をそのままに、イスラエルにとらわれている同志を奪還するのが、目的だったとしたら、奇襲は目的を達成できず、220万人ガザ市民をキャンプ生活に追い込んだ責任は重い。ガザでは、ハマス隊員を壊滅させられ、家無き難民220万人市民に、生活保障をする財源もない。2024年ハマス組織は、ガザにおいて、テロ組織となり、恒久的に、ガザで政治軍事活動は出来ない。パレスチナ暫定政府が、家無きガザ市民を説得、自治組織を立ち上げ、国連の支援とともに、ガザ自治を回復するようになるだろう。
トランプ大統領は、ハマスが人質解放せず、戦闘を続けるのをみて、ネタニヤフ首相のハマス掃討作戦を支持、ガザ市民は、他国へ移民させる考えを持っている。ハマスが抵抗をやめ、撤退するまで、ガザ市民に対する人道支援は、USAIDを廃止したことにみられるように、救済するつもりは全くない。5月中旬の中東3カ国訪問で、ハマスを支援するカタールから、投資を引き出しているから、ハマスの抵抗は無理がある。
EU・英国
EU・英国は、ウクライナの軍民支援を継続するが、EUで、先端産業の育成に、海外企業を呼び込むことは進展した。ロシアに依存したエネルギー構造から脱却する代替エネルギー設備投資は、期待ほど進んでいない。ドイツは、洋上LNG液化工場船を建造している。EUは、基礎食料の自給率は100%を越えているので、ロシア産の食糧に依存はしない。むしろ、ロシアへの農産物・加工品の輸出が停止し、EU生産者の販路が失われた損失はある。
2023年は、フィンランドおよびスウェーデンのNATO加盟があった。ウクライナは、EU加盟の候補国になった。2024年は、3月から、5月まで、NATOの9万規模の大演習が実施された。米国のウクライナ軍支援予算案が4月下旬まで可決せず、ウクライナ軍は、アウディイウカ陣地を占領され、前線は後退した。この事実に、EUの軍需産業は、米国からの武器供与は、信頼できず、NATOのヨーロッパ独自の武器備蓄の必要性が意識された。トランプ氏が大統領になれば、GDPの2%を要請するはずである。EU独自で、兵器開発を開始することも、始まった。
EUおよび英国は、インフレが収まらず、ECBは、4.5%の政策金利を維持、英中央銀行は5.25%である。インフレが続くと、消費者は、節約で対抗するので、消費需要は実質減少していく。日本と違って、賃金は流動的で、インフレに遅れて上昇。消費は手持ち現金で買うので、不必要な財は買わなくなる。景気はなかなか、上がらない。
ウクライナ戦争疲れ、ガザ侵攻疲れで、消費は委縮しているのは、世界各国皆同じである。ヨーロッパが夏休みに入り、7月、パリ・オリンピックがあり、コロナが弱体化し、再び、世界から観光客が回帰してくる。サービス業を中心に、EUの経済回復が加速されるだろう。日本では、春から、大谷事件で、開幕した米メジャーリーグは、大谷選手の活躍で、盛り上がっている。日本人も、ドジャーズが勝ち、大谷選手が活躍すると、元気が出るという人もいるようだ。パリ・オリンピックは、バカンス入りとともに、ヨーロッパの委縮した経済活動を活性化させる。
英国は、EUを脱退し、NATOとの安全保障は、つながっている。ウクライナ戦争で、ロシアの資源に、依存はしないが、高インフレーションの影響もあって、経済成長が停止した。当時の保守党政権は、EU脱退当時の東欧移住者の増加、漁業の漁獲高の調整がつかず、EUの法制度に従うことを嫌っていた。故エリザベス女王も、暗黙の脱退了解があった。現保守党は、人気が落ちて、EUとの経済協定を加盟国並みにもどす方が、成長率は、回復するだろう。
2025年1月トランプ大統領が就任し、関税政策を始めた。EUは、報復関税をかける。英国は、対米貿易は、赤字なので、トランプ関税公式では、関税率はゼロになる。EUは対米経済との縮小均衡になるから、米国以外の販路を求め、国内経済の内需を高める経済政策をとることになる。
ロシア
ロシア経済は、IMF4月予測では、2024年3.2%、2025年1.8%成長である。軍事予算の倍増と、軍事産業に増産させ、外国資本設備を摂取、類似製品を生産したため、成長率が上がっている。ロシア人の夏のバカンスは、パリ・オリンピックでも、ロシア連邦からの観光客はこない。ウクライナ戦争以前は、南欧諸国がロシア観光客の人気地であっただろうが、戦争が長引くにつれ、ロシア人は、東南アジアに行っている。その分、観光収入が減るが、これが、6年間、常態となり、ロシア経済と完全に分断される。
トランプ大統領になって、世界経済の成長率は1%以上縮小を予想している。原油相場は、産油国のシェア争いで、供給を4月から増産し、原油価格が60ドル台に下落している。ウクライナ軍の石油施設へのミサイル攻撃もあり、生産力が低下、原油価格が60ドル台になると、収入がさらに、減少する。国家予算の歳入が減少する。内需産業から、軍需産業に、雇用・資本を移転しているので、内需産業、雇用者に増税もできず、中国から、内需の輸入、イラン、北朝鮮からのドローン・ミサイル・砲弾を輸入し、外国の契約兵は集まらず、国内徴集兵の定期召集16万人だけで、動員数は低下している。国内兵を突撃兵として、最前線で消耗させることはできないだろう。
米国
米国経済は、2023年に引き続き、先進国では、2.7%成長で、インフレ率は直近では3%で、安定している。政策金利5.25%は、インフレ率の2倍あり、利下げが、市場では予想されている。設備投資、住宅建設に影響する長期金利は、直近では、4月4.539%である。米国では、インフレと賃金率上昇が同時化するから、消費需要は、実質的に変化しない。2024年11月大統領選があり、0.25%利下げが、6月11日~12日の公開市場委員会で決まる。大統領選の論点として、中国貿易について、バイデン大統領は、戦略物資の取引禁止、半導体工場の国内誘致、トランプ氏は、中国企業のEV車メキシコからの輸入禁止、対中関税を引き上げるという。米中貿易に、直接、減少を狙っている政策は、トランプ氏である。
米大統領選挙は、トランプ氏の勝利となった。2025年1月の就任後、トランプ関税行使に従って、米国と貿易関係を持つ各国に、関税をかけ、戦略的品目には25%の関税、中国には145%の関税をかけた。関税による期待インフレ率が上昇、FRB政策金利4.5%の高止まり、債券、株式価格が暴落したため、トランプ政権は、軟化、4月から、一律、10%を発動、超過関税は、90日間交渉することにした。対中国関税は、5月14日115%引き下げている。2025年後半、トランプ関税政策による、スタグフレーションが予想されている。
インドおよびASEAN
インドは、ウクライナ戦争のエネルギー・食糧インフレーションに対し、エネルギー面では、ロシアから割引価格で、原油を輸入し、国内消費を上回る石油製品は、EUに輸出した。食料は、主食が米であり、ウクライナ、ロシアの小麦粉には依存しない。どういうわけか、米の輸出国だが、輸出禁止にした。エネルギー・食糧インフレーションは、遮断され、高度成長を2年間続けている。
製造業の発展に、力を入れるようになったのが、最近のインド経済の特徴である。人口成長で、中国抜き、世界一の人口大国になる。インド南部で、ソフト産業が、1985年の頃から、世界的に有名だったが、最近は、人口増を農業部門で吸収できず、余剰人口は、製造業の付加価値の高い産業を育成、雇用し、経済成長することに力を入れ出したのであろう。IMFの2025年の経済成長率は、6.7%で、アップルがインドで生産することになった。インドの人口は中国を超え、製造業の、トランプ関税をかける輸入代替政策から、人口ボーナスを利用して、外資導入、特に、アフリカへの商品供給力を伸ばし、アフリカ市場への輸出競争力をつけるつもりである。中国の高度成長が、10年続いたが、インドも6%以上の高度成長期に入ったようである。
インドは、米国世界関税政策、米国の対中国貿易縮小、EU・ウクライナ対ロシアの戦争を尻目に、製造業の開放に踏み切り、巡航経済成長の高速道路に入ったようである。国際的に、なにも問題ないため、2030年以降、米中経済戦争が終了、ともに、経済成長はせず、インドが、進出した外資とともに、製造業を、低価格インドソフト産業によって、AI高度化し、世界市場に進出してくる。地球温暖化とともに、インド風熱帯化文明となり、暑気払いのインドバラエティーが世界で盛んになるかも。中国は、社会主義こんこんちきで、面白くなく、日本企業も投資しようがないが、インド映画の集団舞踊もええじゃないかで、「インドの夢」を語ろう会に賛同する日本企業は多くなっている。
東南アジア諸国は、コロナから、サービス業が回復し、自律成長軌道に入っている。ADBアジア開発銀行の予測では、2024年は成長率4.8%、25年は4.7%、インフレ率は、3.2%、3%である。
域内の問題は、中国の南シナ海進出に対し、フィリッピン政府が、前政権の中国寄り立場から、対決型になり、漁船、中国海警船との衝突が増え、日本は、巡視船をフリッピン政府に借款している。今年も、追加、建造する。
ミャンマー軍事政権は、2023年は、反軍勢力の政府軍攻撃が強まり、3方向から、首都ネピドーは、包囲されて、国軍兵士の降伏も多く、徴兵令を強化しているが、隣国に逃れている。中国の軍事支援が、国軍本営に届いているのかわからないが、空軍の空爆は続いている。反軍3勢力に、携帯ミサイルが届くようになれば、国軍機械化部隊による軍事的優位は薄れる。国軍は、兵弾つきて、ネピドーから、市民が避難するような事態になりそうだ。
中国
中国は、不動産業界の主要企業が、債務超過に陥り、不動産投資は止まり、全国の都市住宅価格は、下落が続いている。台湾侵攻問題で、海外企業直接投資は減少傾向にあり、米国の半導体国内回帰政策で、中国に米先端品が輸出されず、中国先端商品に搭載できず、輸出が減少している。中国は、伝統的雑貨・衣類製造は、米国市場が制限されても、アジア、欧州、経済制裁を受けるロシア連邦には、依然、輸出力は強い。各種ドローン、5G対応携帯やEV等の世界最先端、高付加価値製品は、輸出に摩擦がでてきた。
2025年は、製造大国25の完成年であるが、習主席には、その目標は達成できない。その輸出輸入経路である一帯一路も、相手国に、断られる事例も出ている。2025年、不動産市況の回復、不動産投資の底打ちはせず、国有銀行、地方銀行の不良債権処理は、手つかずのようで、金融破たんが発生するまで、その抜本的処理は行われないだろう。
トランプ関税戦争は、30%に引き下げたが、任期中は、高関税、中国船舶の入港税徴収はやめないだろう。中国の黒字は激減、米国債の保有も激減する。他方、米国以外との貿易拡大を交渉して、米国依存はしなくなる。中国は、外交、国防、貿易で、2国間で協定を結ぶ主義だったが、トランプ米国経済との分断化となり、EU、日本、ASEANとも、貿易の多国間協定を結び、WTOを機能させる方向をとるだろう。いわゆる社会主義的制約はとりはらい、自由貿易主義をとる。
日本
日本は、岸田首相が、政治資金規正法で、自民党の有力者をはずし、2024年9月までの、総裁選で、選出されないのは明らかで、政権誕生以来、インフレ、円安、安倍氏暗殺、岸田氏暗殺未遂事件があり、国民生活は、毎月3%の必需品値上げで、2023年春闘で賃上げはなく、非正規の最低賃金は十円玉程度の時給を決めた程度の所得では、すべての家計は、節約、倹約生活を1年以上続けていたことが、四半期GDPの消費需要の減少に表れている。岸田政権は、2024年6月から、1年間、月4万円の減税をするというが、インフレが日本では、2%台になり、中小零細の賃金が3%を越えるのは、2024年は出来なかった。総裁選は、岸田氏は降りて、石破氏が選出された。内閣を立ち上げると、すぐさま、衆議院解散に踏み切り、与党は過半数をえられず、予算案は、国民民主党等の選挙公約を取り入れる形で、修正され、2025年3月末成立した。2024年8月の令和米騒動が勃発、例年5キロ2000円の米が、2倍以上で販売される状態が、現在もつついている。そのため、CPIは、毎月3%台を続伸、2025年第1四半期、実質GDPは-0.2%である。2025年春闘の賃上げは吹き飛んでいる。石破首相が、トランプ関税に、国難発言をしたが、内政は火の車となり、7月の参議院選は、惨敗するのは確実である。
次の半年の変動要因を予想
若年世代および壮年世代は、所属する業界に対する景気,政策,海外の景気,各国の政策等の変動は、毎日の仕事に反映されているはずである。変動要因が変化すると、仕事量が変化する。それは、夏、冬のボーナスに成果として、反映されるので、まったく無関心な勤労者はいない。ゆえに、各事業体に所属する勤労者は、半年ごと、その間の事業体の成果と、次期の予想は、おぼろげながらでも、想定できる。
日本経済が活動した半年と、これからの半年の見通しをもとに、ドルコスト平均法で購入している商品をリバランス法にしたがい、変更、売却、新規購入を判断する。
選択した商品に影響する、景気,政策,海外の景気,政策等の変動要因の重要度を考える。下の表に、商品にしたがって、国内外の強く働く変動要因が挙げられている。毎年、元旦の朝刊に、年間の予定表が掲載されており、日米欧の中央銀行の政策決定会合日程およびGDPの速報値発表日が掲載されている。
資産形成論説明ノートおよび金融論説明ノートでは、日本経済新聞の日曜版「今週の市場」から、今週の予定を検討し、金融市場への影響を推論した。経済指標の発表の場合、マネックス証券の「投資情報・レポート一覧」から「経済指標カレンダー」をクリック、さらに、予想・結果をクリックすると時系列が表示される。予想より結果が下回ると失望売りで市場は反応する。
商品リスト 変動要因
海外
債券 日銀の政策会合 日銀短観 米国準備制度理事会 EU中央銀行
消費者物価 為替レート 消費者物価指数 失業率
株式 政府予算 政策の変更 政府予算
政策の変更
四半期 GDP 四半期 GDP
リート 長期金利 都市の地価発表 長期金利 都市の地価発表
バランス 株式 20 40 60 の構成要素に対して、上記の変動要因按分
インデックス 債券の構成要素、株式の構成要素に対して、上記の変動要因
ETF 債券の構成要素、株式の構成要素に対して、上記の変動要因
変動要因の発表は、各証券会社の HP に、スケジュールが公表されている。重大発表は、情報が必ず漏れ伝わってくるので、市場の商品は、発表前に、反応し、価格が上昇するか、下落してくる。変動許容範囲上下 20%以内ならば、再び、平均回帰する見込みが強い。20%を超えると、短期で回帰するのは、無理がある。
MFEXモデルによる簡易予想
マンデル・フレミング開放マクロ経済モデル(MFEXモデル)の枠組み
『金融論2018年テキスト 説明ノート』第13回2019年12月9日から、マンデル・フレミング・モデル(MFEXモデル)において、不完全雇用CASE Iのとき、ドーンブッシュ・フィッシャー『マクロ経済学上・下改訂第4版日本版』1989にしたがった線形化をした開放マクロ経済モデルを、以下のように作成した。投資関数、流動性選好関数は、債券価格表示の方法もあるが、一次関数で線形化している。2024年版資本形成論テキストにおいて、4市場均衡図6.1および6.2を載せている。
完全雇用CASE Ⅱは、『金融論2022年』pp. 187-192に計算している。金融政策を実施すれば、『金融論2022年』p.192図10.17において、QQ2線のように、右へ移行すれば、為替レートは減価し、物価は上昇するから、金融政策は有効である。
各市場均衡式
貿易収支NXをNX=Ex-Im=mwYw-e Pw(mY ) /P、資本収支CFをCF=ΔB/i-e ΔBw/iwとおく。資本流入はΔB/i、資本流出はe ΔBw/iwである。国際収支BPはBP=NX+CF/Pとする。4市場の均衡式は次のようになる。
財市場 Y =C0 +c(Y-T0) +I0-bi +G0+mwYw-e Pw(mY ) /P
貨幣市場 M/P =kY-hi
労働市場 w0=P (1-α)Y/N (CASE I不完全雇用ケインズの場合)
自国通貨建為替市場 P (mwYw)+ΔB/i=e Pw(mY ) +e ΔBw/iw
(1)i <iwの場合、資本流入はΔB/i=0、
(2) i >iwの場合、資本流出はe ΔBw/iw=0とする。
各関数の定義
消費関数 C =C0 +c(Y-T0)
投資関数 I =I0-bi
貿易・サービス収支関数 NX=mwYw-e Pw(mY ) /P
労働供給関数 NS=w0 (CASE Iケインズの場合)
労働需要関数 ND=P (1-α)Y/N (CASE
Iケインズの場合)
実質貨幣供給関数 MS =M/P
実質貨幣需要関数 LD =kY⁻-hi
投機的貨幣需要関数 L2 =-h i
自国通貨建為替供給関数 S¥ =P(mwYw)+ΔB/i
自国通貨建為替需要関数 D¥ =e Pw(mY )+e ΔBw/iw
w0:貨幣賃金率 P:物価水準、i:国内利子率、iw:世界利子率、e:為替レート、
Y:国民所得、Yw:世界国民所得
均衡の決定
財市場均衡式はY=C0 +c(Y-T0) +I0-bi +G0+mwYw-e Pw(mY ) /Pであり、IS曲線という。
貨幣市場均衡式はM/P=kY-hi であり、LM曲線という。
IS曲線に、LM曲線の利子率i=1/h(-M/P+kY )を代入すると、次の総需要曲線ADが求められる。
(1-c+e Pwm /P)Y= C0 -cT0+I0+G0+mwYw-b/h(-M/P+kY )
労働市場均衡式からP={w 0/ (1-α)K0}Yとなる。総供給曲線ASという。
ASから、Y =A P
、A=(1-α)K0/w 0 をADに代入すると3市場が均衡する価格と為替レートの組み合わせであるQQ線が導かれる。
(1-c+e Pwm/P) A P
= C0 -cT0+I0+G0+mwYw-b/h(-M/P+k A P )
(1-c) A P+e Pwm=U-b/h(-M/P+k A P )、ここで、U= C0 -cT0+I0+G0+mwYwとする。
e Pwm= U -(1-c+kb/h) A P+(b/h)M/P。これをQQ線という。 (1)
最後に、為替市場からi <iwの場合、P(mwYw)=ePw(mY )+eΔBw/iw
Y =A Pを代入すると、P(mwYw)=ePw(m A P)+eΔBw/iw
e=P(mwYw)/{ Pw(m A P)+ΔBw/iw }。これをEE線という。 (2)
QQ線を図示する。(1)より、
e ={ U -(1-c+kb/h) A P+(b/h)M/P }/Pwm
=-{(1-c+kb/h) A /Pwm }P+U/Pwm+(b/h)M/Pwm P
となり、直線e =U/Pwm-{(1-c+kb/h) A /Pwm }Pと双曲線e =(b/h)M/Pwm Pとの合成した図になる。
EE線を図示する。(2)より、
e=P(mwYw)/{ Pw(m A P)+ΔBw/iw }=mwYw/Pwm A-/{ Pw(m A P)+ΔBw/iw }
と変形できて、双曲線になる。
EE線は、必ず、原点を通る。価格P=0は、経済学では、除外される。i <iwの場合、資本流出eΔBw/iwがつづくと、流出量が減少し、やがて、0になる。為替レートは、購買力平価説になり、e=mwYw/Pwm Aとなる。
QQ-EE均衡図(資産形成論2024年テキスト、p.133、図6.1)
4市場均衡は、QQ線とEE線の交点である。図では、点A(P*,e*)である。資本流出が生じると、EE線は、必ず、原点を通りつつ、左へ回転する。その結果、均衡点では、価格が減少、為替レートは、減価するという、結果になる。
結果、1)国民所得は低下する、
2)利子率は世界利子率になる、
3)物価は減少する、
4)為替レートは減価する。
資本流出が終了すると、為替レートは
e=mwYw/Pwm Aとなる。物価は一定である。
CASE Iは、ケインズ不完全雇用モデルであり、労働市場が改善されない限り、金利差で資本流出が生じるとき、デフレにおちいる。
金融政策を実施すると、『金融論2022年』p.187図10.14において、QQ線が右にシフトし、点Bで均衡する。
その結果、1)国民所得は増加する、
2)利子率は世界利子率になる、
3)物価は上昇する、
4)為替レートは減価する。
資本流出が終了すると、為替レートは
e=mwYw/Pwm Aとなる。物価は一定である。マンデル・フレミング・モデルにおける金融政策の有効性は、支持される。
本教室のまとめ
資産形成論は、昨年度に引き続き、考え残した課題を整理した。15回の説明で、平均分散法により、商品選択をし、半年間、ドルコスト平均法にしたがい、主に2つの制度、iDeCoおよびNISA利用の投資をする戦略を考えた。商品は、投資信託から選ぶので、もともと、多数商品をなんらかの平均分散で、投資割合を決めているから、その上で、平均分散にしたがって、投資信託の割合を決めるのは、二重計算である。半年の商品の成果を判断するため、選択した実際の投資信託の平均分散のデータを集計表に収集してみた。異なった性質をもつ投資信託の実績を比較することができる。
IMFおよびOECDの推計モデルは、2年先の推計値を公表していて、両者の推計値は近い。開放マクロ貨幣経済モデル(MFEX・モデル)と同様な、線形同時方程式を使っているためだろう。半年間の投資計画を作成する際には、2年先の推計値を参照して、投資信託および個別株式投資の購入計画を立てる。
筆者は、科研費で、大阪府の短期CO2排出量計算のために、大阪府マクロ計量モデルVer.H14R(2005.1.17)、産開研論集第17号平成17年3月の方程式体系で、データを更新し、推計した。当時、大阪府マクロ計量モデル方程式体系については、無批判であり、今回、その方程式体系を検討すると、マンデル・フレミング・為替・モデル(MFEX・モデル)と理論的な整合性が保てない方程式がある。特に、CASEⅡは、最適化モデルあるため、ケインズ不完全雇用CASE Iとは、方程式が異なる。また、大阪府マクロ計量モデルでは、均衡解が求められない。ただし、4半期のGDE=C+Iv+I+G+EX-IMは計算できる。
日本の4半期データ公表は、欧米中国と比較し、制度部門別にデータがきちんと取れない。その分、部門別推計式に頼ることになる。米国と中国の方が、月別公表データがそろっている。日本はデータ公表が1カ月遅れているものもある。
例えば、消費関数の推計式では、C=β+α1IY+α2Sであるが、毎月の個人消費支出C、個人所得IY、貯蓄残高(現預金)Sは、米国では、毎月C、IYは公表される。4半期GDP速報値は、1ヵ月半かかる。MFEX線形・モデルは、ほぼ、本体が決まったので、推計式とデータ確保、データの期間合わせを試行している。資産形成論2025年説明ノートでは、日本、米国、中国の毎月のデータを掲載することにした。金融論2024年説明ノートにおいて、2024年12月から、収集したデータを資産形成論2025年説明ノートにつないでいる。
課題 1 これらの月次データをもとに、四半期MFEX・線形モデルおよび最適化MFEX・線形モデルの計量経済学推定をする。理論分析と推定分析の整合性を確認、半年後の各変数の推計値を計算できるようにすれば、日本経済の半年後の見通しも立てられ、投資判断に役立てることができる。
制度部門別最適成長論を計量経済学的に推計する場合、以上は、四半期の短期離散モデルの伝統的推計である。
経済成長論・景気循環論・経済変動論の理論的立場では、経済変動は、離散的差分方程式より、連続的な微分方程式で表される。ケインズ不均衡動学は、短期的にはCASE I モデルであるが、生産物市場は、有効需要の原理に基づき、実質均衡であり、価格の均衡調整機能は働かない。一部の市場(労働市場に失業がある。)が不均衡であるため、中期、長期的に、均衡しない。
不完全雇用CASE Iは、ケインズ不均衡動学になる。経済成長論を復習してみると、ケインズ不均衡動学と新古典派均衡動学は、短期的には、問題は少ないかもしれないが、中期・長期になると、ケインズ不均衡動学は、財政・金融・経済政策手段だけで、いつ、全市場均衡が達成できるのか、不確定である。ケインズ的経済社会は、不均衡社会であり、国民の物的GDP満足も達成できない。また、国民の質的幸福・福祉の満足も達成できないのは、確かである。
新古典派均衡動学であるCASE Ⅱ
モデルは、全市場が均衡し、内生変数、外生変数微分方程式で、中期、長期均衡を分析することができる。
課題 2 新古典派均衡動学において、内生変数、外生変数の微分方程式の推計法は、中期、長期均衡推定を可能にするが、時系列分析になるから、計量経済学的には、方法に飛躍があり、ハードルは高い。実用化のための研究は続ける。
昨年の『金融論2024年』において、完全雇用CASE Ⅱは、各制度部門(中銀、銀行、企業、家計、政府、海外)が最適計算をする設定をしている。CASE Ⅱを動学化すると、最適成長論の理論的モデルになる。2025年は、経済成長論・景気循環論を復習した。短期モデルと中長期モデルに移行するとき、各種動学モデルは、理論的道しるべになる。MFEX連続モデルCASE I およびCASEⅡは、ケインズ不均衡動学がCASE Iであり、新古典派均衡動学・最適性成長論はCASEⅡになる。
不均衡動学と均衡動学の対立は、現在も続いている。それらの理論的考察を反映した、“理想的”制度部門別最適成長論を構成することを目標にしている。
2025年9月から、『金融論2025年』を開講する。マンデル・フレミング・為替モデル(MFEX・モデル)において、理論的MFEX線形モデルの均衡値に加えて、MFEX連続モデルCASE I およびCASEⅡの均衡値を計算する。
今週(2025年7月14日~7月18日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、6日BRICS首脳会議がリオデジャネイロで7日まで開かれました。
今週のイベントは、17日南アフリカで、G20財務省・中央銀行総裁会議があります。19日ベッセント米財務長官が来日します。
先週の統計は、次の発表がありました。
予測値 実現値
2025年7月7日 日毎月勤労統計 2.6% 1.0%
日5月景気動向指数一致 115.9 115.9
先行 105.2 105.3
8日 日6月景気ウォッチャー調査 44.9 45.0
5月国際収支 -5244億円 -5223億円
9日 中6月消費者物価指数 -0.1% 0.1%
今週の統計は、次の発表があります。
予測値
2025年7月14日 日5月機械受注統計 5.5%
日5月鉱工業生産 -1.8%
中6月貿易統計
15日 米6月消費者物価指数 2.6%
中4~6月期実質GDP
5.1%
6月小売売上高 5.3%
6月鉱工業生産指数 5.6%
16日 米6月鉱工業生産指数
0.2%
17日 日6月貿易統計
3370億円
米6月小売売上高 0.2%
18日 日6月全国消費者物価指数 3.3%
統計は、国民総支出GDE構成要素、物価、利子率について、日本、米国、中国の発表結果を一覧で以下に表します。
日本
3 月 4月 5月
GDP前期比、(年率換算) -0.2%、(-0.7%)
消費コンビニ売上高 9994億27百万円 9762億1900万円 1兆162億800万円
スーパー売上高 1兆899億5480万円1兆668億4608万円 1兆915億8404万円
百貨店売上高 4953億円 4232億円 4356億円
投資(工作機械受注統計) 1511億100万円 1302億600万円 1287億1600万円
輸出 9兆8478億円 8兆7691億円 8兆1350億円
輸入 9兆3038億円 8兆8019億円 8兆7726億円
貿易収支 5441億円 -328億円 -6376億円
物価指数 3.6% 3.5% 3.5%
利子率 0.5% 0.5% 0.5%
株価 36790.03 34609.00 36928.63
(第2金曜日の前営業日) 25/3/13 25/4/10 25/5/8
原油価格 71.6ドル 66.4ドル 59.21ドル
ドバイ、現物1バレル、ドル、5月渡し、(第2金曜日の前営業日)
個人所得(毎月勤労統計) 30万8572円 30万2453円 30万141円
完全失業率 2.5% 2.5% 2.5%
景気動向一致指数 116
116 115.9
先行指数 107.7
104.2 105.3
米国
3 月 4月 5月
GDP(前期比年率) -0.5%
個人支出(前月比) 0.7% 0.2%
個人所得 (前月比) 0.5% 0.8%
投資(耐久財受注統計) 9.2% -6.3% 16.4%
輸出 1808億ドル 2894億ドル 1792億ドル
輸入 3427億ドル 3510億ドル 2758億ドル
貿易収支 -1620 億ドル -616億ドル -966億ドル
物価指数 2.4% 2.3% 2.4%
利子率 4.5% 4.5% 4.5%
株価 40813.57 39593.66 41368.45
(第2金曜日の前営業日) 25/3/13 25/4/10 25/5/8
原油価格 71.6ドル 60.07ドル 61.8ドル
NY、先物、標準品WTI、1バレル、ドル、5月渡し、(第2金曜日の前営業日)
完全失業率 4.2% 4.2% 4.1%
ISM製造業景気動向指数 49 48.7 48.5
ISM非製造業景気動向指数50.8 51.6 49.9
中国
3 月 4月 5月
GDP(前期比) 5.4%
個人消費
投資
輸出
輸入
貿易収支 7367億元 7,000億元 7,500億元
物価指数 -0.1% -0.1% -0.1%
利子率(1年物LPR) 3.1% 3.1% 3.00%
株価(上海) 3358.73 3223.64 3352
(第2金曜日の前営業日) 25/3/13 25/4/10 25/5/8
個人所得
完全失業率
財新製造業PMI 51.2 50.4 48.3
日本 2024年12月 2025年1月 2月
GDP(前期比)
消費コンビニ売上高1兆407億1100万円 9506億9700万円 8874億6200万円
スーパー売上高 1兆2707億4504万円 1兆487億5248万円 1兆59億1492万円
百貨店売上高 6616億円 4805億円 4254億円
投資(工作機械受注統計)1430億94百万円 1161億46百万円 1182億15百万円
輸出 9兆4737億円 7兆5022億円 9兆1911億円
輸入 9兆4113億円 10兆4401億円 8兆6066億円
貿易収支 623億円 -2兆9379億円 5845億円
為替レート(円/ドル) 150.34円 158.33円 154.36円
(第2金曜日の前営業日) 24/12/5 25/1/9 25/2/13
物価指数(総合指数) 3.6% 4% 3.7%
利子率 0.5% 0.5% 0.5%
株価 39395.6円 39605.09円 39461.47円
原油価格 71.8ドル 76.3ドル 76.4ドル
ドバイ、現物1バレル、ドル (第2金曜日の前営業日)
個人所得(毎月勤労統計) 617375円 292468円 289562円
完全失業率 2.4% 2.5% 2.4%
景気動向一致指数 116.8 116.2 116.9
先行指数 108.9 108.2 107.9
米国
12月 1 月 2月
GDP(前期比) 2.4%
個人消費 5兆656億ドル
投資(耐久財受注) 2761億ドル 2823億ドル 2893億ドル
輸出 2665億ドル 2698億ドル 2785億ドル
輸入 3649億ドル 4012億ドル 4011億ドル
貿易収支 -984億ドル -1314億ドル -1227億ドル
PCEコアデフレータ 2.8% 2.6% 2.8%
消費者物価指数 2.9% 3% 2.8%
利子率 4.5% 4.5% 4.5%
株価(NY) 44765.71ドル 42635.2ドル 44711.43ドル
(第2金曜日の前営業日) 24/12/5 25/1/8 25/2/13
原油価格 68.3ドル 73.92ドル(25/1/9) 71.29ドル
NY、先物、標準品WTI、1バレル、ドル、 (第2金曜日の前営業日)
個人所得 25.119兆ドル 25.345兆ドル 25.442兆ドル
完全失業率 4.1% 4.0% 4.1%
中国
12月 1 月 2月
GDP(前年同期比) 5.4%
個人消費(小売売上高) 3.7% 4.0%(1~2月)
全国固定資産投資 3.3% 3.2% 4.1%
輸出 3356億ドル 3兆8800億元(1~2月)
輸入 2307億ドル 2兆6600億元
貿易収支 1048億ドル 1兆2200億元
物価指数 0.1% 0.5% -0.7%
利子率(1年物LPR) 3.1 % 3.1% 3.1%
株価(上海) 3368.86 3211.39 3332.48
(第2金曜日の前営業日) 24/12/5 25/1/8 25/2/13
個人所得
完全失業率(四半期発表) 5.1% 5.4%
ホームページへ戻る
基準価格データ
2019年1月28日~2025年6月27日まで,基準価格データは次の通りである。2023年6月27日の基準価格は取れなかったので、6月30日のデータである。
投資信託EXCEL表 期間2019/1/28~2025/6/27(各データ数90コ)
|
日付
|
SBI外債
|
日興20
|
日興40
|
日興60
|
SBIGREIT
|
日JREIT
|
|
190128
|
11258
|
15501
|
18364
|
20949
|
13557
|
11153
|
|
190227
|
11446
|
15654
|
18758
|
21582
|
14170
|
11351
|
|
190327
|
11584
|
15767
|
18843
|
21683
|
14535
|
11839
|
|
190426
|
11629
|
15811
|
18956
|
21884
|
14576
|
11800
|
|
190527
|
11518
|
15684
|
19623
|
21291
|
14415
|
11905
|
|
190627
|
11593
|
15801
|
18763
|
21454
|
14092
|
11951
|
|
190729
|
11642
|
15874
|
18905
|
21677
|
14432
|
12399
|
|
190827
|
11623
|
15832
|
18595
|
21021
|
14082
|
12815
|
|
190927
|
11743
|
16025
|
19144
|
22004
|
14822
|
13556
|
|
191028
|
11816
|
16049
|
19307
|
22348
|
15195
|
13932
|
|
191127
|
11962
|
16168
|
19596
|
22850
|
15149
|
13908
|
|
191227
|
11903
|
16167
|
19699
|
23090
|
15129
|
13470
|
|
200127
|
11931
|
16188
|
19665
|
22980
|
15403
|
13653
|
|
200227
|
12167
|
16037
|
19193
|
22094
|
15034
|
13487
|
|
200327
|
11858
|
15627
|
18375
|
20763
|
10917
|
9782
|
|
200426
|
11927
|
15684
|
18485
|
20939
|
10918
|
10084
|
|
200527
|
11997
|
15884
|
18980
|
21796
|
11490
|
10377
|
|
200629
|
12146
|
15889
|
19112
|
21891
|
11470
|
10635
|
|
200727
|
12224
|
15992
|
19261
|
22269
|
11533
|
10760
|
|
200827
|
12232
|
16095
|
19531
|
22754
|
12011
|
11219
|
|
200928
|
12096
|
16113
|
19576
|
22833
|
11531
|
11292
|
|
201027
|
12099
|
16094
|
19519
|
22729
|
11657
|
10765
|
|
201127
|
12127
|
16400
|
20255
|
24041
|
12586
|
11052
|
|
201228
|
12169
|
16439
|
20344
|
24156
|
12500
|
11452
|
|
210127
|
12122
|
16545
|
20646
|
24653
|
12829
|
11885
|
|
210301
|
12156
|
16531
|
20754
|
24996
|
13260
|
12984
|
|
210329
|
12369
|
16871
|
21292
|
25865
|
14324
|
13135
|
|
210427
|
12337
|
16754
|
21147
|
25600
|
14794
|
13512
|
|
210527
|
12474
|
16798
|
21236
|
25746
|
15128
|
13734
|
|
210628
|
12569
|
16908
|
21501
|
26221
|
15800
|
14306
|
|
210727
|
12642
|
16946
|
21510
|
26185
|
15933
|
14279
|
|
210827
|
12572
|
16925
|
21479
|
26140
|
15885
|
14424
|
|
210927
|
12572
|
17106
|
21982
|
27089
|
15813
|
14061
|
|
211027
|
12820
|
17076
|
21895
|
27017
|
16811
|
13916
|
|
211129
|
12741
|
16980
|
21693
|
26558
|
16524
|
13567
|
|
211227
|
12796
|
17058
|
21873
|
26878
|
17017
|
13677
|
|
220127
|
12507
|
16722
|
21172
|
25685
|
16144
|
13082
|
|
220228
|
12385
|
16694
|
21251
|
25923
|
16325
|
12761
|
|
220328
|
12657
|
16827
|
21723
|
26835
|
17148
|
13520
|
|
220427
|
12791
|
16712
|
21373
|
26163
|
18264
|
13608
|
|
210527
|
12474
|
16798
|
21236
|
25746
|
15128
|
13734
|
|
210628
|
12569
|
16908
|
21501
|
26221
|
15800
|
14306
|
|
210727
|
12642
|
16946
|
21510
|
26185
|
15933
|
14279
|
|
210827
|
12572
|
16925
|
21479
|
26140
|
15885
|
14424
|
|
210927
|
12572
|
17106
|
21982
|
27089
|
15813
|
14061
|
|
211027
|
12820
|
17076
|
21895
|
27017
|
16811
|
13916
|
|
211129
|
12741
|
16980
|
21693
|
26558
|
16524
|
13567
|
|
211227
|
12796
|
17058
|
21873
|
26878
|
17017
|
13677
|
|
220127
|
12507
|
16722
|
21172
|
25685
|
16144
|
13082
|
|
220228
|
12385
|
16694
|
21251
|
25923
|
16325
|
12761
|
|
220328
|
12657
|
16827
|
21723
|
26835
|
17148
|
13520
|
|
220427
|
12791
|
16712
|
21373
|
26163
|
18264
|
13608
|
|
220527
|
12673
|
16725
|
21404
|
26216
|
16871
|
13541
|
|
220627
|
12929
|
16637
|
21361
|
26248
|
17049
|
13222
|
|
220727
|
13310
|
16866
|
21745
|
26827
|
17465
|
13696
|
|
220829
|
13164
|
16820
|
21739
|
26887
|
17640
|
13930
|
|
220927
|
12840
|
16520
|
21213
|
26064
|
15949
|
13460
|
|
221027
|
13087
|
16669
|
21571
|
26713
|
16053
|
13568
|
|
221128
|
13012
|
16782
|
21901
|
27347
|
16550
|
13686
|
|
221227
|
12462
|
16395
|
21207
|
26249
|
15410
|
13156
|
|
230127
|
12483
|
16484
|
21506
|
26845
|
16151
|
12953
|
|
230227
|
12574
|
16582
|
21662
|
27075
|
16140
|
13006
|
|
230327
|
12551
|
16684
|
21921
|
26807
|
14543
|
12412
|
|
230427
|
12820
|
16876
|
22096
|
27677
|
15305
|
13022
|
|
230527
|
13123
|
17179
|
22773
|
28866
|
15427
|
13180
|
|
230630
|
13619
|
17505
|
23476
|
30108
|
16704
|
13228
|
|
230727
|
13345
|
17458
|
23441
|
30058
|
17002
|
13500
|
|
230828
|
13527
|
17257
|
23280
|
30031
|
16630
|
13458
|
|
230927
|
13451
|
17276
|
23437
|
30401
|
16101
|
13450
|
|
231027
|
13383
|
16993
|
22929
|
29585
|
15594
|
13264
|
|
231127
|
13925
|
17386
|
23716
|
30933
|
17113
|
13263
|
|
231227
|
13925
|
17520
|
23819
|
30963
|
17904
|
12897
|
|
240129
|
14133
|
17660
|
24379
|
32170
|
17876
|
13128
|
|
240227
|
14194
|
17946
|
25026
|
33355
|
17984
|
12574
|
|
240327
|
14415
|
17086
|
25453
|
34228
|
18314
|
13291
|
|
240430
|
14707
|
17962
|
25326
|
34118
|
18491
|
13327
|
|
240527
|
14835
|
17892
|
25374
|
34379
|
18734
|
12940
|
|
240627
|
15331
|
17971
|
25601
|
34842
|
19301
|
12799
|
|
240729
|
14858
|
17905
|
25380
|
34372
|
19778
|
12778
|
|
240827
|
14315
|
17888
|
25235
|
33929
|
17753
|
13340
|
|
240927
|
14495
|
18063
|
25626
|
34645
|
20529
|
13225
|
|
241028
|
15040
|
17968
|
25489
|
34457
|
21027
|
12737
|
|
241127
|
15043
|
17887
|
25452
|
34570
|
21012
|
12643
|
|
241227
|
15449
|
18102
|
25998
|
35576
|
20439
|
12651
|
|
250127
|
15204
|
17979
|
25790
|
35250
|
20213
|
12860
|
|
250227
|
14810
|
17751
|
25419
|
34683
|
19869
|
13090
|
|
250327
|
14843
|
17659
|
25446
|
34931
|
19761
|
13314
|
|
250428
|
14339
|
17603
|
25043
|
33930
|
18589
|
13185
|
|
250527
|
14138
|
17649
|
25375
|
34754
|
18612
|
13425
|
|
250627
|
14562
|
17867
|
25862
|
36030
|
19147
|
13937
|
|
SBI外債
|
日興20
|
日興40
|
日興60
|
SBIGREIT
|
日JREIT
|
投信月次収益率表 期間2019/1/28~2025/6/27(各データ数89コ)
|
日付
|
SBI外債
|
日興20
|
日興40
|
日興60
|
SBIGREIT
|
日JREIT
|
|
190128
|
|
|
|
|
|
|
|
190227
|
0.016699
|
0.00987
|
0.021455
|
0.030216
|
0.045216
|
0.017753
|
|
190327
|
0.012057
|
0.007219
|
0.004531
|
0.00468
|
0.025759
|
0.042992
|
|
190426
|
0.003885
|
0.002791
|
0.005997
|
0.00927
|
0.002821
|
-0.00329
|
|
190527
|
-0.00955
|
-0.00803
|
0.035187
|
-0.0271
|
-0.01105
|
0.008898
|
|
190627
|
0.006512
|
0.00746
|
-0.04383
|
0.007656
|
-0.02241
|
0.003864
|
|
190729
|
0.004227
|
0.00462
|
0.007568
|
0.010394
|
0.024127
|
0.037486
|
|
190827
|
-0.00163
|
-0.00265
|
-0.0164
|
-0.03026
|
-0.02425
|
0.033551
|
|
190927
|
0.010324
|
0.012191
|
0.029524
|
0.046763
|
0.052549
|
0.057823
|
|
191028
|
0.006216
|
0.001498
|
0.008514
|
0.015634
|
0.025165
|
0.027737
|
|
191127
|
0.012356
|
0.007415
|
0.014969
|
0.022463
|
-0.00303
|
-0.00172
|
|
191227
|
-0.00493
|
-6.2E-05
|
0.005256
|
0.010503
|
-0.00132
|
-0.03149
|
|
200127
|
0.002352
|
0.001299
|
-0.00173
|
-0.00476
|
0.018111
|
0.013586
|
|
200227
|
0.01978
|
-0.00933
|
-0.024
|
-0.03856
|
-0.02396
|
-0.01216
|
|
200327
|
-0.0254
|
-0.02557
|
-0.04262
|
-0.06024
|
-0.27385
|
-0.27471
|
|
200426
|
0.005819
|
0.003648
|
0.005986
|
0.008477
|
9.16E-05
|
0.030873
|
|
200527
|
0.005869
|
0.012752
|
0.026778
|
0.040928
|
0.052391
|
0.029056
|
|
200629
|
0.01242
|
0.000315
|
0.006955
|
0.004359
|
-0.00174
|
0.024863
|
|
200727
|
0.006422
|
0.006482
|
0.007796
|
0.017267
|
0.005493
|
0.011754
|
|
200827
|
0.000654
|
0.006441
|
0.014018
|
0.021779
|
0.041446
|
0.042658
|
|
200928
|
-0.01112
|
0.001118
|
0.002304
|
0.003472
|
-0.03996
|
0.006507
|
|
201027
|
0.000248
|
-0.00118
|
-0.00291
|
-0.00455
|
0.010927
|
-0.04667
|
|
201127
|
0.002314
|
0.019013
|
0.037707
|
0.057724
|
0.079695
|
0.02666
|
|
201228
|
0.003463
|
0.002378
|
0.004394
|
0.004783
|
-0.00683
|
0.036193
|
|
210127
|
-0.00386
|
0.006448
|
0.014845
|
0.020575
|
0.02632
|
0.03781
|
|
210301
|
0.002805
|
-0.00085
|
0.005231
|
0.013913
|
0.033596
|
0.092469
|
|
210329
|
0.017522
|
0.020567
|
0.025923
|
0.034766
|
0.080241
|
0.01163
|
|
210427
|
-0.00259
|
-0.00693
|
-0.00681
|
-0.01025
|
0.032812
|
0.028702
|
|
210527
|
0.011105
|
0.002626
|
0.004209
|
0.005703
|
0.022577
|
0.01643
|
|
210628
|
0.007616
|
0.006548
|
0.012479
|
0.018449
|
0.044421
|
0.041648
|
|
210727
|
0.005808
|
0.002247
|
0.000419
|
-0.00137
|
0.008418
|
-0.00189
|
|
210827
|
-0.00554
|
-0.00124
|
-0.00144
|
-0.00172
|
-0.00301
|
0.010155
|
|
210927
|
0
|
0.010694
|
0.023418
|
0.036305
|
-0.00453
|
-0.02517
|
|
211027
|
0.019726
|
-0.00175
|
-0.00396
|
-0.00266
|
0.063113
|
-0.01031
|
|
211129
|
-0.00616
|
-0.00562
|
-0.00923
|
-0.01699
|
-0.01707
|
-0.02508
|
|
211227
|
0.004317
|
0.004594
|
0.008298
|
0.012049
|
0.029835
|
0.008108
|
|
220127
|
-0.02259
|
-0.0197
|
-0.03205
|
-0.04439
|
-0.0513
|
-0.0435
|
|
220228
|
-0.00975
|
-0.00167
|
0.003731
|
0.009266
|
0.011212
|
-0.02454
|
|
220328
|
0.021962
|
0.007967
|
0.022211
|
0.035181
|
0.050413
|
0.059478
|
|
220427
|
0.010587
|
-0.00683
|
-0.01611
|
-0.02504
|
0.06508
|
0.006509
|
|
210527
|
-0.02478
|
0.005146
|
-0.00641
|
-0.01594
|
-0.1717
|
0.009259
|
|
210628
|
0.007616
|
0.006548
|
0.012479
|
0.018449
|
0.044421
|
0.041648
|
|
210727
|
0.005808
|
0.002247
|
0.000419
|
-0.00137
|
0.008418
|
-0.00189
|
|
210827
|
-0.00554
|
-0.00124
|
-0.00144
|
-0.00172
|
-0.00301
|
0.010155
|
|
210927
|
0
|
0.010694
|
0.023418
|
0.036305
|
-0.00453
|
-0.02517
|
|
211027
|
0.019726
|
-0.00175
|
-0.00396
|
-0.00266
|
0.063113
|
-0.01031
|
|
211129
|
-0.00616
|
-0.00562
|
-0.00923
|
-0.01699
|
-0.01707
|
-0.02508
|
|
211227
|
0.004317
|
0.004594
|
0.008298
|
0.012049
|
0.029835
|
0.008108
|
|
220127
|
-0.02259
|
-0.0197
|
-0.03205
|
-0.04439
|
-0.0513
|
-0.0435
|
|
220228
|
-0.00975
|
-0.00167
|
0.003731
|
0.009266
|
0.011212
|
-0.02454
|
|
220328
|
0.021962
|
0.007967
|
0.022211
|
0.035181
|
0.050413
|
0.059478
|
|
220427
|
0.010587
|
-0.00683
|
-0.01611
|
-0.02504
|
0.06508
|
0.006509
|
|
220527
|
-0.00923
|
0.000778
|
0.00145
|
0.002026
|
-0.07627
|
-0.00492
|
|
220627
|
0.0202
|
-0.00526
|
-0.00201
|
0.001221
|
0.010551
|
-0.02356
|
|
220727
|
0.029469
|
0.013765
|
0.017977
|
0.022059
|
0.0244
|
0.035849
|
|
220829
|
-0.01097
|
-0.00273
|
-0.00028
|
0.002237
|
0.01002
|
0.017085
|
|
220927
|
-0.02461
|
-0.01784
|
-0.0242
|
-0.03061
|
-0.09586
|
-0.03374
|
|
221027
|
0.019237
|
0.009019
|
0.016876
|
0.0249
|
0.006521
|
0.008024
|
|
221128
|
-0.00573
|
0.006779
|
0.015298
|
0.023734
|
0.03096
|
0.008697
|
|
221227
|
-0.04227
|
-0.02306
|
-0.03169
|
-0.04015
|
-0.06888
|
-0.03873
|
|
230127
|
0.001685
|
0.005428
|
0.014099
|
0.022706
|
0.048086
|
-0.01543
|
|
230227
|
0.00729
|
0.005945
|
0.007254
|
0.008568
|
-0.00068
|
0.004092
|
|
230327
|
-0.00183
|
0.006151
|
0.011956
|
-0.0099
|
-0.09895
|
-0.04567
|
|
230427
|
0.021433
|
0.011508
|
0.007983
|
0.032454
|
0.052396
|
0.049146
|
|
230527
|
0.023635
|
0.017954
|
0.030639
|
0.04296
|
0.007971
|
0.012133
|
|
230630
|
0.037796
|
0.018977
|
0.03087
|
0.043026
|
0.082777
|
0.003642
|
|
230727
|
-0.02012
|
-0.00268
|
-0.00149
|
-0.00166
|
0.01784
|
0.020562
|
|
230828
|
0.013638
|
-0.01151
|
-0.00687
|
-0.0009
|
-0.02188
|
-0.00311
|
|
230927
|
-0.00562
|
0.001101
|
0.006744
|
0.012321
|
-0.03181
|
-0.00059
|
|
231027
|
-0.00506
|
-0.01638
|
-0.02168
|
-0.02684
|
-0.03149
|
-0.01383
|
|
231127
|
0.040499
|
0.023127
|
0.034323
|
0.045564
|
0.097409
|
-7.5E-05
|
|
231227
|
0
|
0.007707
|
0.004343
|
0.00097
|
0.046222
|
-0.0276
|
|
240129
|
0.014937
|
0.007991
|
0.023511
|
0.038982
|
-0.00156
|
0.017911
|
|
240227
|
0.004316
|
0.016195
|
0.026539
|
0.036836
|
0.006042
|
-0.0422
|
|
240327
|
0.01557
|
-0.04792
|
0.017062
|
0.026173
|
0.01835
|
0.057022
|
|
240430
|
0.020257
|
0.05127
|
-0.00499
|
-0.00321
|
0.009665
|
0.002709
|
|
240527
|
0.008703
|
-0.0039
|
0.001895
|
0.00765
|
0.013142
|
-0.02904
|
|
240627
|
0.033434
|
0.004415
|
0.008946
|
0.013468
|
0.030266
|
-0.0109
|
|
240729
|
-0.03085
|
-0.00367
|
-0.00863
|
-0.01349
|
0.024714
|
-0.00164
|
|
240827
|
-0.03655
|
-0.00095
|
-0.00571
|
-0.01289
|
-0.10239
|
0.043982
|
|
240927
|
0.012574
|
0.009783
|
0.015494
|
0.021103
|
0.156368
|
-0.00862
|
|
241028
|
0.037599
|
-0.00526
|
-0.00535
|
-0.00543
|
0.024258
|
-0.0369
|
|
241127
|
0.000199
|
-0.00451
|
-0.00145
|
0.003279
|
-0.00071
|
-0.00738
|
|
241227
|
0.026989
|
0.01202
|
0.021452
|
0.0291
|
-0.02727
|
0.000633
|
|
250127
|
-0.01586
|
-0.00679
|
-0.008
|
-0.00916
|
-0.01106
|
0.01652
|
|
250227
|
-0.02591
|
-0.01268
|
-0.01439
|
-0.01609
|
-0.01702
|
0.017885
|
|
250327
|
0.002228
|
-0.00518
|
0.001062
|
0.00715
|
-0.00544
|
0.017112
|
|
250428
|
-0.03396
|
-0.00317
|
-0.01584
|
-0.02866
|
-0.05931
|
-0.00969
|
|
250527
|
-0.01402
|
0.002613
|
0.013257
|
0.024285
|
0.001237
|
0.018203
|
|
250627
|
0.02999
|
0.012352
|
0.019192
|
0.036715
|
0.028745
|
0.038138
|
|
SBI外債
|
日興20
|
日興40
|
日興60
|
SBIGREIT
|
日JREIT
|
第1回目 2025年4月7日
1 はじめに
就職すると、まず、公的保険制度に加入し、失業、労働災害、疾病、介護等の保険事象が、身にふりかかって来た時の備えをします。同時に、生涯にわたる資産形成は、公的年金制度および財形制度を利用しつつ、毎月の給与および夏冬2期の賞与を、天引きして、利息、配当、収益などが非課税になる資産に投資することが、基本です。公的年金制度(国民基礎年金+厚生年金)、財形制度(住宅財形550万円+年金財形550万円)、企業年金(企業型年金、個人型確定拠出年金iDeCo)および新NISA制度(家族一人あたり終身1800万円)の投資可能資産総額は、平均的勤労者が、可処分所得から、毎月の消費支出を引いた、貯蓄額をもとに、定年まで、各種資産に投資する合計額を超えています。
いわゆる資産家は、制度的非課税枠を超える自己資産を所有、経済・金融知識があり、自分で、資産運用でき、資産収益を平均以上、稼ぐことができる人です。自己資産が多いが、資産運用に専念できない人は、大口資産投資専門業者に資産を委ねることができます。
2025年の資産形成教室の方針
『資産形成論 2025年テキスト』第2章において、公的保険制度、年金制度および財形制度の概略を頭に入れることを目的としています。2024年1月から、新NISA制度が、はじまり、特に、株式投資を主体とする投信信託および個別株への投資額が、毎年、つみたて枠NISAに120万円、成長枠に240万円を上限として投資でき、生涯上限1800万円まで投資信託および上場株式に投資できるようになりました。夫婦では、3600万円まで、非課税になります。
第3章では、年金制度、財形制度および新NISA制度を用いて、資産形成する資産の特徴と、それらの資産を市場で購入する場合、そのような制限があるかを学びます。また、売買する資産の価格は、計算方法が違っている場合があります。その評価方法を実例で計算します。先物商品では、予想収益率およびその標準偏差が価格の計算に入ります。
第4章では、個人が、一生涯にわたるライフ・サイクル期間において、定期収入を消費に支出し、過不足を自己金融あるいは、金融機関から融資を受け、貯蓄、返済をくりかえし、退職後の年金生活に十分な資産形成をすることを、計算で求めます。ライフ・サイクルの途中では、定期収入を超える出費があるイベントがあります。たとえば、子供の進学時の入学金・授業料等です。また、車や住宅を購入する場合です。その過不足を自己金融すれば、資産を取り崩し、あるいは、金融機関から融資を受け、返済します。退職すれば、退職金と年金および老後の蓄えで、残りの生涯を過ごすことになります。そのようなイベントに対応して、定期収入から天引き貯蓄される額を、財形制度(住宅財形550万円+年金財形550万円)、企業年金(企業型年金、個人型確定拠出年金iDeCo)および新NISA制度(家族一人1800万円)に、配分して、各イベントに備える資産形成は、どのように、決めるとよいかを次のように理論的に求めます。
経済学の金融論では、家計は、1期間に稼いだ所得と繰越貨幣量をもとに、予算制約式を立て、その中で、効用関数を最大にする消費支出と次期繰越貨幣量を求めます。この計画期間を終身までのばすと、ライフ・サイクル理論になります。例えば、80歳まで、計画することができます。
① 貨幣一時的一般均衡論を確実性下2期間モデル
ライフ・サイクル理論の応用は、1期間に稼いだ所得と銀行からの借入金をもとに、消費支出を決めて、次期から、返済期間ほど、返済金を決めることができます。
② 貨幣一時的一般均衡論を応用して、不確実性下貨幣・債券・株式の現物・債券・株式の先物市場均衡論を説明する
①では、将来が確実性下の多期間一般均衡理論でした。不確実性下にある2期間モデルで、前期保有の3資産と今期繰り越し貨幣をもとに、期待効用を最大にするように、今期、資産需要を決めます。その際、期間2では、2資産の先物市場が開かれているとします。2資産の先物契約量が決定されます。
③ 資産先物理論とオプション理論の関係を説明し、オプション市場の使い方を考える
②で契約した資産の先物市場価格をもとに、期間2において、いかなる価格が成立しても、資産価値が変化しないように、オプション保険料を、今期支払う、または、受け取るオプション理論を説明します。
第5章では、資産選択理論を3資産モデルで説明し、最適ポートフォリオに従った、
資産売買を説明します。不確実性下にある資産市場で、3資産の投資割合を決定しました。
資産形成論では、次期繰越貨幣量と前期の投資収益を、3資産、預金、国債、株式に、平均収益率と、リスクの指標である平均収益率の標準偏差で作られる有効フロンティアから、期待効用関数が最大となる、資産構成(ポートフォリオ)を選択します。
第6章では、若年世代、壮年世代、老年世代の3世代のライフイベントを想定し、第5章の理論・方法にもとづく資産形成計画、運用・管理を考えます。運用管理については、運用は、天引きの定額拠出を原則としていますから、そのような運用法は、商品を固定し、定額で購入するドルコスト平均法が、推奨されます。しかし、運用期間が6カ月を越えると、複数以上の商品では、経済・金融変動で、収益率の平均値やその標準偏差が、予定の幅を外れることが生じます。そのときは、当該商品の購入を止め、範囲内の商品を購入するリバランス法があります。
若年世代 新卒、海原氏を例にとると、海原氏は、新卒で、入社後、10年間のイベント表を作成する。イベントは、仕事を習熟すること、婚活をすることである。企業キャリアアップ制度、厚労省キャリアアップ制度を利用、自己研鑽を心がけ、年収を少なくとも年12万円昇給させる。入社10年間で、この最低限の昇給制度がない企業は、大学卒を必要としない業種である。
2000年の米国IT不況、2003年の金融再編で、毎年の就職活動は、内定率が下がり、超氷河期になった。2008年リーマン・ショックで、米国は再び、金融恐慌に陥り、欧州も南欧を中心に、国債価格が下落し、不況に入った。その間、貿易が縮小、日本経済の停滞は継続した。大手企業は、新入社員の選好を絞り、速戦のある学生を採用するので、大学4年間で、入社前職業訓練をするように、4年間段階的に、大学キャリア教育カリキュラムで、自己研鑽の方法を身につけさせようになった。現在も、そのカリキュラムは、全国の大学で、実施されているはずである。
新卒社員海原氏は、入社した企業で研修をし、10年間のライフイベントに、キャリアアップの社内外、自己研修プログラムの時間を取り、各種資格の一つをとって、有資格者の昇給を手にする。その費用は、入社3年から、厚労省、当該企業の助成金を得られる。私のゼミでは、FP3級、宅地建物取引主任者、簿記3級受験を勧め、ゼミでも、過去問を解いていた。2000年から、大卒の就職事情が悪化していたため、就職指導もするようになったのである。就職後も、昇給には、資格があると、職種の範囲が増えるので、資格試験問題の解き方は、身に着けた方がよい。その自己負担金と、時間を定期的にさかなければならない。
消費支出は、年収の8割である。消費生活を充実しつつ、自己研鑽費、婚活費は消費支出に含まれる。年2回のボーナスで、実物資産形成として、住宅頭金500万円を貯蓄する。収支差額が出るが、これを金融資産形成に使う。テキストでは、海原氏のイベント表にもとづく期末貸借対照表を作成しているが、その運用益を反映していない。本教室では、この運用益が出る方法を学ぶ。
最後に、実際の投資は、商品を固定し、定額で購入するドルコスト平均法をとり、半年以上1年で、その間の経済・金融変動で、収益率の平均値やその標準偏差が、予定の幅を外れることが生じる。そのときは、当該商品の購入を止め、範囲内の商品を購入するリバランス法をとる。したがって、ドルコスト平均法の投資方法は、経済学でいう動学的な経済・金融情勢に判断に基づいて、動学的な投資方法であることが分かる。
資産形成計画、運用・管理には、政策、景気等の変動を予想することが重要な視点であるので、2025年、9月15日から12月22日まで15回の予定で、財政・金融政策とマクロ金融経済について、『金融論2025年テキスト』を解説する。
経済政策について
コロナ禍において、日本政府の長期政策方針が転換されました。
1)地球温暖化対策には、各国経済が、持続して、成長を続けながら、温暖化ガス排出ゼロの経済・社会を実現できるかどうかが問題であり、そのための技術革新の方向付けをし、投資しつつ、経済・社会を誘導しなければなりません。政府は、2050年実質ゼロの目標を取っています。実際に、政府は、ウクライナ戦争を機に、実質ゼロの目標を取り入れた、エネルギー源の多様性に向かった行動計画をしている。
2)実質ゼロ目標年次計画にしたがう、国際技術革新のための投資計画、中国の一帯一路世界戦略に対抗して、自由開放貿易圏防衛協力計画が、新たに策定され、民生用車両、航空機、船舶、陸上軍車両、軍艦船、軍用機、ミサイルのCO2排出ゼロ化のため、新燃料、新型エンジン装備によって、輸送CO2排出ゼロ化を実現する方向性が出てきました。
3)デジタル庁の設置により、経済活動および社会活動によって、送受信される情報量が多い情報社会が、日本の仮想情報社会で、実現する方向性で、政府が活動するようになりました。世界の情報社会に、接続され、情報の送受信が盛んになります。
4)中国の半導体戦略に対抗して、米欧日台韓の半導体開発が、自前主義に移行しました。日本の半導体研究開発は、全分野にわたって、日本で生産されるわけではなく、得意な分野だけ、日本で生産していました。政府は、開発促進策をとり、熊本県に、台湾企業の工場を誘致しました。半導体不足で、家電、情報機器、自動車の製造に1年以上の遅れが出て、輸出減、原油・LNGインフレの輸入増で、日本独自の金融緩和の世界金利差が5%開き、円安になり、日本のGDPを下げました。今後、半導体関連企業は、国策支援をバックに、半導体全分野で、自前開発に投資をするかもしれません。
岸田政権は、以上の基本方針に従いつつ、長期政策方針にもとづき、日本経済を成長路線に乗せて、成長成果を労使双方が分配を享受でき、税制・投資資金支援をうけられる経済政策を目指しているように見えます。
2024年8月自民党総裁選で、石破氏が総裁になり、10月首相に指名された後、衆議院を解散、裏金問題とインフレ対策の終了で、与党は過半数割れし、少数野党に転落しました。石破首相は、再指名を受けましたが、過半数野党の政策を取り入れた予算案を2025年3月末可決しました。石破氏の経済政策は、安部・菅・岸田政権までの政策を変更した結果になっています。
金融政策について
日本経済は、大企業の寡占価格が市場を支配していて、物価はほとんど動きません。デフレではありません。ところが、ウクライナ戦争突入前後から、エネルギー価格、食料品価格が5%以上上がり続け、黒田日銀は、賃金率上昇を伴わないということで、少なくとも、金融緩和政策は、維持しました。その間、新規国債10年債利回りが2022年4月1日0.215、2023年3月31日0.32、債券先物10年債(6%)の利回りが、2022年4月1日0.688、2023年3月31日0.802でした。その差は2022年4月1日で0.482、2023年3月31日0.473でした。これが黒田地銀のイールド操作いう、仕事でした。日本国債のプレーヤーは国と日銀で、イールド操作して、円安、原材料価格高騰に、全く、効果はなかった。
金融緩和政策の離脱ために、国債を一定率で減少させる資産調整を一切いなかったために、黒田総裁以降の日銀総裁は、金利利上げすれば、国債市場の買い手に安く保有国債を手放さざるを得なくなる。そのままでは、日銀バランスシートの[貸付金+債券|預金]の資産<預金で、日銀は破たんする。国内外の関係者、専門家も、黒田総裁が退任するまで、何もしない日銀だろうと予想して、資金運用、調達して来た。国債市場を機能させるには、イールド操作は止めざるを得ない。
世界的にインフレが燃え盛り、経済成長しなくなり、実質賃金率が低下し、国民の購買力が減少しました。円高、2022年4月1日122円が、2023年3月31日133.48円になり、輸入燃料、食料の高騰に、国民生活は圧迫されました。
物価上昇率は、一般物価指数の上昇率を言い、名目賃金率は、物価指数には入りません。黒田日銀では、物価上昇率2%と政策目標でした。物価上昇率+名目賃金率上昇率を政策目標に入れる中央銀行はありません。なぜなら、賃金率は、所得分配構造から決まり、社会主義国では、国の機関が、最低賃金と賃金階級を決めます。欧米では、最低賃金は、各自治体で決まりますが、最低賃金以上の賃金階級は、労使双方で決めます。賃金上昇に対して、中央銀行では、関与する政策手段はありません。黒田日銀も、賃金上昇率が伴わないとは言いましたが、2%以上あれば、金融引締めに移行するとは、最後まで言及しませんでした。2022年3月から、毎月、消費者物価指数は2%を越えました。その間、最低賃金は全国で、上昇しました。しかし、基本給が上がらないので、一貫して、実質賃金率(実質賃金率は、賃金率Wを物価指数Pで割ったW/Pで定義します。)は減少し、生活困窮者、年金生活者に、インフレによる生活水準の切り詰めが常態化しています。2023年の春闘から、大企業も数パーセントの賃金上昇に踏み切りました。
2023年4月、植田日銀総裁に交代しましたが、依然、日銀はインフレを阻止できていません。黒田日銀の物価上昇および物価上昇に伴う賃金上昇が顕在化しきますので、金融引締めへ政策変更しなければ、2023年秋まで、インフレは止まらない。
2024年3月ゼロ金利政策を解除、政策金利を0.1%としました。2024年7月0.25%に、2025年1月0.5%に利上げしました。2025年1月に就任したトランプ大統領の関税政策で、日本は2025年4月9日から、24%の関税が賦課されます。現在、株式市場は、下落し、円高に方向が振れています。日本から米国への輸出が減少することのGDP減少が0.7%あるとの推計もあります。植田日銀総裁は、政策金利を据え置きしそうです。
マクロ金融経済モデルと財政・金融政策の効果分析
『金融論2024年テキスト』では、マンデル・フレミング開放経済モデル(MFEXモデル)を使って、財政・金融政策の有効性を理論的に論証しています。資産の運用は、ドルコスト平均法で、運用管理は、リバランス法を取っています。ともに、経済が変動すると、資産構成を変更する必要があります。
MFEXモデルは、比較静学あるいは比較動学モデルであり、与件の一つが変化すれば、長期均衡値に収束する経路を表します。経済成長論や景気変動論のテキストでは、比較動学モデルでなく、人口成長率、生産関数に技術進歩率が仮定され、動学方程式が、一定の比率を満たして、成長するかを示しています。MFEXモデルは、ケインジャンの領域である不均衡市場と新古典派の領域である均衡市場の2種類に分けて、分析しました。経済成長論や景気変動論も2種類あります。
貨幣をふくむ3資産、外国資産がある経済成長論や景気変動論は、複雑すぎて、テキストになるほどの典型モデルはありません。要するに、経済学は、内生変数、外生変数が、経済主体を増やせば、それだけ、増えてきて、物理学より、宇宙物理学のような、無数の天体の動きを、統一した理論で把握できるのかという話になるのです。しかし、手に負えなくなるほどの変数はまだない貨幣的MFEXモデルの均衡市場モデルを貨幣的経済成長論・景気変動から、動学微分方程式を設定し、解経路を求めれば、資本主義経済の発展経路を理論的に示すことになります。これが、経済予測のトレンドを理論的にしめすことになります。
第15週までに、景気,政策,海外の景気,政策等の変動を、市場関係者が予測するように理解することはむつかしい。そこで、毎週、日本経済新聞日曜版「今週の予定」から、イベントの「今週の市場」に与える影響を推測します。保有資産や購入予定の資産は、その結果を反映します。なぜそうなるかは、今年後半の『金融論2025年』によって、理論的な方向性を説明します。
変動要因の発表は、各証券会社のHPに、スケジュールが公表されています。重大発表は、情報が必ず漏れ伝わってくるので、市場の商品は、発表前に、反応し、価格が上昇するか、下落してきます.理論にしたがった各商品と変動要因を表にすると次のようになります。
商品 変動要因 海外
債券 日銀の政策会合 日銀短観 米国準備制度理事会 EU中央銀行
消費者物価 為替レート 消費者物価指数 失業率
株式 政府予算 政策の変更 政府予算 政策の変更
四半期GDP 四半期GDP
企業業績 企業業績
リート 長期金利 都市の地価発表 長期金利 都市の地価発表
為替 貿易収支 資本収支 日米の金利差 戦略商品(原油、金)
バランス 株式20 40 60の構成要素に対して,上記の変動要因按分
インデックス 債券の構成要素,株式の構成要素に対して,上記の変動要因
ETF 債券の構成要素,株式の構成要素に対して,上記の変動要因
首脳会談、政策機関の会議の予想、結果は、新聞各紙に観測記事が載るので、参考になります。本教室では、日本経済新聞の毎日曜日の今週の予定と先週の結果を載せています。統計調査の発表は、各省庁、各業界団体、各証券会社のサイトに、掲載されています。マネックス証券のホームページ「投資情報『経済指標カレンダー』」が各指標の予想、実現値が出ていて、過去1年間フォローできます。
毎回、2024年12月から、毎月、日本、米国、中国の統計データを掲載しています。それらのデータは、主に、景気変動を四半期国内総生産GDPで予測する指標です。
国内総生産GDPは、総供給=総需要の等式では、GDP=GDE+統計誤差です。国内総支出GDE=C+Iv+I+G+Ex-Imと定義すれば、GDPの速報値では、左辺の数値が確定するのは2年後ですから、右辺のGDEに従って、各需要の構成要素C、I、G、Ex、Imが発表されます。それらのデータをもちいて、構成要素の重回帰曲線を推計します。MFEXモデルに従い、四半期国民総支出関連データによって、簡易的に、次の四半期の国民総支出を試算することに取りかかっています。
今週(2025年4月7日~4月11日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、日銀3月の全国企業短期経済観測調査の発表がありました。4月2日、トランプ大統領は、米国との貿易相手国に対し、相互関税を賦課しました。日本は24%でした。世界一律、基本税率10%を日本時間5日13時1分に発動しました。
今週のイベントは、米国は、上乗せ税率を日本時間9日13時1分に発動します。12日大阪・関西万博開会式があります。
経済統計は、次の発表がありました。
予想値 実現値
2025年
3月31日 日3月鉱工業生産 1.1% 0.3%
中3月製造業PMI 50.3 50.5
4月1日 日2月完全失業率 2.4%
2月有効求人倍率 1.24倍
日銀短観大製造業先行き 10 12
業況 12 12
大非製造業先行き 29 28
業況 33 35
中3月財新製造業PMI 50.6 51.2
米3月ISM製造業景気指数 49.9 49.0
2日 米2月耐久財受注 0.9 % 1.0%
3日 米2月貿易収支 -1100 億円 -1227億円
3月ISM非製造業 53.2 50.8
4日 日2月全世帯家計調査 -0.5%
米3月完全失業率 4.1% 4.2%
経済統計は、次の発表があります。
予測値
7日 日2月毎月勤労統計 2.9%
2月景気動向指数一致 116.6
先行 107.9
8日 日2月国際収支貿易収支 5380億円
3月景気ウォッチャー調査
9日 日3月消費動向調査 34.8
3月工作機械受注額
10日 米3月消費者物価指数 2.6%
中3月消費者物価指数 0.1%
第2回目 2025年4月14日
2章 公的保険および公的年金制度、企業年金および個人資産形成制度
就職した場合、公的保険制度および公的年金制度に、就職先を通じて加入することになります。さらに、退職後の公的年金を補う企業年金制度および個人資産形成制度が、就職先の制度によって、選択可能です。前者は、就職先としては、できれば、定年まで勤めてもらいたいため、企業年金制度によって、退職金をつみたて、退職時に、一時金あるいは年金として受け取ることができるようにした制度です。
個人資産形成制度は、人生100年の長寿社会を政府が認識し出し、そのために、公的年金、企業年金を補充して、個人が老後の蓄えを保有する場合、制度的優遇措置を取るための制度です。これは、老年世代が、人生平均寿命85歳を目標にすると、70歳を過ぎれば、リスクレスの定期預金で貯蓄しがちですが、昨今の長期ゼロ金利政策では、利息は、蚊の涙でしかありません。それでは、人生100年とすると、実は、介護老人のリスクが増大し、そのための出費が増加するのです。いわゆる、長生きリスクが高くなるので、元気なうちは、リスクオンで老後の蓄えを成長させなければならない事例が増えてきました。
他方、公的年金について、2004年頃の年金問題では、新聞記事に、「団塊世代より若い世代は、次第に、保険料総額に支給総額が等しくなる」と試算されていました。それゆえ、65歳支給開始になりました。この話を当時の学生にすると、講義のあと、「私は、国民年金は払いません。」と言いに来たほどです。
私が勤めていた関西では、2019年から、新入生人口が10年間減少する大学淘汰の時代に入り、4年後から新入社員が減少していきます。日本は、人口減少時代に入り、高齢年金支給者の割合が3割を超えだすと年金財政が悪化し、いずれ、70歳支給開始もありうるかもしれません。
コロナ流行期、明らかに、適齢期の男女が結婚や出産の延期をしたため、出生率が減少しました。コロナ後、壊れた機会が復活するかは、経済・社会活動の回復次第ですが、将来の年金財政に影響は避けられません。政府も少子化対策に、子供世代の養育負担を軽減する財政・税制措置を講じはじめています。政府の政策により、若年世代の幼年期の子育て費用、壮年世代の教育資金が軽減されるならば、従来通りの形成目標、住宅、老後の安心に重点を移すことができます。
資産形成を開始する若年世代、住宅ローンがあり、教育資金と老後の安心を貯蓄する壮年世代は、制度金融を利用すれば、利息、配当に課税されません。現役世代を15歳から64歳までの労働力人口とし、65歳から退職世代とします。2世代の利用可能な制度金融を表にすると次のようになります。
NISAつみたてNISAは、2024年度、新NISAに併合され、2024年1月から、新制度に変更されました。今年の教室の中で、新NISAを取り上げます。旧制度の資産は、そのまま、最大5年まで、保有できます。その後は、新NISA制度に従います。
世代別の制度金融
世代別 制度金融
1) 現役世代 公的保険 医療保険, 労働保険, 雇用保険, 介護保険(40歳から)
公的年金 国民年金, 厚生年金
企業年金 国民年金基金, 確定拠出年金(DC,iDeCo)
確定給付企業年金, 厚生年金基金, 年金払い退職給付
NISA、つみたてNISA
財形住宅貯蓄
財形持家融資制度
2) 退職世代 年金収入=公的年金(-税控除)
DC,iDeCo,財形年金,NISA,つみたてNISA等の取り崩し収入
公的保険料(国保,介護)、自宅の場合固定資産税納付
自宅, 不動産担保ローン契約,老人ハウスに終身契約
2.1 公的保険制度と民間保険
2024年テキストでは、制度の概要を厚生労働省のHPより、要約しました。
公的保険制度は、現役世代では、医療保険、労働保険、雇用保険、介護保険(40歳から)があります。事業所の規模、組織によって、これらの保険料や、給付金が異なり、雇用者の所得によっても、自己負担の保険料が異なります。
医療保険では、保険の事象が生じた場合、かかる費用に、自己負担金があります。介護保険の対象者に認定されると、介護保険サービスが提供されますが自己負担金は、1割か2割です。
私は、退職世代に属します。その立場から、公的保険と民間保険を資産形成の立場から、どうかけたらよいのかを考えます。
退職世代の公的保険は、国民健康保険および介護保険であり、所得に応じて、保険料がランクづけられています。健康診断は毎年、基本的な項目で無料、有料の案内が市役所から送られてきます。介護保険により、各種サービスを受けるのであれば、要介護認定を判定委員会にしてもらいます。その際、毎年、介護認定に至った事由で診療した医者から、診断書を委員会に提出してもらいます。要介護に認定されると、要介護1、2であれば、その地域のケアマネジャーと自宅介護の契約をし、毎月、介護計画を立て、介護施設のデイサービス利用、介護ヘルパーの自宅派遣、介護補助具等のレンタル契約できます。要介護3、4、5であれば、特別養護老人ホームに入所できます。例外的に、要介護1、2でも認知症の程度により、特養に入所できます。ただし、申し込み順です。
現職世代では、民間生命保険があります。現役世代に掛ける理由は、死亡保険金を年収の3倍以下で、掛けて置き、残された家族の生活保障を担保することです。退職に近づくと、退職後の終身医療保障に掛ける理由が切り替わります。成人病等の疾患を現役世代中に患った場合は、特に、入院、手術する場合があるので、国民健康保険でカバーできない自己負担金が発生し、要介護に認定され、介護施設を利用すると自己負担金が発生します。疾病と介護を民間保険金で補うようにすると、年金や資産形成資金から、自己負担金を支出しなくてもよいことになります。終身医療保険の死亡保険金は葬式ができますという程度、100万円にします。葬式は、最近は、家族葬が多く、身内だけで、葬儀会館で行う場合が増えてきました。
現役世代で、自家用車保険、住宅保険などの損害賠償保険をかけることがあります。
民間生命保険および民間損害賠償保険は、現役世代で、所得階層の内、余裕階層に属すれば、税制上、社会保険控除できますから、それらの民間保険の実質負担は減ります。医療・介護で、自己負担金が発生した場合は、確定申告で負担を還付されます。
今週(2025年4月14日~4月18日)のイベントと市場への影響度
先週は、米国は、上乗せ税率を日本時間9日13時1分に発動しました。10日金融市場の動揺を見て、米国は中国以外の相互関税賦課を90日延期することを発表しました。対中国関税は145%となりました。11日中国の報復関税は125%となりました。12日大阪・関西万博開会式がありました。
今週は、13日大阪・関西万博が10月13日まで開かれます。
先週の統計は、次の発表がありました。
予測値 実績値
7日 日2月毎月勤労統計 2.9% 3.1%
2月景気動向指数一致 116.6 116.9
先行 107.9 107.9
8日 日2月国際収支貿易収支 5380億円 7129億円
3月景気ウォッチャー調査 45.4 45.1
9日 日3月消費動向調査 34.8 34.1
3月工作機械受注額
10日 米3月消費者物価指数 2.6% 2.4%
中3月消費者物価指数 0.1% -0.1%
今週の統計は、次の発表があります。
予測値
14日 中3月貿易収支
日2月鉱工業生産指数 0.3%
16日 日2月機械受注 -0.7%
米3月小売売上高 4.2%
中1~3月期GDP 5.2%
3月小売売上高 4.2%
3月鉱工業生産指数 5.2
17日 ECB政策金利 2.4%
日3月通関ベース貿易収支 5040億円
18日 日全国CPI 3.7%
第3回目 2025年4月21日
個人資産形成制度の見取り図
2.2 公的年金制度、2.3 企業年金、2.4 勤労者少額財形制度
要点・公的年金制度の概要
・企業年金の概要
確定給付企業年金、確定拠出企業年金、個人確定拠出年金(iDeCo)
・勤労者少額財形制度
個人資産形成制度の見取り図
テキスト6章において、ライフ・サイクル・プランの例として、海原さん、山川家、高原家のイベント表を載せています。3人の個人資産を制度支援の資産形成制度を当てはめてみます。
海原さんは、大学を卒業して、23歳とします。65歳で、現在の会社を退職します。海原さんのイベント表は、30歳で結婚し、31歳で1子をもちます。家族ができると、山川家のライフル・サイクル・プランに移ります。したがって、海原さんは、30歳までのシングル・プランです。
海原さんイベント表
年齢 23 30 35
60 65
確定拠出年金(iDeCo)
財形住宅貯蓄 財形持家融資制度(フラット25) 住宅ローン完済 年金生活
成長枠NISA
つみたてNISA
山川氏は大学を卒業して、33歳とします。65歳で、現在の会社を退職します。山川氏のイベント表は、25歳で結婚し、26歳で1子をもちます。妻は共稼ぎです。結婚後の資産形成は、所有権は半分ずつです。基礎年金は、個別保有の権利ですが、共稼ぎの2人の厚生年金は、半分ずつに分割されます。その他の資産は、結婚期間の共同財産ですから、離婚すれば、半分ずつです。同様に、遺族年金は、半分です。
私のゼミ生で、離婚すると、結婚期間の厚生年金が半分に分割されるようになった、経緯を研究テーマに修士論文を書いたものがいます。当時、企業は、大企業は確定給付企業年金制度があり、従業員の拠出はなく、企業が退職時支払ってくれる退職金でした。この制度をもつ大企業に就職すると、退職時には、公的年金と企業年金の3階建ての年金がもらえるのです。企業は、毎月、支払うであろう給料を企業負債として、退職給付を積立て、退職時から、一時金か年金で支払う制度です。高原氏は、65歳で、年金生活に入っています。政府主管の年金・資産形成制度に基づいて、イベントを作成すると、次のようになります。
山川家イベント表
年齢夫
33 35 48 56 60 65 68
確定拠出年金(iDeCo) 年金生活
財形住宅貯蓄 財形持家融資制度(フラット25) 住宅ローン完済
成長枠NISA
つみたてNISA
妻 30 46 53 58 62 65
確定拠出年金(iDeCo)
年金生活
成長枠NISA
つみたてNISA
高原家イベント表
年齢夫 65
85
老齢基礎年金・厚生年金受給
確定拠出年金(iDeCo)受給
成長枠NISA
つみたてNISA
妻 65
85
老齢基礎年金・厚生年金受給
確定拠出年金(iDeCo)受給
成長枠NISA
つみたてNISA
自主的に運用管理できる資産形成制度は、確定拠出年金、成長枠NISA・つみたてNISA制度です。運用資産は、投資信託、株式を自由に選択できるようになりました。特に、株式を勤労者の資産形成に売買できるようにした新NISA制度は、日本型の資本主義の所有者構造の転換を意味します。かつて、西ドイツでは、国民、または従業員、経営者に株式を所有させ、企業の外国人支配を防衛する制度を支援していました。日本は、自由民主主義の政治制度と資本主義制度の経済制度を基本に、政治経済を管理、運営している国です。戦前からの財閥支配構造が、引き継がれてきましたが、バブル不良債権処理が10年で終了した2003年から、日本独特である、金融機関・会社の株式持ち合いは崩れ、外国支配の問題が政府・企業・金融機関に意識され、従業員株主・経営者報酬株式を支援、ここは、一番、広く国民に、長期保有の企業ファンを増やして、安定株主になってもらうことを意識した制度設計になっています。
2000年に入って、バブルの清算で、超氷河期に入り、退職給付の積み立て不足に陥り、従業員負債が増大するのを嫌い、確定給付企業年金から、確定拠出企業年金に移行する企業が増えていきます。金融危機で、企業の再編もあり、企業価値の永続性が壊れました。米国も同様に、ITバブルが崩壊し、確定給付型から、確定拠出企業年金401k制度を選択するようになります。その日本版が、確定拠出企業年金制度です。要するに、創業百年以上、事業を継続できなくなり、いわゆる、老舗倒産や、そのままの事業形態では、企業が存続できなくなったのです。
退職給付引当金と株価の関係を統計的に実証し、有意性を実証したゼミ生もいます。5年ごとの2004年、年金財政再計算を控え、年金問題が重大な政治課題だった時代です。金融リストラの時代でもあり、大阪府から、企業の広告看板が下ろされ、御堂筋の両側は、全国、海外の金融機関が軒を連ねていましたが、次々に撤退しまし、寂しくなっていった時代です。企業年金の、確定給付企業年金は維持できず、大企業でも、確定拠出型に移行するのが、新聞で話題になりました。国の年金財政の補完として、自己積立年金制度を充実させようということで、確定拠出年金制度が拡充されました。
一方、株式市場の低迷で、米国のファンドから企業乗っ取りが流行し、あの村上ファンドや堀江モンが評判になりました。従来、銀行・保険等金融機関が持ち合い株で、流動化を阻止していたのが、日本の金融システムが再編されにつれて、持ち株を売却する銀行・保険会社も増えました。国は、株式市場形成時代から、個人投資家を育成する行政をしませんでした。戦前は、オーナー企業、5大財閥で、機関銀行の持ち合いが普通で、浮動株が少なく、相場師が暗躍、「博打場」のように、株価が乱高下したと言われています。
戦後、企業は、株主総会において、総会屋に会場の株主を取り仕切ってもらい、経営者側優位に議事が進行するのが通常でした。これは、総会屋の横行がはなはだしく、株主民主主義の原則から、総会屋の議事進行妨害は出来なくなり、企業も総会屋を支援できなくなりました。
戦後、銀行の株式保有には5%以下というルールがあり、系列機関で、株式を持ち合えば、企業側は安定株主の議決権51%を確保できました。金融リストラが始まって、安定株主がいなくなってしまうと、株主民主主義が機能し、3年間業績不振の経営者には、解任動議が通ることになりました。
財務省は、証券市場が縮小するので、NISA制度で、個人投資家を投資可能な全世代に向けて、小口証券投資を税制で優遇しようとNISAが始まりました。同時に、金融商品のリスクを承知の上で、資産形成の方法を生徒・学生に学ばせる金融教育の機会を業界が提供し、文科省でも、小学校高学年から、金融教育を社会科学の分野で取り入れる流れがあります。個人は、50パーセント以上、銀行預金か保険で、資産形成をしていましたから、金融行政全体から、直接証券保有を推奨する体制に流れが進んでいるのです。1997年以降バブル退治がはじまり、100兆円以上の不良債権が処理され、戦後金融システムの再編が2003年にめどがつきました。5財閥+新興系列1の系列金融は集約され、企業間の株式持ち合い、系列金融の持合いは、解消されますが、海外ファンド等のハゲタカ株主が企業価値を切り売りすることも横行、、企業・金融の持合いが50%をわり、株主主権が総会で有効になりました。政府に、日本型の経営をする企業から、個人に安定株主になってもらう仕組みができないか、要望もあったかもしれません。ささやかな仕組みが、NISA制度であり、2024年からのNISA制度です。韓国は、日本と同じ財閥が、系列企業を持合いしています。中国は、基幹産業は政府が51%保有しています。日本は、財閥支配から、51%の株主に、従業員、経営者、日本国民になって、外国ファンドに経営権をTBOされないように、政府が制度的に配慮しているとも言えます。
2.2 公的年金制度
年金制度は、3階立ての構造をしており(本文の図)、1階は、20歳以上60歳までの国民が加入する老齢基礎年金です。2階は、勤労者であれば、雇用主の条件以上は強制加入である厚生年金です。3階は、企業年金です。
年金の保険料および給付は、賦課方式と積立方式があります。賦課方式は、毎年の保険料収入を年金受給者に配分する方法であり、国民年金、厚生年金が賦課方式です。積立方式は、加入者個人に対して、所定の期間、定期的に一定額の掛金を払込期間まで積立て、受給開始期以降、給付する方式です。掛金は全額、事業主負担の場合、自営業者等が負担する場合、企業年金等に加入していない従業員が負担する場合があります。本文では、国民年金、厚生年金の以下の項目をまとめています。
受給資格
受給開始年齢
保険料
年金額
国民年金の保険料と年金給付額算定方式について、将来の受給額については、日本年金機構のHP「ねんきんネット」で、保険料の支払い記録と年金受け取り見込み額を知ることができます。国民年金、厚生年金に、保険料とあるのは、年金に保険機能が付与されているためです。5年ごとに、国勢調査結果、人口統計等から、年金財政の均衡を再計算し、保険料を改訂します。厚生年金は保険料額表が公表されていて、給与明細書を保存していれば、簡易計算できます。厚生年金は、一元化されましたが、厚生年金機構に、一元化されていないので、もとの制度にしたがうしかありません。それゆえ、「厚生ねんきんネット」はないので、保険料の支払い記録と年金受け取り見込み額は、いろいろな金融機関等の簡易計算で、推測するしかありません。
いわゆる年金財政の危機は、国庫負担が50%となった国民年金の方で、厚生年金ではない。受給開始年齢を70歳にする、保険料支払いを65歳までにする、保険料を上げない代わりに、消費税を20%以上にし、消費税から直接徴収するとか、政官民学が主張する議論があります。
年金額が、年金数理計算で決まると、物価変動に対しては、物価スライド制があり、経済変動に対しては、マクロ経済スライド制があります。年金額の改訂は、物価上昇および経済成長率に依存する計算によって決められています。アベノミクス政策において、2%物価上昇、経済成長率?%の目標を5年間、前者は日本銀行が、後者は経済諮問委員会が政策を実施しました。目標は達成できず、日銀は、地方銀行の経営悪化を招き、借り手不足というか、地方は、高齢少子が進み、企業の廃業が進んでいます。2020年度、マクロ経済スライド制が発動され、年金増加額が0.2%に抑制されました。2021年度は、両制度は物価上昇、経済成長が規定に達成せず、発動されませんでしたが、年金は-0.1%減額されました。
国民年金財政には、過去の余剰金があり、保険料総額>給付総額の状況にあり、日本年金機構が、余剰金を運用していて、昨年からの米国の金融正常化政策により、株式市場が引き締まってきました。そのあおりで、日本の株式市場も下落しています。日本年金機構の運用状況は、公表されるので、株式に損失が出たようです。2019年9月から、日本株式市場に海外投資家の資金が流入し、米国の金融緩和回帰があり、米国の株式市場も上昇しましたが、中国の新型コロナウイルスの世界拡散が発生し、ダウは3分の1消滅しました。2020年7月から、規制は緩和されました。コロナショックから、財政支出で持ち直し、米FRBは、金融緩和に戻しました。2021年、コロナワクチンの接種率が上がるとともに、世界経済は、緩やかに、回復過程に入りました。
運用について、リスク資産は、民間運用会社に競争運用を委託する国もあります。日本の年金財政の危機は、高齢者の増加で、受給者が増加し、保険料総額<給付総額の状況となり、余剰金で差額が賄われので、余剰金が減少することです。
2.3 企業年金
企業年金は、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、個人確定拠出年金(iDeCo)に分けられます。確定給付企業年金が、企業の従業員からの負債となり、企業の事業業績が落ちると、企業は利潤から積立不足を補てんしなければなりません。株主の配当がその分減少するので、株価の減少要因になります。確定拠出企業年金に移行し、企業は一定額を拠出し、その運用は、従業員に委ねられます。確定給付企業年金と比較すると、退職給付引当金に入らないので、大企業も、この制度に移行するようになってきました。本教室は、従業員が、その場合の運用管理をどうするのかに答えるのが、大きな目的です。
大企業が確定給付企業年金制度をもっていますので、概要は省略しました。テキストでは、確定拠出年金と個人型確定拠出年金の概要は、詳しく、載せています。
今週(2025年4月21日~4月25日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、13日大阪・関西万博が開幕しました。10月13日まで開かれます。
今週のイベントは、21日から26日まで、ワシントンでIMF・世界銀行周期総会が開かれます。23日20ヵ国財務相・中央銀行総裁会議が24日まで、ワシントンであります。
先週の統計は、次の発表がありました。
予測値 実績値
14日 中3月貿易収支 -7367億元
日2月鉱工業生産指数 0.3% 0.1%
16日 日2月機械受注 -0.7% 1.5%
米3月小売売上高 1.4% 1.4%
3月鉱工業生産指数 -0.3% -0.3%
中1~3月期実質GDP 5.2% 5.4%
3月小売売上高 4.2% 5.9%
3月鉱工業生産指数 5.7% 7.7%
17日 ECB政策金利 2.4% 2.25%
日3月通関ベース貿易収支 5040億円 5441億円
18日 日全国CPI 3.7% 3.6%
今週の統計は、次の発表があります。
予測値
21日 米3月景気先行指数 -0.5
中4月最優遇貸出金利(LPR)
24日 米3月耐久財受注 1.4%
日4月東京都区部CPI 3.2%
3月スーパー売上高
第4回目 2025年4月28日
2.3 個人確定拠出年金(iDeCo)制度
2. 4 勤労者少額貯蓄制度・財形持家融資制度
2.5 NISA制度
2. 6 イベント表と資産形成制度の当てはめ例
要点・一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄
・成長投資枠NISA、つみたて投資枠NISA
・イベント表へ資産形成制度当てはめ
2. 3 企業年金のつづき 個人確定拠出年金(iDeCo)制度
山川氏イベント表で、妻の個人型確定拠出年金(iDeCo)が可能になっています。女性の資産形成について、山川氏と同様に、会社勤めで、同様に、ライフ・サイクル・プランを運用管理しているとする場合は、結婚後の共同資産形成になります。個人型確定拠出年金は、勤めている企業が、企業型確定拠出年金に加入していない場合、妻が専業主婦で、第3号被保険者である場合、個人で加入できます。転職や再就職の機会が多い業種であれば、企業加入していると、企業負担を再開できます。
2. 4 勤労者少額貯蓄制度と財形持家融資制度
勤労者少額貯蓄制度は、厚生労働省の所管で、勤労者財産形成貯蓄、勤労者財産形成年金貯蓄および財形持家融資制度があります。年金と住宅に対しては、利子等非課税措置があります。従業員の定着性効果を期待する企業では、従業員が金融機関と契約し、運用指示は本人であり、事業主は給与天引き、金融機関からの運用状況連絡を仲介するだけの負担です。必ずしも、就職した企業が、これらの制度に加入していない場合は、年金および住宅頭金をつくる財形住宅貯蓄は、個人確定年金制度(iDeCo)およびNISA制度を利用するとよいでしょう。
財形持家融資制度は、財形貯蓄・年金の残高に応じた融資を、事業主を通じて又は直接に、長期・低利な住宅ローンを35年間受けることができます。融資額は、財形貯蓄残高の10倍相当額(最高4,000万円)で、実際に要する費用の90%相当額までです。住宅金融支援機構の融資と併用できます。事業主は社内融資制度を国の資金の転貸で、負担を軽減できます。
勤労者財産形成住宅貯蓄は、住宅所有をライフ・サイクル・プランに入れている場合、財形持家融資制度を利用する、初期資金を貯蓄する制度として有用です。元金利子を含めて、550万円まで非課税ですから、その次の制度は、財形持家融資制度があります。
日本銀行の超金融緩和が10年続き、預金利子率は0・01%程度でしたから、月2万円、年間24万円を10年間、続けても、240万円+1万円以下の利息しかなりませんでした。住宅頭金や教育資金は、定期預金では、目標額を貯蓄するのは、無理で、投資信託にすれば、10年で2倍になっています。新規購入層の住宅頭金は、超金融緩和期と名目賃金上昇がなく、現在の30代は、10年間、目標額の半分しか貯蓄していないことになります。金融政策で、ゼロ金利政策を10年続けると、住宅ローン借入者には、金利負担が少なくてすむが、年々、新規購入者には、頭金が未達になり、政策解除すると、金利が上がり、購入費が上ります。世代で負担の不公平性を生んでしまいました。
住宅地の選択
各市の都市計画の用途地域を調べていると、昨今、農地は消滅し、都市計画は完成している市が多くなっていると思います。その中での選択ですから、家族で住みたくても、物件が少ないかもしれません。不動産の将来価値は、公示価格、売買例、利便性評価等で決まりますから、少なくとも、建物の耐用年数が来るまでに、土地の著しい減価が生じなければ、住宅投資は成功したことになるでしょう。
2.5 NISA制度
NISA制度は、金融庁所管で、2014年から始まった少額投資非課税制度(Nippon
Individual Savings Account)です。2016年から、ジュニアNISA、2018年からつみたてNISAが始まりました。ジュニアNISAは18歳まで原則、払出しができませんから、大学の教育資金に向いていますが、さらに、高校進学時に、特別払出しができれば、学資資金の性格がでて、よいかもしれません。つみたてNISAは20歳以上、20年間非課税ですが、制度の延長は定められていません。
新NISA制度
「令和5年度税制改正の大綱」において、NISA制度は、新NISA制度に移行、2024年度以降のNISA制度は、抜本的拡充・恒久化の方針が示されました。
開始時期 2024年1月から
対象者 18歳以上、1口座開設できる。
投資枠 つみたて投資枠 (併用化) 成長投資枠
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有期間 無期限 無期限
非課税保有限度額 1,800万円(内 成長投資枠1,200万円)
口座開設期間 恒久化 恒久化
投資対象商品 積立・分散投資に適した 上場株式・投資信託等
一定の投資信託 (毎月分配型投資信託等は除く)
2023年末までのNISA制度で投資した商品は、新NISA制度の外枠で、非課税制度を適用しますが、定められた保有期間が過ぎると、その商品を新NISA制度の口座に繰り越し(ロールオーバー)できません。
2. 6 イベント表と資産形成制度の当てはめ例
個人確定拠出年金(iDeCo)、勤労者少額貯蓄制度と財形持家融資制度および新NISA制度によって、家族全体のライフ・サイクル・イベントを設定し、資産を非課税で形成できるようになってきました。
日本銀行のゼロ金利政策は、解除されましたが、依然、政策金利は0.5%です。日本の金融商品だけの資産選択は、収益率目標を達成できそうもありません。本教室では、長期の資産運用を想定しますが、日本債券、日本株式、そのバランス、上場投資信託、不動産投資信託等の国産商品では、資産運用コスト以上の成績を上げるのは、難しそうです。第6章において、資産選択、定額購入、資産管理を学びますが、ここでは、イベント表と資産形成制度との対応させてみます。
イベント表の計画終身年齢
私の身の回りを見ると、死亡率は男性の方が高く、女性は低いのが普通のようです。山川氏が平均寿命で亡くなった場合、妻は余命があり、共同財産を相続することになります。老後の安心には、このことも、ライフ・サイクル・プランでは、考慮すべきイベントです。自民党が「人生百年」時代と言いますが、それを可能とする退職後のモデル生活は何も政策導入しませんから、男性の平均寿命が80歳から、20年延びる「稼ぎと体力」、社会保障があるわけない。むしろ、「失われた20年間」で、所得が失われたので、栄養不足による体力の減退により、80歳台にとどまると予想するのが普通でしょう。女性もやはり、90歳台に、「失われた20年間」の「稼ぎと体力」の減少効果が効いてくると思われます。退職後、なんらかの運動を継続し、ミネラル、ビタミン、たんぱく質が不足しがちの、1週間の3食献立に変化がなく、惣菜ばかりをたべていると、筋肉が落ち、寝たきりになるようです。老後の食生活は、野菜中心の脂肪・たんぱく質を減らした、精進料理かという、想像をする人がいますが、それでは、体力維持に必要な栄養素が不足するのです。食は、生命の根源に与える活力ですから、少ない稼ぎから、食費を節約はしない方が、元気で長生きできます。
私の『資産形成論2024年テキスト』では、山川氏は33歳であり、妻は専業主婦です。私自身は、妻に対して、資産形成を実行してきましたが、これは普通なのか、そうでもないのか。夫婦で、妻には、ライフ・サイクル・プランをどう考えて、実行しているのか、実態調査があるのでしょうか。
前回、ライフ・サイクル・プランの例として、海原さん、山川家のイベント表を載せました。それぞれのイベント表に資産形成制度を当てはめます。
海原さんイベント表と資産形成制度
海原さんイベント表で、各年の収支差額表が計算できると、勤労者少額貯蓄制度の内、勤労者財産形成住宅貯蓄によって、毎年、ボーナスを入れて、住宅取得頭金を550万円貯蓄することが、主要な資産形成の目的になります。結婚が難しくとも、退職後、老後の安心による、退職後の生活資金資産形成より、住居の手当はライフ・サイクル・プランでは最も重要です。それを控除した差額が、退職後の生活資金資産形成になり、個人確定拠出年金(iDeCo)を事業主の負担を利用しつつ、運用します。海原さんの場合は、毎月、最大1万円、残りは、中期目的の自己資産形成でNISA制度を利用します。海原さんの収入では、NISA制度の上限を超えることはありません。
海原さんイベント表
年齢 23 30 35
60 65
確定拠出年金(iDeCo)
財形住宅貯蓄 財形持家融資制度(フラット25) 住宅ローン完済 年金生活
つみたて投資枠NISA
成長投資枠NISA
資産家と違い、勤労者は、毎月の月給から、少額積み立てをします。制度金融では、預金以外の金融商品を、選択できますから、例えば、住宅資金の目標550万円は、10年より早く達成できます。教育資金でも、預金以外の金融商品で、長期積立をすれば、目標期間を短縮できます。
山川家イベント表と資産形成制度
山川氏の個人資産を制度支援の資産形成制度を当てはめてみます。山川氏は大学を卒業して、33歳とします。65歳で、現在の会社を退職します。山川氏のイベント表は、妻は、30歳で6歳の子がいます。
山川家イベント表
年齢夫
33 35 48 56 60 65
68
確定拠出年金(iDeCo) 年金生活
財形住宅貯蓄 財形持家融資制度(フラット25) 住宅ローン完済
つみたて投資枠NISA
成長投資枠NISA
妻 30 45 53 57 62
65
確定拠出年金(iDeCo)
年金生活
つみたて投資枠NISA
成長投資枠NISA
子 6
21
テキスト第6章では、資産形成の期間(フロー)表である収支差額表と資産の時価評価表(ストック)である期末貸借対照表をモデル計算しています。経済社会活動の結果は、経済活動した期間中の財・サービスの変動量の収支を合計するフロー表と、活動期間の期末時点に、資産/負債・正味資産を評価したストック表で記録することになっています。家計部門である山川家に、ライフ・プラン計画期間において、各年のフロー表とストック表を作成しています。
各年、各月の収入の見通し
現役世代である海原さんと山川家は、各年、各月の収入の見通しが決まっていないとライフ・プラン計画表は作成できません。各年、各月の収入の見通しは、日本経済と世界経済の見通しが必要です。世界経済の見通しは、OECDとIMFの毎年(少なくとも2年先)の予測が発表されます。日本経済の見通しは、内閣府から、1月発表されていますが、単年度であり、長期見通しは、日本において、権威がある見通しの定期的公表はないと思います。
モデル賃金カーブ
ライフ・プラン計画期間において、現役世代の給与見通しをどう計算すればよいのでしょうか。私は、教職員組合に、就職と同時に全員加入で、退職まで、組合員でした。大阪府下大学教職員組合で定期的に、職種別賃金、年齢別賃金、ボーナス、退職金、研究費等組合間でデータが印刷されています。モデル賃金カーブは、推計するのが容易でした。しかし、他の業界と同様に、組合員は、1998年日本金融危機以後、雇用不安、新卒の超氷河期とつづき、全国的に、組合員は減少していきました。私の勤めていた大学もそうでした。教授は、管理職ですが、組合員のままでは、大学行政の管理職にはなりにくい傾向があります。現在でも、他の業界でも、組合員が労務担当管理職になれても、一般管理職はむつかしいのではないでしょうか。
私的には、そういう行政管理職に野心は全くありませんから、学務、教務、研究に集中する一方、地方経済の国際競争力向上、アジアの経済発展に貢献したいと、国内、アジアを視察して、現場で考えていきました。私は、社会主義者ではありませんが、組合員であれば、大学行政の労務情報は、非組合員より、得ることはできますので、満足していました。38年間で、最初は、賃金交渉、教育・研究費でしたが、阪神淡路大震災後、互助会が解散、2000年以降、創立時の教職員が退職するのに伴い、退職金規定の大改正をしました。賃金カーブは、大阪府教職員に準拠していましたが、独自の賃金カーブになりました。その後は、1998年以降の金融危機が終わり、団塊ジュニアの入学増も終わり、日本経済は、本格的な停滞期に沈みました。大学の組合員は減少、賃金は上がりませんでした。
金融危機以前は、組合の団体交渉にも参加したし、そこで、関西の大学教職員のモデル賃金を知ることができました。普通の会社員では、その資料は配布されませんので、自分の会社のモデル賃金は、サイトで、知るしか方法はありません。大阪市では、モデル賃金統計表がありましたが、維新の会が府政、市政を統合する段階で、発行しなくなったようです。もちろん、公務員は、公開されているので、調べることができます。特に、年齢別に、各業界の平均賃金を知ることができれば、ライフ・プラン計画期間の給与所得を推計できます。サイトで、業界の年齢別給与所得は推計があります。関西の大学教職員のモデル賃金等一覧ほど詳細な資料は、公務員資料と同じだと思いますが、他の民間企業の労働組合で、そのような業界モデル賃金資料があります。例えば、産業総合研究所『2024年版モデル賃金実態資料』がありますが、市の図書館には、ありません。類似の『2019年版モデル賃金・年収と昇給・賞与』はありました。
大学と教員組合の毎年の賃金交渉では、大阪府教職員俸給表に準拠していましたが、大学独自の俸給表に移行しました。業界モデル賃金資料は、労働関係の研究所で毎年改定されています。しかし、一般には、手にすることはできません。各種業界の平均モデル賃金資料として、国家公務員俸給表「行政職俸給表(一)」や地方公務員給料表は、サイトで、検索できるので、参考にできます。
モデル賃金曲線で定年までの収入系列を推定する
さて、このようなモデル賃金曲線は、サイトでシミュレーションしています。大学では、学生に、必ず、モデル賃金曲線を説明しました。「波乗り3波乗り」と言って、終身雇用・年功序列職階級制(公務員的ですが)においては、入社10年後、社員一斉、係長波に乗り(1年の評価で、平波の場合もあるそうで)、次は課長波、部長波がモデル賃金曲線にあります。上役が毎年部下を査定し、評価しています。課長波、部長波に乗れるのは、かなり高度な能力がないと乗れないと、説明していました。上昇志向の強い人は、それなりの努力を上役に、付き合いをよくして、アピールするようです。評価が上役全体で決まる客観性がある社風ならば、必要がなく、評価基準を満たすことに専心すべきです。しかし、民間では、情実が効果的かもしれません。
男性社員は、妻を専業主婦で、家族を養えましたが、現在は、係長波は消滅しないにしても、残り2波は、年功序列より、能力主義になっています。夫婦、共稼ぎしないと、家族を養うのは、かなり難しくなります。東京では、3人核家族が多いのも、生活水準を維持しつつ、子を二人以上持つのは、経済的に苦しいのでしょう。地方では、都会生活が身近にありませんので、子供は2人以上、所得水準が東京ほどありませんから、共稼ぎの方が専業より多い傾向があります。地方では、食べる心配のない、両親が近くにいて、子供を世話してもらえる、暮らしやすい平和な環境があれば、子を二人以上持つ若年家庭が多い。少子高齢化がすすみ、人口流出している、過疎化町村では、所得を田舎暮らしを維持する所得が稼げなくなっているのです。
業界および業界内でも、モデル賃金曲線は格差があります。モデル賃金曲線が会社から開示されれば、在職者は退職までの予想所得の参考になります。一般の業界に就職して、組合員用のモデル賃金曲線は、会社側から、提示されることは、まずないでしょう。かつての日本では、終身雇用・年功序列職階級制のもとでは、年齢で、給与が上昇するので、モデル賃金曲線は、次年度の上昇率をみれば、知る必要もなかったかもしれません。
終身雇用・年功序列職階級制から、能力主義へ移行
日本経済は、人口減少が始まっていますので、労働力不足になる一方、日本経済は、第3次産業が主要産業となり、中小零細企業が多数を占める労働集約的産業です。男女賃金格差が是正されないため、低賃金の女性労働が必要とされる産業でもあります。第3次産業は、製造業と違って、寡占的ではないので、いわゆる大企業の賃金水準は支払えません。したがって、男性の給与水準は、35歳以上では、昇給が頭打ちになる傾向があります。女性は、男女格差があり、大卒女子は、35歳になると、平均賃金が大卒初任給に戻る傾向があります。
日本の大都市の第3次産業が進行し、労働の内容が、知的労働生産をともなわない事務職は、生産性に見合う賃金を測定できないので、2000年の金融業界から製造業を中心とした業界再編で、終身雇用・年功序列職階級制で、賃金は支払えず、能力主義に移行したといわれますが、第3次産業のサービス業では、元来、能力の評価は、上司の主観、人的関係に依存しやすい。上司の能力を越えれば、上司のいじめ、降格、転勤、転籍もあります。直属の上司に、「上役になりたい。」と飲み会で口を滑らした人が、上司にウザイと見られたのか、子会社に飛ばされたと、話してくれました。私は、「そういうことを口に出すのは、危ない。」と余計なお世話をその人に言っていましたが。
神戸大学大学院時代、アメリカに研究にいかれた後尾哲夫先生と雑談で、「アメリカで、研究するのと、日本とどう違いうのですか。」とたずねると、「アメリカでは、なんでも、日本より大きく育つ。日本では、研究資金がなく、鉛筆と紙でしか研究できないから、研究成果は小さい。」私が買ったのは、関数電卓「CASIOfx-115」で、まだ、働いております。アメリカは、能力主義の殿堂だが、日本の大都市で、日本流能力主義になると、能力評価が恣意的になり、伸びるものは引きずり落とす、日本古来の「出る杭は叩かれる。」になりがちです。20年間、東京の大卒賃金は、実質賃金は上昇しない。日本流能力主義賃金の公正価値は測れない。
今週(2025年4月28日~5月2日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、21日から26日まで、ワシントンでIMF・世界銀行周期総会が開かれました。IMFは22日、2025年世界成長率見通しを1月の3.3%から、2.8%に引き下げました。引き下げの原因は、トランプ関税の賦課です。23日20ヵ国財務相・中央銀行総裁会議が24日まで、ワシントンでありました。21日フランシスコローマ教皇が死去され、26日160か国以上から首脳、閣僚、宗教関係者の参列があり、葬儀が行われました。
今週のイベントは、27日石破首相がベトナム・フィリッピンに30日まで訪問します。30日日銀政策委員会・金融政策決定会合が5月1日まであります。
先週の統計は、次の発表がありました。
予測値 実績値
21日 米3月景気先行指数 -0.5 -0.7%
中4月最優遇貸出金利(LPR) 3.1% 3.1%
24日 米3月耐久財受注 1.4% 9.2%
日4月東京都区部CPI 3.2% 3.4%
3月スーパー売上高 1兆899億5480万円
今週の統計は、次の発表があります。
予測値
29日 米4月消費者信頼感指数
30日 日政策金利 0.5%
3月鉱工業生産指数 1.2
米1~3月期GDP 0.4%
3月個人消費支出 0.4%
個人所得 0.4%
3月PCEコアデフレータ 2.6%
1日 日4月消費動向調査
2月 日3月有効求人倍率 1.25
3月完全失業率 2.4%
米4月完全失業率 4.2%
第5回目 2025年5月5日
要点・3. 金融商品と金融市場の分類と特徴
・3.1 金融商品の特徴、金融市場の特徴と分類
・3.2 日本の(1)預金、(4)債券、(5)株式の取引と現状
3.金融商品と金融市場の分類と特徴
第3章では、はじめに、金融商品の定義と特徴を述べ、それらを取り扱う金融市場を、銀行の間接金融市場と、金融機関および取引所の直接金融市場に分類します。個人投資家が選択できる商品とアクセスできる市場を中心に、紹介しています。
次に、個別に特徴のある商品を詳しく説明しています。最後に、金融商品の貨幣価値、すなわち、商品価格表示の表し方を示しています。金融市場において、商品1単位が、貨幣価格でいくらするかが、取引者間で決定できるとき、取引が成立します。
金融商品の評価は、数列、級数の知識があれば、容易に理解できます。各金融商品は、満期期間があり、その間の価格変動は、平均(期待)収益率および標準偏差で測ります。そのため、確率と統計の知識が必要です。第4章で、満期期間とリスクが異なる商品を購入する理論を学ぶので、そのとき、高校数学程度の初歩的な確率と統計の知識を示しています。数学ができなくとも、2期間か、3期間、価格が上がるか下がるか、変化を追うことができれば、経済学・経営学では問題ありません。
3.1 金融商品の定義および金融市場の分類と特徴
金融商品の定義と特徴
日本国内で取引できる金融商品は、それらの商品の金融市場で取引されます。小口投資家が取引できる金融商品を主に取り上げます。金融商品の特徴は、満期期間、最終利回り、制限条件、取引単位(1口)および発行の方法で分けられます。
預貯金
消費者ローンクレジットカード住宅ローン
債券
株式
投資信託ETF (上場投資信託)
Jリート[日本版不動産投資信託]
外貨 外貨預金 外国債券 外国株式 外国投資信託
国内金融市場における金融派生商品は、次のようなものがあります。外国と比較すると、機関投資家が取り扱う商品です。個別株式オプションはないので、個別株式にオプションをかけることは、日本ではできません。株式指数を保有、あるいは購入予定がある場合、日経平均株価、TOPIX等に、オプション取引をすることができます。投資信託商品は、リスクヘッジを金融派生商品で掛けている場合があります。仕組みを理解するのも、むつかしいですが、個人投資家が利用することも、使い勝手が悪い商品です。
金融商品 限月 権利行使価格(刻み) 取引単位(1口) 証拠金
債券先物 2限月 1円 額面1億円 あり
債券オプション 最長1年 任意 任意(額面1億円以上) なし
金利先物 3限月 0.25ポイント 元本1億円 なし
株式指数オプション 直近連続4カ月 500円(日経) 原資産の1,000倍 あり
Jリート先物
金融市場の特徴
相対(あいたい)取引は、顧客と金融仲介者が1対1で金融仲介者の窓口において金融商品を取引することをいいます。店頭取引ともいいます。取引所は、顧客が金融仲介者を通して金融商品を取引し、金融仲介者自身が自己資金で取引します。金融市場の内、預貯金、外貨預金、貸付金市場は、金融仲介者が銀行であり、銀行だけが預貯金を取り扱えます。銀行は、預金を貸付、預金金利と貸付金利との利ザヤを収益とします。
銀行が預金者と借入者とを資金で仲介することを間接金融といいます。債券および株式は、資金供給者と資金需要者が、直接、資金と金融請求権(債券および株式)を取引することを直接金融といいます。
デリバティブ商品の内、先物、先渡し商品は、投資家の予想を反映して、契約価格が決まります。オプションは、オプション価格が確率過程から導かれるため、同じ満期期間であっても、先物、先渡しとは、違う値動きをします。オプションは、顧客が取引所の設定するオプション価格帯から選択し、原資産の損失を前払いで確定できる、保険的商品です。投機的に、利用することもできますが、オプション商品は、業界では、保険的認識で運用しているようです。日本では、原資産が指数である金融商品に対して、証券取引所で取引できます。個別商品のオプションは、相対取引になります。
本教室対象の個人投資家は、保有する原資産額が小さく、それに対してリスク・ヘッジするほどでもありませんが、海外を投資対象にしている投資信託の中には、為替変動のリスクをデリバティブ商品で、価値の下落に対して、保険をかけている商品がありますから、その方法を理解する必要があります。
第4章では、コール・オプションをとりあげて、先物市場とオプション価格付けの違いを考えました。オプション価格付けでは、投資家が、取引所が指定する満期時点の権利行使価格を選びます。満期時点の商品価格は不確実性下にあり、取引所では正規分布を指定します。株式1単位の購入とそのコールδ単位の売りというポートフォリオを考え、満期時で、いかなる価格が実現しても、損益が変わらないδを決めます。現時点のポートフォリオの価値を確定利子率で運用した収益は、満期時の収益と一致するように、裁定取引が働きます。その方程式が解ければ、オプション価格付けが決まります。このようなヘッジを前提とした計算過程をみると、オプション価格付けは、取引所で決められます。投資家は、たとえば、ある株式をx単位保有していれば、コールxδ単位売りで、現行利子率で代金を運用しておけば、損失を少なくすることができます。
現在の金融市場とその先物市場との関係は、経済学で、価格が決まると考えられます。しかし、経済学では、株式市場の価格理論およびその先物市場の価格理論も、周知の理論があるわけではありません。したがって、経済学の価格理論とデリバティブ商品理論との関係は、価格理論によって決定される先決変数(現行株価、その価格分布、株価の時間的推移を表す確率過程)を所与として、取引所が提示する権利行使価格(経済学では満期時先物価格)の幅で、ヘッジ目的にしばられて、コール価格付けが提示され、コールの売買で、現金が受け渡しされます。経済学の先物市場では、先物契約で、証拠金の差出はあっても、現時点での現金の授受はありません。経済学へのデリバティブ商品理論の影響は、現先資産市場の価格決定と、資産予想価格分布および資産価格確率過程を研究する接近法として、役立っていると思います。
金融市場の特徴
金融市場 取引方法 取引期間 金融仲介者
間接金融市場
預貯金 相対(あいたい) 1日~10年 銀行
外貨預金 相対 1日~3年 銀行
貸付金 相対
1日~35年 銀行
直接金融市場
債券 相対・取引所 3ヵ月~30年 銀行・証券会社
株式 相対・取引所 無期限 証券会社
投資信託 証券会社 ~無期限 銀行・証券会社
Jリート 取引所 ~無期限 銀行・証券会社
金融派生市場
先物 取引所 ~1年
取引所・証券会社
先渡 相対 ~1年 証券会社
オプション 取引所 直近連続4ヵ月 取引所
スワップ 相対 ~1年 銀行
3.2 日本の(1)預金、(2)債券、(3)株式の取引と現状
個別金融商品の内、関接金融市場では、(1)預金、(2)外貨、外貨預金、(3)住宅ローン、直接金融市場では、(4)債券、(5)株式、(6)投資信託、(7)ETF、(8)Jリートを取り上げている。取引の方法と、市場の現状について、(1)預金、(4)債券、(5)株式を取り上げて、説明する。
(1)預金:預金取扱金融機関において、本人名義で1円から入金すると、預金口座を開設できる。普通預金は、公共料金等の自動振り込み、消費者ローンおよび住宅ローンの返済資金決済に利用される。貯蓄手段としては、原則満期期間2年まで、3年以上は自動更新の定期預金口座があり、普通預金から、定期的に積み立てることができる。本人が死亡するまで、預金口座は存続するが、10年以上使用しなければ、休眠口座となり、その預金は公益事業に活用され、ふたたび、使用すれば、利用できる。預金が没収されるのでは、ない。
預金口座は、本人名義の金融請求権であり、本人の委託なしに、口座を利用できない。10万円以上の振り込みには、本人確認書類を要求され、その手続きが不便である。インターネット銀行や流通業者の銀行が設立され、銀行の窓口に行かないで、決済ができる。
仮想通貨が流行しだし、取引所も増えた。通貨というが、本来の通貨との交換レートが変動する。中央銀行が発行している通貨ではないから、交換レートが仮想通貨取引所で毎日成立する。仮想通貨は、銀行で金預金、外貨預金と同様、仮想通貨預金できるようになるのか、模索が続くだろう。
ポイントが流通業者間で共通化されて、物品、サービスと交換できるようになっている。共通ポイントの場合、物品、サービスの購入の都度、例えば200円につき1ポイントを店側のメモリーに付与してくれる。1ポイントは1円に交換して、物品の購入に使える。これも電子マネーのようで、決済手段に使われるので、業者間では共通通貨である。ポイントを貯める人も多いが、失効期日があり、貯めても、利息は付かない。小銭のおつり分にポイントを使用するのではないかと思う。
(4)債券:満期期日に元本を返済する割引債と満期期間に半年か1年ごとに利息(確定利息)を支払う利息付債がある。割引債は、かつて、長期信用銀行および東京銀行において、国内に支店網が少ないため、資金調達のために、割引債を発行し、郵便局から購入できた。普通銀行は、地域に支店網が多く、預金によって、資金調達可能であったため、発行は認められなかった。しかし、1998年のバブル破たん処理が本格化して、預金金融機関の再編が起こり、長期信用銀行および東京銀行は、普通銀行となった。リーマン・ショックまで、割引債は存続したが、ゼロ金利時代となり、割引債は発行されない。
利息付債は、国債を中心として、発行額は増大している。かつては、インフラ・ストラクチャー計画のため、建設国債が発行され、「失われた時代」は、税収減から、赤字国債が発行され、雪だるま式に増大した。リーマン・ショック以降は、社会保障予算が増大して、今後、高齢者医療費が増大する時代が30年間つづくだろう。
封建時代であれば、藩の人口減少は、領民の逃亡であり、すなわち、領主の統治能力の欠如であり、幕府により領地お取り上げとなり、近隣の藩に統合されるのは当然であった。さしずめ、市であれば、3万人未満になれば、原則的に市政返上となる。地方交付税は、かなりの部分は人口割であるから、人口が減少すれば、地方交付税が減少し、市は近隣の市に合併され、国の財政健全化に寄与するし、地方債の発行は、国より健全財政均衡が求められているので、今後は、減少するだろう。
全国的に、地方自治体の平成大合併時代があったが、近畿では、大阪府が不作為であった。維新の会ができて、大阪市を再編しようとか、府と市の行政機関が同じような業務をしているということで、統合が実現した行政事業もある。また、道州制などの議論があり、「地方自治体消滅」の研究が発表されたこともある。しかし、維新の会では、大阪都は実現できなかった。大阪市、堺市は、今もって、行政区域は変更なしである。
日本では、社債は、1970年の資本の自由化、1974年以降の変動相場制により、大企業は、銀行による借入金より、外債発行による、国内金利より低い利息で資金調達をし、海外進出を図った。海外投資家は、変動相場制により、360円から200円台と、ドル安を見込んでいるから、為替差益がほぼ確実に期待できた。つまり、1億円、1%で5年債を発行すると毎年、100万円利息が払われるが、発行時、1ドル280円、次の年260円に円高になると100万円はドル換算すると、3,571ドルが3,846ドルであるから、差益は7.7%になる。これが、日本の銀行システムが縮小する原因であり、日本銀行の金融政策が効きにくくなる原因でもあった。
また、企業の投資案件は、企業成長に欠かせないが、資金調達の段階で、銀行の借入金より、社債発行の方が、資本調達コストは低い。しかし、戦後の産業成長期に、社債市場は育成されず、社債発行費用が高かった。1970年代、変動為替制に移行し、大企業は、海外市場で資金調達に出る。日本独特のメインバンク制(銀行が大株主の地位をもちい、財務取締役に銀行員を派遣し、財務管理をする。)による、銀行の直接財務管理がきらわれ、企業独自の財務管理へ移行する。海外市場をもたない中小企業では、社債を発行しても、買い手が限られる。株式の増資となるとさらに引き受けてはいないから、依然、間接金融優位であり、メインバンク制は残っている。
日本では、債券は、国債と地方債が大半であり、地方債は、人口減少のため、発行が減少する。社債は、海外市場消化を想定した伝統を引き継ぐだろう。
(5)株式:新古典派経済学やケインズ経済学では、株式市場の典型的なモデルはほとんど開発されていない。債券市場は、新古典派経済学では「投資・貯蓄説」がある。ケインズ経済学では、貨幣市場という現実にはない市場で、「流動性選好説」があり、債券市場は、流動性選好説で決まる利回りが債券市場の利回りである。貨幣市場の均衡で、債券市場の利回りが決まることになっている。ケインズ経済学はマクロ経済学であり、新古典派経済学はミクロ経済学もマクロ経済学もある。しかし、両学派のモデルには、株式市場の株価はどう決まるのかは、はっきりしない。株式市場は、資本主義経済の中核の市場なのだが、株式市場の典型的理論モデルはない。
本資産形成論では、4章において、株式市場は、交換経済市場であり、不確実性下のミクロ経済学によって、株式価格の市場均衡価格が決まることを論じる。
今週(2025年5月5日~5月9日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、27日石破首相がベトナム・フィリッピンに30日まで訪問しました。30日日銀政策委員会・金融政策決定会合が5月1日までありました。日本銀行は、政策金利を0.5%に据え置きました。
今週のイベントは、4日アジア開発銀行年次総会がミラノにおいて、7日まであります。6日米連邦公開市場委員会が7日まで開かれます。
先週の統計は、次の発表がありました。
予測値 実績値
29日 米4月消費者信頼感指数 86.0
30日 日3月鉱工業生産指数 0.8 % -0.3%
中4月製造業PMI 49.8 49
4月財新製造業PMI 49.7 50.4
米1~3月期GDP -0.2% -0.3%
GDPデフレータ 3% 3.7%
3月個人消費支出 0.4% 0.7%
個人所得 0.4% 0.5%
3月PCEコアデフレータ 2.6% 2.6%
1日 日銀政策金利 0.5% 0.5%
4月消費動向調査 31.2
2日 日3月有効求人倍率
1.25倍 1.26倍
3月完全失業率
2.4% 2.5%
米4月完全失業率
4.2% 4.2%
4月耐久財受注 9.2% 9.2%
今週の統計は、次の発表があります。
予測値
5日 米4月ISM非製造業景気指数 50.2
6日 米3月貿易収支 -1220億ドル
8日 米FRB政策金利 4.5%
9日 中4月貿易統計
第6回目 2024年5月12日
要点・3. 3 債券先物と債券オプション
3. 4 金融資産・負債の評価
3. 3 債券先物と債券オプション
債券先物と債券オプションの取引の仕組みと取引例を、旧東京証券取引所のHPより引用した。現在は、金融先物・オプション取引は、大阪取引所に移管されている。
債券先物取引は、架空の国債である標準物を、額面1億円で、満期月(3, 6, 9, 12月)に予想される、額面100円当たりの市場価格で売買する。
債券オプションは、原資産を、額面1億円で、満期月(3, 6, 9, 12月)に予想される、額面100円当たりの権利行使価格が、中心価格と上下2本、取引所の計算に従い、提示され、投資家は、売買して、コール・オプションの買いでは、プレミアムを前払いする。ヨーロピアンでは、満期日に、権利行使すれば、契約価格で原資産を買える。
3. 4 金融資産・負債の評価
金融商品の貨幣価値、すなわち、金融商品1単位が、貨幣でいくらするのかという評価方法が、金融商品で違いがある。
・預金の現在価値と将来価値、最終利回りと市場価格との関係
・外貨・外貨預金の評価
・住宅ローンの元利均等払いと元金均等払い
・帰属家賃の計算と賃貸か持家か
・債券の評価
・株式の評価
・投資信託の評価
・貴金属投資の取引価格
預金、債券は、利息の支払いと元本の償還がある金融商品である。ともに、満期までに、利払いがあり、利息と元本を足した額を元利合計という。預金は、1口1億円の譲渡性預金以外は、預金の名義人以外に、途中、譲渡できない。
預金の価値
現在0、将来1、2で表す.現在、銀行に年利子率iでA0円預金する。1年後の元金A0円と利息i×A0円を合わせた額A1=A0+i×A0=(1+i) A0円を元利合計という。
2年定期預金の元利合計A2 は、元金 A0 、利子率iと表すと単利と複利の2種類がある。
単利 A2 =i×A0 +(1+i) A0 =(1+2i) A0
1年目の利息 + 2年目の利息+元本
複利 A2 =(1+i) ×i×A0
+(1+i) A0 =(1+i) 2A0
1年目利息iA0の+ 2年目の利息+元本
再投資
元金A0を現在価値、1年満期の預金の元利合計を将来価値A1とよぶ。
金融商品の市場価値を現時点で評価する方法は、割引現在価値がある。預金の場合、
現在価値A0の将来価値A1 (1年満期の預金の元利合計) A1 =(1+i) A0
将来価値A1の割引現在価値A0 A0 = A1/(1+i)
ということにする。割引現在価値A0は、預金A1という元利合計の金融商品の現在市場価格を表す。A0 = A1/(1+i)から、分かるように、利子率iと市場価格A0は反比例の関係がある。
さらに、従来、利子率は確定利息であるが、期間平均利子率の変動金利もある。預金は相対取引であるが、預金金利は自由化されていて、各銀行で、顧客との関係で、預金利子率は違う。現在、日本銀行のマイナス金利政策で、金利差がほとんど目立たない。
外貨の価値
外貨交換所で、1万円でドルを購入する場合、為替レートは、午前11時過ぎに、当日の銀区間為替レートが決まり、そのレートに、手数料が追加された為替レートで、購入できる。
2021年5月14日中心相場は、109.6円/ドルであった。対顧客電信売相場は、110.63円/ドルであった。1万円で、90.39ドルと交換される。例えば、9月に、ロサンジェルスに旅行する予定であれば、税関申請が不要な外貨持ち出し上限は100万円であり、旅行期間中のホテル・クーポン以外の現金保有ドルを20万円とし、現在、対顧客電信売相場が円高で、108円/ドルになったとき、外国為替取扱銀行で1851.85ドル購入する。帰国後、300ドル使い残した場合、次回両行まで、そのままか、円安になれば、買い相場110円/ドルでなったとき、33,000円に交換する。
外貨預金の価値
外貨の現金保有は、利子がつかないが、外貨預金は利子がつく。現在、米国は、金融緩和中で、定期預金利子率は、年0.01%、日本の銀行で、スーパー定期(300万未満)年0.002%である。現在、世界の先進国の利子率は年0.01%である。世界は、金融緩和時代でも、日銀の政策金利は、飛びぬけて、低金利である。
外貨預金は、現金保有より、利子がつく。方法は、銀行で外貨預金口座を開き、現金か、円預金から振り返れば、定期預金となり、自動更新できる。引出は、外貨ではできない。海外旅行中、外貨で引き出しできる場合もある。
1ヵ月定期に、200万円を1年定期預金すると、110.63円/ドルで、18,078.27ドル預金する。1か月後、買相場112円/ドルで、18,078.27ドルを引き出すと、2,024,766.24×(1+0.0001)=2,024,968円である。為替差益と利息が稼げる。収益の主な成分は、為替差益であり、売りtimingが悪ければ、1ヵ月定期を自動更新すると、複利が効き、売りtiming好時に、満期解約損を少なくし、差益を機動的に稼げることが分かる。ただし、国内で外貨預金をした場合、利息は20%、課税され、満期・解約時に発生する為替差損益は、雑所得として、分離課税ではなく、総合課税される。
外貨建MMF(Money Manegement Fund)投資信託
証券会社は、預金取扱機関ではない。その代わりに、外国短期証券又は国債の投資信託があり、外貨建ての他の金融資産を売買するとき、外貨建MMFを使って、1ドル単位で決済が可能である。外貨預金は、為替差益等は総合課税になるが、外貨建MMFは外貨建て短期投資信託のため、売却した場合、分離課税になる。外貨建て投資信託である外貨建MMFは、短期証券の価格動向で、毎月分配型利回りが計算され、外貨預金の確定利子と比較すると価格安定性はない。外貨建MMFを売却すれば、為替手数料を支払い、ドルを円に交換できる。
2024年5月13日、野村證券ドル建てMMF利回りは、4.768%、為替手数料50銭(5月8日)、三菱UFJ銀行ドル預金は、5月10日普通預金1%(年率)、1ヵ月外貨定期預金インターネット優遇金利10%為替手数料0円である。
住宅ローンの元利均等払いと元金均等払い
家計が住宅を取得するために、住宅金融支援機構や銀行から融資を受ける書類審査の要件を満たせば、融資の手続きに入る。そのとき、返済方法は、元利均等払いと元金均等払いがある。
元利均等払い(固定返済型)年固定返済額FR、満期期間 n年、利子率 iとする。借入金 L0は、銀行側は元利合計L0×(1+i)n+1円を返済してもらい、借入者は毎年FR円を返済する。FR円を利子率iでつみたて運用すれば、
元利合計はFR{(1+i)n+ … +(1+i)2+(1+i)}となる。
L0×(1+i)n+1=FR{(1+i)n+ … +(1+i)2+1+i}
と表せる。両辺を(1+i)n+1で割れば、借入金と固定返済額の現在価値とが等しくなることを意味する。
L0= FR +FR + … + FR
1+i (1+i)2 (1+i)n
固定返済額 FRは,公式1(金融数学1)を使って
FR = L0÷{ 1 + 1 + …
+ 1 }
1+i (1+i)2 (1+i)n
= L0×i(1+i)n / {(1+i)n -1}
元金均等払い
元金均等払いは、毎回の元金返済を均等にする返済方式である。t回目の返済額をRtとする。毎回元金均等分L0/nを残存年数間、単利で運用する。
Rt= L0×{1+(n-t+1)×i}
n
総返済額は、R=Σt=1n L0×{1+(n-t+1)×i}=L0+L0×i×n(n+1)
n n 2
このように、元金均等払いは、元金と利払いが分離する。
元利均等払いと元金均等払いの違い
元利均等払いは、利払い額が先行し、元本返済が後半に多くなる。銀行では、元利均等払いの方が、複利計算により、返済利息にも利息がとられるので利息収入が多い。また、たとえば、貸付初期5年で借入者が返済不能になっても、借入者には元本分がほとんどないので、住宅債権は銀行側に落ちる。銀行側優位の返済方法である。
元金均等払いは、最初からL0/n円、元本返済が進むので、住宅債権は、最初から借入者に移っていく。しかも、利息は単利計算なので、元利均等払いと比較しても、支払利息は少ない。しかし、最初から、L0/n円という返済額は、負担が大きい。住宅ローンは、借入者の方が、銀行より債務者として、立場が弱いので、銀行の言いなりで、元利均等払いの返済契約が多いはずである。子供の教育イベントが済めば、退職まで早めに、繰り上げ返済することが望ましい。
賃貸住宅の帰属家賃の計算方法
山川家は、4人家族なので、山川氏が定年退職60歳まで、2階建て賃貸4LDKに住み、61歳から、平屋3DKに移る。退職後は、2階は、高齢化で、ほとんど使用しないため、平屋の方が、高齢者の階段転落事故がなく、介護等にも動線がフラットで安全である。前者が月8万円、共益費5千円、後者が月6万円、共益費5千円とする。家賃・共益費が一定であると、帰属家賃の総額は、
4LDK[(家賃+共益費)×12か月×25年+更新料×13回]+3DK [同計算]
85000×12×25+80000×13+65000×12×25+60000×13=25500000+1040000+19500000+780000=46820000
である。
例として、(2022年賃貸住宅HPから、物件を選択した。)山川氏は、東京都あきる野市で、新築戸建て、土地120㎡(37坪)、4LDK95㎡、3000万円が気に入り、自己資金500万円、借入金2500万円で、購入することにした。建築費は、住宅展示場で、好みの住宅を選び、建築費を参考にする。建築費は、3000万円のうち60%、1800万円であり、残り1200万円が土地代になる。ローン返済後、土地1200万円が資産として残る。25年間のローン支払総額は、143万6千円×12=3590万円である。
中古住宅は、団塊の世代のラストが75歳になるので、その住宅も含め、中古住宅・空き家は、全国的に増加する。中古住宅をローンで購入することができるが、土地の評価と家屋の残存価値で、評価される。土地流通評価額+補強・増改築工事費(更地費用300万円<工事費<新築費)+仲介手数料で中古住宅の取引価格が決まる。ただし、各都道府県不動産住宅市場で、仲介業者による新・中古住宅市場価格はなく、店頭取引である。
注意 以上の計算は、インフレ期、家賃もインフレに追随することが考慮されていない。金融資産の株式と同じく、インフレ期には、株式価値もインフレになり株価が上昇する危惧があるのは、企業が土地建物・機械の実物資産の評価が上がるからである。米国では、インフレ期にあり、賃貸住宅が10%上昇、家賃払えなく人々がすでに出ている。年金高齢者で、フロリダに成功者が集まるのは、暖房費が要らず、年金と資産で、快適な老後を過ごせる人々だけである。
(1)賃貸か新築かの判定条件
帰属家賃の総額4682万円(住設・固定費込み)>ローン支払総額3590万円
戸建の固定資産税および建物の修繕費は含まれていない。都市計画法にもとづく用途別で、土地価格が異なり、住宅専用地域から、用途指定が雑多な用途になるにつれて、建蔽率および容積率が,緩和され、その分、日当たりが減少する。あきる野市で、37坪では、地価の上昇は、期待できない。120㎡程度の小規模宅地では、売却して、投資額を回収できるほどの資産価値は期待できない。
(2)ローン返済能力条件
年間所得の27%がローン返済であるから、消費生活の健全性をクリアしている。したがって、住宅金融支援機構の審査を合格し、取次の銀行の審査にも合格する。
債券の評価
債券は、譲渡可能であるから、証券会社で売却可能である。途中で、売却することは証券会社では勧めていない。その売却価格が、そのときの市場利子率で評価される。満期期間、最終利回りの計算法、発行の方法、1口の金額、取引単位で分けられる。
債券を特徴付ける項目は次の通りである。
満期利回り Rn
債券市場価格 P
1期間当りのクーポン C
償還価値 F
残存期間 n
1) 単利の最終利回りをRnとする。各期間のクーポンはその債券に再投資されない。
Rn = C+(F-P)/n
P
2) 複利の最終利回りをRnとする。クーポンCは再投資される。ただし,日本では発行されることは少ない。
P(1+Rn)n=C(1+Rn)n-1+C(1+Rn)n-2 +…+C(1+Rn)+C+F
これをRnについて解く。
割引債の評価 額面 F、利子率i、満期期間 1年とし、市場価格は現在価値Pであり、満期時に額面 Fが償還される。
P= A1 / (1+i )
額面 F、利子率i、残存期間 n年とし、市場価格Pである割引債は
P=F/ (1+i )n
国債の評価 額面 F、クーポン C、満期期間 n年、市場利子率iとし、発行時の市場価格P は、
P = C + C + … + C+F
1+i (1+i)2 (1+i)n
債券の最終利回りと市場価格との関係は、割引債、国債ともに反比例である。
証券取引所では、10年国債の場合、額面100円、クーポン6円、満期期間10年で標準化される。
実際に発行されている国債は、クーポンは、市場利子率の実勢に応じて、発行されるから、10年国債は存在しない。現物を購入したい顧客は、10年国債を基準に、クーポン、残存期間に応じて、交換比率(conversion factor)が計算される。
株式の評価
1株あたり年配当Dを将来無限に受け取ることができるとする。配当割引モデルにおいて、株式収益率(安全資産利子率+危険負担率)をρとし、市場株式価格をPとすると
P= D + D + D + … = D
1+ρ (1+ρ)2 (1+ρ)3 ρ
1期間だけで、現在価格P、株式収益率s、1株当たりの今期配当Dと株式の期末予想株式価値Peとすれば、
s= D +(Pe -P)
P
と定義する。変形すると、
P= D +Pe
1+s
と表される。このとき、Peは、清算価値にあたる。
投資信託の評価
投資信託受益証券は、投資信託会社が、投資方針で、投資家から資金を募集し、資産を購入、当初10,000口、10,000円を当初の基準価格とする。総資産の各時点での評価額を投資口数で割って、時価の基準価格が新聞に公表される。
口数の計算法(10,000円で、ある投資信託を購入する場合)次の比例式から
10,000(円)投資額 対 基準価格(円)=x(口数) 対 10,000(口数)
x(口数)={10,000(円)投資額÷基準価格}×10,000(口数)
償還期間は無期限から、1年未満まである。購入時に買付手数料がかかり、商品保管のための信託報酬料がかかる。投資信託は、利息や配当が定期的に確定するが、それらは、口数に応じて分配され、追加投資されるか、または、税引き後、払い出される。
例 本教室で扱う、日興DCインデックスバランス(株式20)の場合、基準価格(2022年5月13日)16,663円、純資産9,561百万円、信託報酬0.1450%、設定日2002年12月10日、組入れ比率(株式20.2%、債券74.6%、その他、5.2%)、無期限である。基準価格10,000円より低い、投資投信は、運用成績が設定よりは低い。
投資方針は、株式、債券、REIT、バランス等がある。それぞれ、国内資産と国際資産がある。国際地域別がある。商品は、目論見書の閲覧確認が義務化されているので、必ず、投資方針の確認はしなければならない。
格付け(レーティング) 各商品は、モーニングスター社等の格付け会社によって、格付け(レーティング)してある。
買付手数料がかかるが、手数料0円もある。
信託報酬料は、商品ごとで、違いがある。
貴金属投資の取引価格
貴金属で、金は、国際通貨の地位を金本位制下では、長らく、保ってきた。現在は、世界の中央銀行は、その名残で、金保有を紙幣発行の担保として保有している。日本銀行は、戦後、国際的担保として金保有する規定はない。新日本銀行法でもない。国際通貨価値の番人である財務省にも、円の国際価値の担保として、国庫に金保有が省令で定められていない。権威国化したロシア連邦、中国は、金保有している。伝統的に、インドは、民需もあり、金保有している。金保有が乏しい国の通貨は、国内インフレの変動も大きい。
そのような国際価値を持つ金は、商品取引されるが、現物と先物がある。日本では、(東京、大口需要家渡し、持ち込み、現金、円)で、2024年5月9日午後4時現在)金(99.99%以上、1g)11,576円である。昨今、円安と世界インフレーションの影響があり、2021年5月7日では、6,375円だった。為替レートは、109.13円であった。
金融論研究者は、金本位制の歴史が、1971年ドル金本位制が崩壊、変動相場制に移行した時代から、50数年であるので、金融論の考慮外に置くわけにはいかない。研究者、関係者は、多少とも金を保有し、その魔力が国際金融の世界では、衰えていないことを思い知る昨今である。金は、日本では、3年間で、1.8倍は、驚異の大化け商品となっている。日銀・財務省が、大胆かつ果敢に、世界の金融潮流を乗りこなす技量・政策遂行能力に欠けていた、大蔵省出身黒田前総裁と財務省のタッグチームは、世界リーグ4位に転落、世界経済競争では惨敗している。
日本に、大谷選手はいないのか、岸田氏は増税眼鏡をかけた貧乏神と就任当時から、陰口をたたかれていたが、この世界リーグ成績では、国際的に評価を落としているから、本人は、気づかないだろうが、岸田政策は成功しなかった。2024年10月首相に選出された石破首相は、無謀にも、すぐさま、衆議院解散、総選挙を実施、自公は、歴史的敗北で、過半数割れした。再び、衆議院で、首相に選出されたが、政府予算案に自公独自政策はかすみ、1月の通常国会で、野党案を取り入れた政府予算案を3月末、衆議院で議決した。その間、岸田政権のインフレ対策であったガソリン補助金を廃止、賃上げを企業に要請し、特に、2024年令和米騒動8月引継ぎ、米価が諸物価より、倍増となり、4月から、CPIはインフレになっている。石破政権は、政府統制色が強い米価すら、備蓄米で引き下げることはできなかった。コメは、5月端境期に入り、8月まで、令和米騒動2期目を迎える、無策ぶりである。
日本経済は、世界インフレーションのストロー効果で、30年間デフレ基調からインフレ基調に転換している。資産選択の商品取引の内、個人投資家が小口から取引できる現物商品もあり、投資信託もある。筆者は、長期投資として、現物金小口つみたて商品をドルコスト平均法で購入し、10年過ぎて、売却し、車の購入費、家族の海外旅行に使った。3年間で、これほど大化けになると、資産選択の多様化の一つとして、国際金融取引にも影響する。東京、大口需要家渡し2024年5月9日11,581円/g、NY金先物5月限月2,340.3ドル/トロイオンスであったが、2025年5月8日15,587円/g、3,296.6ドル/トロイオンスである。
米国は、トランプ関税政策で、米国の国内インフレ期待が上昇、さらに、ドルの国際信認に、減価予想があり、NY金価格が上昇している。金は、金本位制という国際通貨の歴史があり、各国が発行する紙幣より、国際評価基準として、価値が安定している。
金をドルコスト平均法で購入することを付け加える。プラチナ、銀には、金の国際的価値標準の機能はなく、プラチナは自動車の排ガス触媒、銀は工業材料で使用され、2024年金価格の暴騰のような変化はない。2024年5月8日のプラチナ価格は4927円、2025年5月8日4606円であった。
日本では、古来、コメが年貢として、領主に取り立てられ、金銀の金属通貨と同様な価値があり、江戸時代のコメ相場で、GNPを推計するほどである。2000年から実質賃金は変化せず、コメ価格も変化しなかった。しかし、24年の春闘で名目賃金が久しぶりに上昇すると、コメ価格は連動し、昭和、平成、令和を通じて、驚異の2倍以上の急上昇になった。日本史的、国際的にも、珍現象のインフレーションだった。歴史的に、江戸時代から、大阪のコメ取引所では、コメ先物が取引されていたが、このほど、復活し、コメ先物が2024年8月開設された。ご祝儀相場でもあるまいし、コメの相場は、金価格の暴騰をこえる世界一の暴騰であった。
今週(2025年5月12日~5月16日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、4日アジア開発銀行年次総会がミラノにおいて、7日までありました。6日米連邦公開市場委員会が7日まで開かれました。
今週のイベントは、3月期決算発表があります。
経済統計は、次の発表がありました。
予測値 実現値
5日 米4月ISM非製造業景気指数 50.2 51.6
6日 米3月貿易収支 -1,320億ドル -1,405億ドル
8日 米FRB政策金利 4.5% 4.5%
9日 中4月貿易統計 -7,000億元
日3月景気一致指数 115.7 116
先行指数 107.6 107.7
経済統計は、次の発表があります。
予測値
5月12日 日4月景気ウオッチャー調査 44.7
日3月国際収支 5500億円
13日 米4月CPI 2.4%
15日 日4月工作機械受注額
米4月小売売上高 0.0%
4月鉱工業生産指数 0.1%
16日 日1~3月期実質国内総生産 -0.2%
GDPデフレータ
3.2%
3月鉱工業生産指数 -1.1%
第7回目 2025年5月19日
4.資産市場における行動理論
要点
4. 1 消費・貯蓄理論
・国内総生産GDPの実質化
4. 2 貨幣一時的一般均衡理論(フローの枠組み)
・2025年、1)世界経済予測と石油需要予測、2)世界経済・政治の見通し
4. 1 消費・貯蓄理論
今回は、伝統的実質ライフ・サイクル理論および貨幣一時的一般均衡理論による名目ライフ・サイクル理論を説明します。消費者が、1期間、予算内で、消費者の効用関数のもとで、効用が最大になる消費量の組を決める問題があります。この消費決定問題を、2期間以上に拡大して、終身まで計画する問題にすると、ライフ・サイクル理論になります。伝統的経済理論では、異時間の経済量の比較は、実質化して比較します。ところが、日常生活では、練習問題にあるように、経済取引は、貨幣を用いますから、消費者の所得、支出、貯蓄、税は、貨幣(円)で評価されます。
貨幣には、比較時間内の交換手段、価値尺度および異時間の価値比較尺度という機能があります。お店で、台湾パイナップル1個700円を買うとき、700円と交換して、パイナップルを手にします。700円が貨幣の価値尺度で評価した値です。異時間の価値比較は、次の週、同じ店で、台湾パイナップル1個買うとき、円の価値尺度で、700円で、表示されていることをいいます。このため、貨幣は貯蔵手段として使用できます。
さらに、貨幣自体に資産価値があると認識される国債管理通貨制度の時代になり、「貨幣ベール観:貨幣自体に価値がない」という考えは、経済が崩壊している国以外は、取っていません。
現在、日本国内で、経済取引されるものは、貯蔵価値のある通貨単位(円)との交換比率で表示される相対価格です。りんご1個269円といいますが、通貨単位とりんごの相対価格は、円/個という比率で表されます。すべての経済財は単位量が円で評価されます。
かつては、金や銀の貨幣がありましたが、紙幣と金との交換比率を法律で定め、兌換紙幣を発行しました。現在は、すべての紙幣は、不換紙幣です。
日本も、円が金という金属との公的交換性がなくなり、すべての経済財は円による絶対評価です。継続して、すべての経済財の円評価が増加すれば、インフレーションであり、逆は、デフレーションです。
現在、植田日本銀行総裁が、ゼロ金利政策は解除しましたが、金融緩和は続行、株式や国債を買い上げ、それらの価格上昇を引き起こしています。財・サービス価格は、海外市場のインフレーションと為替レートの日本円価値減少(減価または円安)により、3%のインフレーション状態が続いています。財は、中国製品を輸入していて、150円台の為替レートですから、輸入価格が上昇しています。サービス価格は、販売、運輸、建設で上昇していますが、財に転嫁されにくいのですが、政府が転嫁するように、大企業に要請しています。
第3次産業では、労働が生産費のほとんどを占めますから、その産業の賃上げは期待できませんでしたが、政府が、今年の春闘から、中小企業の多い第3次産業に賃上げを要請しました。資産市場価格の高止まりには、金融緩和が貢献していますが、一年間、毎月、生鮮食料品を中心に、値上げが続き、消費者の節約志向が強く働き、消費需要が減少しています。第3次産業のサービス市場には、店舗新築・改装等の投資がありません。
本題に戻ると、個人がライフ・サイクル理論にしたがって、終身の消費・貯蓄計画を立てるとき、予想所得および個別の品物の予想貨幣価格で計算すれば、ラスパイレス型注)実質化をしていることになります。インフレ時代では、継続的に大幅な物価上昇があり、実質化して、異時間の経済量を比較して、経済成長を実質的に考察する意義があり、物価変数は実質的経済成長論に入りません。日本経済のように、逆に、デフレーションが20年間続き、リフレーション政策を取ったのが、黒田前日銀総裁の超金融緩和です。結果は、1%程度のインフレーションとなりましたが、所得は増加せず、実質賃金率が長期間マイナスでした。消費需要増、それに伴う投資増で、経済成長が加速され、インフレが増幅されるという世界には戻れませんでした。
1970年代、1971年ドル金本位崩壊、変動相場制移行、1974年石油危機、狂乱物価まで、世界経済成長モデルは、実質的経済成長論が全盛期でした。しかし、物価変動が経済成長率より、大きい経済変動をすると、物価予想は、経済成長ないし変動モデルに入ってきます。マクロ貨幣的経済成長論はありましたが、貨幣・資産市場のマクロ動学化は研究が進んでいません。
1970年から、ヨーロッパで、Hicks=Patinkinの流れをくむ、ミクロ貨幣一時一般均衡論の数学モデルの研究が始まりました。貨幣・資産市場のミクロ動学化は、研究が進んでいません。しかし、家計部門において、名目ライフ・サイクル理論は、実質モデルに貨幣・債券を入れた予算制約式のもとで、多期間効用関数を最大化するので、形はあまり変りありません。
注)ラスパイレス型価格指数(消費者物価指数CPI)は、比較時の数量は、2年後でなければ手に入らないので、基準時のままとし、比較時の価格は手に入るため、比較時価格×基準時数量で合計した比較時価値合計を作成し、CPI=比較時価値合計/基準時価値合計を計算したものです。比較時の価値の実質化は、比較時の価値をCPIで割ります。今回の終わりに、国内総生産GDPの実質化を載せています。
実質ライフ・サイクル理論
図4.1に、消費者の最適解が原点に凸の無差別曲線と北西から南東へ引かれた直線が、この消費者の予算線である。点Aは、(消費者の初期資産+現在所得a0+y0、将来所得y1)の組を表す。点Aをとおる予算線上で、消費者は最適消費量を選択する。選択する判断は、同じ効用を表す無差別曲線u1=c0c1(定数u1のとき、双曲線として描ける。)と予算線との交点を選ぶ。無差別曲線は、右上にいくほど、選好順位が高くなる。無差別曲線と予算線とが接する点が、消費者均衡点Eである。
名目ライフ・サイクル理論
図4. 5に、最適解の点Eを示している。貨幣残高m0があるため、消費は期間1では、e1+m0/p1まで可能である。
問題は、予想価格p2である。消費者が現在価格p1と同じp2を予想している場合、p1が十分低い水準から上昇させるならば、予算線EAの傾きは変化せず、m0/p1が小さくなるから、点線 のように左側へ並行移動し、同じ点線 の無差別曲線との新均衡点では、消費財の需要は減少する。これは、実質貨幣残高m0/p1が減少するためで、実質残高効果という。
ところが、消費者が、インフレーションp1<p2を予想していると、予算線の傾きはEAより、BA’のように傾斜が緩やかになる。需要は、いったん、左へ移動する実質残高効果で減少するが、次に、無差別効用線u2上に移動する異時間代替効果が働き、需要が増加する場合がある。例えば、2022年3月から、世界ほどではないが、日本も、インフレーションに入っている。収入は上がらないので、購入額ほど、食料品量は買えない。実質残高効果が働く。しかし、インフレーションは続くと考えれば、あがりそうな食品は、今買う方が安く買えると思い、その現在消費量を増やそうとする。これが異時間代替効果である。灯油が上がるから、今、タンクいっぱいにする行動である。
デフレーションの場合は、傾きは急になる。均衡点は、右に移動する。
すべての消費者は、インフレーションp1<p2を予想し、初期の貨幣残高m0を保有しているとする。財市場において、p1が十分低いとき、競り価格p1を上げると、個別超過需要c1 -e1は正である。財市場の総超過需要がゼロにならないので、市場は均衡しない。
少なくとも一人の消費者が予想価格p2を固定していると、その人の縦軸切片(p1/p2)e1+ e2+m0/p2は上昇し、横軸切片e1+m0/p1は減少して、BA’線が右上に回転移動し、異時間効果が働かなくなる。この人の個別超過需要は0になって行き、市場は均衡する。
貨幣をもつ一般均衡理論では、予想条件では、市場均衡しない場合がある。消費者の将来価格予想が取り扱える点で、実質ライフ・サイクル理論と異なり、将来価格予想を分析できるようになった。さらに、貨幣を公定歩合で各主体に供給できる中央銀行を導入すると、中央銀行は、金融政策の手段である公開市場操作および貸出政策を実施できる。
・ 国内総生産GDPの実質化
一国の1年間の経済主体の経済活動は、国民経済計算SNA(System of
National Accounts)で測定・記録・公表される。経済基盤情報として、3カ月ごと、前四半期の国内総生産GDP(実際は、GDP確報は2年後公表なので、速報性のある国内総支出GDE,会計上GDP≡GDE)が政府から公表される。これは、景気観測の情報として重要度が高い。
デフレーターの作成
基準時を0とし、比較時をtとする。商品は、りんごとみかんとする。
商品 基準時0 比較時t
価格P0 数量Q0 価格Pt 数量Qt
りんご 100円 20個 120円 30個
みかん 20円 100個 30円 80個
基準時および比較時のりんごおよびみかんの購入合計は、それぞれ、その時点での名目値といい、次の通りである。
ΣP0×Q0 = 100×20 + 20×100 =4,000
ΣPt×Qt = 120×30 + 30×80 =6,000
これら名目値同士で、購入額を比較するとき、りんごとみかんの価格が変化しているので比較できない。そこで、基準時から価格が不変だったとして、価値額ΣP0×Qt を計算する。これを比較時tの実質値という。上の例では
ΣP0×Qt = 100×30 + 20×80 =4,600
実質値 ΣP0×Qtは、変形すると
ΣP0×Qt = ΣPt×Qt
ΣPt×Qt
ΣP0×Qt
このとき、分母の比率(ΣPt×Qt)/(ΣP0×Qt)をパーシェ型価格指数(GDPデフレーター)という。この指数で、基準時の名目値を割れば、基準時の実質値がえられる。上の例では
パーシェ型価格指数=(ΣPt×Qt)/(ΣP0×Qt)=6,000/4,600≒1.3 。
しかし、比較時の数量Qtのデータは、すぐえられないので、(ΣPt×Q0)/(ΣP0×Q0)とした、ラスパイレス型価格指数を作成する。これは、消費者物価指数CPIとして用いられている。上の例では、
ΣPt×Q0=120×20 + 30×100 =5,400であるから、
ラスパイレス型価格指数=(ΣPt×Q0)/(ΣP0×Q0)=5,400/4,000≒1.35。
これらの価格指数を、集計量を比較可能にするデフレーターとよび、公表されている。
資産形成論の本文4.1において、若年世代および壮年世代の消費・貯蓄の決定をそれぞれ2期間モデルで示している。経済学教科書では、2期間モデルによって、ライフ・サイクル理論が説明される。本文の中で、実質所得、実質消費量、実質貯蓄量が使われている。これらは、パーシェ型価格指数またはラスパイレス型価格指数で実質化している。生涯所得の推計という実務(例えば,裁判所の生涯所得推計法)は、比較時の数量Qtのデータが得られないので、価格Ptだけを予想し、基準時の数量データQ0を使うのは合理的である。
国民総生産GNP(Gross National Product)と国内総生産GDP(Gross Domestic Product)の概念の違い
「国内」とは、「ある国の政治的領土からその国に所在する外国政府の公館と外国軍隊を除き、領土外に所在する当該国の公館と軍隊を加えたもの」である。「国民」とは, 国内の居住者である。国内総生産GDPは、国内の要素所得Y(付加価値合計)に固定資本減耗Dおよび間接税-補助金を加えたものである。国民総生産GNPは、国内総生産に海外からの純要素所得ΔFYを加えたものである。
・ 2025年 世界経済と石油需要予測、世界経済・政治の見通し
1)IMF、OECD、ADBの経済見通しとIEA、OPECの石油需要予測
IMFの世界経済見通し、OECDの加盟国経済見通しおよびADBの新興アジアの経済見通しが、経済成長率とインフレ率の2025年および2026年の予測値が公表されている。
ウクライナ戦争で、世界インフレがはじまり、中央銀行は、自国のインフレを押させるため、政策決定会議ごとに、政策金利を上げてきた。今年は、日本以外、インフレ率が、政策金利を下回り、消費需要のインフレ抑制が効いて、GDP伸び率が止まってきている。各見通しは、トランプ関税で、対米輸出が減少する国では、政策金利がインフレ率にならび、消費需要を回復させ、企業の金利負担を軽減する景気刺激策を取り出した。米国は、関税効果で、上乗せインフレは続き、FRBは政策金利を維持、4.5%の金利高は続くから、国内投資は縮小する。米国景気は、後退する。ユーロ圏・英国では、25年は、成長率は、トランプ関税で停滞する。他も、世界需要減で、資源安が働き、インフレが2%台に落ち着いても、成長率は下がると見ている。
石油需要予測は、IEA、OPECともに、25年は、需要が減少する。中国の経済成長率が減少し、石油需要が減る。
IMF世界経済2025年、2026年の見通し
OECD
2025/4/14発表 2024 2025 2026 2024/3/17発表2025 2026
世界GDP 3.3 2.8 3.0 3.1 3.0
米国 2.8 1.8
1.7 2.2 1.6
ユーロ圏 0.9 0.8 1.2 1.0 1.2
英国 1.1 1.1 1.4 1.4 1.2
日本 0.1 0.6 0.6 1.1 0.2
新興・途上国 4.3 3.7 3.9
中国 5.0 4.0 4.0
4.8 4.4
インド 6.5 6.2 6.3
6.4 6.6
世界インフレ率 5.9 4.3 3.6 2.8 2.6
ADB(アジア開発銀行)の新興アジア経済見通し
2025/4/9発表 2024 2025 2026
新興アジア 5.0 4.9 4.7
中国 5.0 4.7 4.3
インド 6.4
6.7 6.8
新興アジアインフレ率 2.6 2.3 2.2
IEA石油需要予測
2025/5/15発表 2025 2026
世界需要日量 1億390万バレル 1億470万バレル
世界供給日量 1億460万バレル 1億560万バレル
OPECプラス石油供給 2025/4,5,6
2024/5/14発表 日量41万バレル増産
2)世界経済・政治の見通し
ウクライナ戦争経過
ロシア軍は、ドンバス地域を2023年5月9日の戦勝記念日まで、完全制圧を命令したが、その間目立った戦闘は、バフムート攻防戦に限定され、ワグナー会社と精鋭部隊を投入したが、制圧できなかった。6月ワグナー社は、バフムート市街を奪還、社員を撤退させ、ロストフ市ロシア軍司令部に帰還、モスクワまで進軍、プーチンと決裂、ベラルーシに移動した。その後、プーチンとの話し合いが不調、自家用機と共に、墜落した。
ウクライナ軍の反転攻勢は2023年4月からだったが、EU諸国の戦闘車、戦車、砲弾等軍備と乗員の訓練に遅れがあり、東部・南部の天候待ちで、6月からになった。ウクライナ軍が反転攻勢を開始したが、9月南部戦線で、第1防衛線を突破、ロボチィネ村まで到達したが、米軍の予算が成立せず、弾薬不足に陥り、他方、ロシア軍は北朝鮮から、弾薬、ロケット弾、ミサイルを調達、南部戦線は膠着し、東部のバフムートから、50㎞南、ドネツク市から15㎞のアウディイウカ陣地に、ロシア軍が猛攻をかけて来た。ウクライナ軍は、南部戦線の機械化旅団を救援したが、2024年2月で、すべての前線で、弾薬はつきて、シルスキー新総司令官は、アウディイウカ守備隊を完全撤退させた。6月からの反転攻勢は、失敗に終わった。その責任は、ウクライナ軍を3方向から攻勢させたこと、軍装備、弾薬も、3分散されたため、ロシア軍を圧倒、突破できなかった。
ロシア大統領選後、反対に、ロシア軍は、ハルキュウ州境とドネツク市間の東部戦線に戦力を集中、特に、2023年10月から、2024年3月大統領選の戦果としてアウディイウカ陣地陥落をめざし、兵力・軍装備と北朝鮮砲弾・ミサイルを飽和攻撃し、ウクライナ軍は負けて西方に撤退した。
2025年ウクライナ戦争見通し
ロシア軍は、2年目になる軍事目標である、ドンバス地域を2024年5月9日の戦勝記念日まで、完全制圧は達成できなかった。プーチンが新大統領に就任し、現在、新政府閣僚を任命している。ゲラシモフ総司令官は再任、ショイグ国防相は、ベロウソフ新国防相に交代した。ロシア新体制は、プーチンの演説から、特別軍事作戦の続行が、核心にあり、その作戦が終了するのは、クリミア半島、東南部4州を6年間、維持することだろう。その間、軍需産業を主体に、新たに、NATOに加盟したフィンランド・スウェーデンとの国境線から、バルト海、バルト3国・ポーランド・ウクライナ含め、ロシア連邦の熱い国境線防衛に、軍装備・施設を増強、毎年、予算を増やす必要がある。
2024年前半、ロシア軍はアウディイウカ陣地攻略と、ハルキュウ州まで、バフムートを含む北東部で、西進した。さらに、ハルキュウ州からベルゴロド州に、反ロシア軍事組織が頻繁に奇襲攻撃をかけてくるため、看過できず、5万人5個師団を投入、ハルキュウ州国境10㎞を確保するため、侵略を開始した。ウクライナ軍の軍資源の枯渇を見て、新たに、ベルゴロド州国境からハルキュウ州巾10㎞を侵略したことは、ロシア政府は、敵国がGDP10倍である限り、遠慮なく侵略する意思を示した。ロシア国境周辺国は、この政権がNATO諸国に軍資源で勝てば、問答無用で、侵略をすると、枯渇しないように、軍備を圧倒すべきである。今回のように、ロシア軍が国境を越えてくれば、NATOは、逆に、ロシア領に10km、保安措置で、進軍すべきである。今のロシア政府に、国際法に基づく主張は、聞く耳はもたない。
2024年後半、ロシア国防予算は、すでに、半分は消化、残り、5兆ルーブルを年末までに消化する。ロシア軍は、バフムート・アウディイウカ・ドネツク市を結ぶ線は、2年間で10兆ルーブルを費やし占領した。2年間で、兵士の戦死傷者30万人以上・陸海空軍装備・外国からの輸入軍装備を消耗した。戦時経済からみれば、流動費30万人は、戦時労働者として、消失した。固定費の海軍艦船、空軍航空機・防空システム、陸軍火砲、装甲車、戦闘車、戦車等を破壊された。プチーチンは、ウクライナ占領地に、新たに、兵士17万を投入するというから、年間、戦時労働者を損失した予測値15万と数値がほぼ一致する。破壊された固定設備は、2024年で、2023年で失われた分を、軍需産業に発注する。ロシア企業の生産能力から、艦船、航空機、装甲車、戦闘車、戦車・S400等、重量設備ほど、年間充足率は落ちる。軍事消耗品である砲弾、ミサイル、ドローンとちがって、艦船、航空機、装甲車、戦闘車、戦車・S400は、外国から購入は出来ない。
ウクライナ軍は軍重装備を、西側から供与を受けるから、ロシア軍より優越していく。ウクライナ徴兵と適性配属がすんなり、決まり、訓練がすむ2024年8月以降のウクライナ軍の反転攻勢は、第1次反転攻勢よりは、戦果が確実に見込める。ウクライナ戦争におけるウ・ロ軍装備の優劣が明白になり、NATOおよび日本は、軍重装備は、新装備に切り替えが必要になっている。GDP2%を防衛費に投入する方向に、コンセンサスができつつあり、ユーロ圏20カ国では、2023年名目GDPは、15兆5483億ドルである。その2%は、3109.66億ドル(46兆6449億円)となる。日本は2023年名目GDP591兆4820億円で、その2%は11兆8296億円である。
2024年後半、ウクライナ軍重装備は、占領地のロシア軍重装備より、優越していく。2023年秋から、ウクライナ軍は枯渇し、ロシア軍は調達できた砲弾、ミサイル、ドローンは、秋以降、両軍生産、ウクライナは供与を受け、量は1対1の互角になる。1000㎞のロシア軍防衛線は、南部をふたたび、第1次反転攻勢の3倍で進軍すれば、すなわち、5万以上の5個師団が、秋から、進軍すれば、南部の分断に成功し、東部ロストフ市およびクリミア半島からのロシア軍の兵站は遮断できる。しかし、F16の実戦配備があっても、昨年と同様な、数個旅団1万程度では、2重防衛線と、幹線沿い高地に陣取る火砲群の餌食になり、南部分断作戦は成功しない。
2024年8月、ウクライナ軍機動部隊は、クリコフ州スジャを越境攻撃した。モスクワまで、600㎞、1000㎢以上を占領し、主要な弾薬庫、空軍基地をドローン、中距離ミサイルで、攻撃、ウクライナへのドローン・ミサイル攻撃を国境から300㎞下げた。ウクライナ長距離ドローンが、1000㎞以上離れた、空軍基地、軍需工場、石油製品貯蔵所、発電・変電設備、ガス・パイプラインの攻撃を始めたことが新しい。ロシア軍は、クリコフ州奪還に、東南部から部隊を移動させず、北朝鮮と交渉をし、北朝鮮契約兵を2024年12月までに、1万2千人調達、北朝鮮製の砲弾、ミサイルを調達、2025年に入って、ロシア軍は、定期的な16万人徴集し、クリコフ州の奪還作戦を強行、2025年3月奪還に成功した。
2025年3月トランプ大統領が、ロシア・ウクライナ両国の停戦仲介に入った。5月16日トルコの仲介で、ロシア・ウクライナの直接交渉が、3年ぶりに開かれた。捕虜交換が成立しただけであった。ロシア側は、今年度は、東南部の完全占領、2024年5月越境10㎞のハルキュウ州、クリコフ州を奪還し、国境緩衝地域をスムイ州の必要性を痛感、両州の侵攻を主張した。
ウクライナ軍は、米国の軍支援が不確実となり、クリコフ州から撤退、東南部は膠着状態のままである。ウクライナ各地に対するミサイル・ドローン攻撃は、続いている。ウクライナ軍需工場は、EU軍需工場の進出で、砲弾等の消耗品生産、小型偵察、自爆ドローンの生産、年間400万機、射程100㎞の滑空ミサイルの増産によって、ロシア軍占領地内で使用する量は、ほぼ1対1になるようだ。ロシア軍を東部戦線の膠着状態に抑えているのは、現在、2対1になり、今年中に、EUからの供給も増加する。
日本自衛隊の高機動車は、昨年度、100台供与されたが、今年度は30台のようだ。むしろ、商業汎用車の中古車である、大型建機、ランドクルーザー、パジェロ、軽トラの方が、軍装備の運搬、1500kmへのアクセス兵站輸送路建設、偵察・自爆ドローンを撃墜、ジャミングする機動性をつける改造ができ、部品も豊富に供給できる。ロシア軍は、周辺国からの中古車両が手に入らなく、占領地での移動が不便になっている。
ガザと中東
2023年10月7日、ガザから、隣接したイスラエル領に、ハマスが奇襲をかけ、村と国際コンサート会場を攻撃し、1400人以上の死傷者と220人の人質をとって、ガザに引きあげた。イスラエル軍は、直ちに、30万人を召集、ガザ北部と南部を分断、北部市民を南部に避難させた後、空爆、市街地と地下トンネルを破壊した。南部と北部を建機で、分断、ハマスと人質解放をカタールおよびエジプトで、継続して、人質半数は、解放したが残りは、解放しない。現在、南部も空爆、エジプト国境ラファ検問所まで、北部と同様、空爆する状態にある。その間、南イエーメンのフーシ派のミサイル攻撃と紅海・アデン湾の商船をミサイル攻撃したが、欧米の艦船が、基地を同様にミサイル攻撃、商船の通航を護衛している。シリア・ダマスカスにあるイラン大使館にいたイラン革命防衛隊幹部をイスラエルが空爆した。イランは、300発ミサイル・ドローンによる、イスラエル報復攻撃後、レバノン・ヒズボラ、シリア・イラク・シーア派のイスラエル攻撃も収まっている。イスラエルのイランへの反撃は、規模が小さかった。
イスラエルは、南部を北部と同様、空爆で破壊、地下トンネルの基地を破壊するまで、作戦は続行するだろう。停戦できず、南部に潜むハマス隊員は脱出できず、人質は、交渉では、生存しては帰らないだろう。ハマスは、すでに、ガザ居住地はラファ近郊以外、灰塵に帰し、ハマス組織は、ガザ指揮部は壊滅した。ハマスの奇襲目的が、ガザ市民の居住地をそのままに、イスラエルにとらわれている同志を奪還するのが、目的だったとしたら、奇襲は目的を達成できず、220万人ガザ市民をキャンプ生活に追い込んだ責任は重い。ガザでは、ハマス隊員を壊滅させられ、家無き難民220万人市民に、生活保障をする財源もない。2024年ハマス組織は、ガザにおいて、テロ組織となり、恒久的に、ガザで政治軍事活動は出来ない。パレスチナ暫定政府が、家無きガザ市民を説得、自治組織を立ち上げ、国連の支援とともに、ガザ自治を回復するようになるだろう。
トランプ大統領は、ハマスが人質解放せず、戦闘を続けるのをみて、ネタニヤフ首相のハマス掃討作戦を支持、ガザ市民は、他国へ移民させる考えを持っている。ハマスが抵抗をやめ、撤退するまで、ガザ市民に対する人道支援は、USAIDを廃止したことにみられるように、救済するつもりは全くない。2025年5月中旬の中東3カ国訪問で、ハマスを支援するカタールから、投資を引き出しているから、ハマスの抵抗は無理がある。
EU・英国
EU・英国は、ウクライナの軍民支援を継続するが、EUで、先端産業の育成に、海外企業を呼び込むことは進展した。ロシアに依存したエネルギー構造から脱却する代替エネルギー設備投資は、期待ほど進んでいない。ドイツは、洋上LNG液化工場船を建造している。EUは、基礎食料の自給率は100%を越えているので、ロシア産の食糧に依存はしない。むしろ、ロシアへの農産物・加工品の輸出が停止し、EU生産者の販路が失われた損失はある。
2023年は、フィンランドおよびスウェーデンのNATO加盟があった。ウクライナは、EU加盟の候補国になった。2024年は、3月から、5月まで、NATOの9万規模の大演習が実施された。米国のウクライナ軍支援予算案が4月下旬まで可決せず、ウクライナ軍は、アウディイウカ陣地を占領され、前線は後退した。この事実に、EUの軍需産業は、米国からの武器供与は、信頼できず、NATOのヨーロッパ独自の武器備蓄の必要性が意識された。トランプ氏が大統領になれば、GDPの2%を要請するはずである。EU独自で、兵器開発を開始することも、始まった。
EUおよび英国は、インフレが収まらず、ECBは、4.5%の政策金利を維持、英中央銀行は5.25%である。インフレが続くと、消費者は、節約で対抗するので、消費需要は実質減少していく。日本と違って、賃金は流動的で、インフレに遅れて上昇。消費は手持ち現金で買うので、不必要な財は買わなくなる。景気はなかなか、上がらない。
ウクライナ戦争疲れ、ガザ侵攻疲れで、消費は委縮しているのは、世界各国皆同じである。ヨーロッパが夏休みに入り、7月、パリ・オリンピックがあり、コロナが弱体化し、再び、世界から観光客が回帰してくる。サービス業を中心に、EUの経済回復が加速されるだろう。日本では、春から、大谷事件で、開幕した米メジャーリーグは、大谷選手の活躍で、盛り上がっている。日本人も、ドジャーズが勝ち、大谷選手が活躍すると、元気が出るという人もいるようだ。パリ・オリンピックは、バカンス入りとともに、ヨーロッパの委縮した経済活動を活性化させる。
英国は、EUを脱退し、NATOとの安全保障は、つながっている。ウクライナ戦争で、ロシアの資源に、依存はしないが、高インフレーションの影響もあって、経済成長が停止した。当時の保守党政権は、EU脱退当時の東欧移住者の増加、漁業の漁獲高の調整がつかず、EUの法制度に従うことを嫌っていた。故エリザベス女王も、暗黙の脱退了解があった。現保守党は、人気が落ちて、EUとの経済協定を加盟国並みにもどす方が、成長率は、回復するだろう。
2025年1月トランプ大統領が就任し、関税政策を始めた。EUは、報復関税をかける。英国は、対米貿易は、赤字なので、トランプ関税公式では、関税率はゼロになる。EUは対米経済との縮小均衡になるから、米国以外の販路を求め、国内経済の内需を高める経済政策をとることになる。
ロシア
ロシア経済は、IMF4月予測では、2024年3.2%、2025年1.8%成長である。軍事予算の倍増と、軍事産業に増産させ、外国資本設備を摂取、類似製品を生産したため、成長率が上がっている。ロシア人の夏のバカンスは、パリ・オリンピックでも、ロシア連邦からの観光客はこない。ウクライナ戦争以前は、南欧諸国がロシア観光客の人気地であっただろうが、戦争が長引くにつれ、ロシア人は、東南アジアに行っている。その分、観光収入が減るが、これが、6年間、常態となり、ロシア経済と完全に分断される。
2025年1月、トランプ大統領になって、世界経済の成長率は1%以上縮小を予想している。原油相場は、産油国のシェア争いで、供給を4月から増産し、原油価格が60ドル台に下落している。ウクライナ軍の石油施設へのミサイル攻撃もあり、生産力が低下、原油価格が60ドル台になると、収入がさらに、減少する。国家予算の歳入が減少する。内需産業から、軍需産業に、雇用・資本を移転しているので、内需産業、雇用者に増税もできず、中国から、内需の輸入、イラン、北朝鮮からのドローン・ミサイル・砲弾を輸入し、外国の契約兵は集まらず、国内徴集兵の定期召集16万人だけで、動員数は低下している。国内兵を突撃兵として、最前線で消耗させることはできないだろう。
米国
米国経済は、2023年に引き続き、先進国では、2.7%成長で、インフレ率は直近では3%で、安定している。政策金利5.25%は、インフレ率の2倍あり、利下げが、市場では予想されている。設備投資、住宅建設に影響する長期金利は、直近では、4月4.539%である。米国では、インフレと賃金率上昇が同時化するから、消費需要は、実質的に変化しない。2024年11月大統領選があり、0.25%利下げが、6月11日~12日の公開市場委員会で決まる。大統領選の論点として、中国貿易について、バイデン大統領は、戦略物資の取引禁止、半導体工場の国内誘致、トランプ氏は、中国企業のEV車メキシコからの輸入禁止、対中関税を引き上げるという。米中貿易に、直接、減少を狙っている政策は、トランプ氏である。
米大統領選挙は、トランプ氏の勝利となった。2025年1月の就任後、トランプ関税行使に従って、米国と貿易関係を持つ各国に、関税をかけ、戦略的品目には25%の関税、中国には145%の関税をかけた。関税による期待インフレ率が上昇、FRB政策金利4.5%の高止まり、債券、株式価格が暴落したため、トランプ政権は、軟化、4月から、一律、10%を発動、超過関税は、90日間交渉することにした。対中国関税は、5月14日115%引き下げている。2025年後半、トランプ関税政策による、スタグフレーションが予想されている。
インドおよびASEAN
インドは、ウクライナ戦争のエネルギー・食糧インフレーションに対し、エネルギー面では、ロシアから割引価格で、原油を輸入し、国内消費を上回る石油製品は、EUに輸出した。食料は、主食が米であり、ウクライナ、ロシアの小麦粉には依存しない。どういうわけか、米の輸出国だが、輸出禁止にした。エネルギー・食糧インフレーションは、遮断され、高度成長を2年間続けている。
製造業の発展に、力を入れるようになったのが、最近のインド経済の特徴である。人口成長で、中国抜き、世界一の人口大国になる。インド南部で、ソフト産業が、1985年の頃から、世界的に有名だったが、最近は、人口増を農業部門で吸収できず、余剰人口は、製造業の付加価値の高い産業を育成、雇用し、経済成長することに力を入れ出したのであろう。IMFの2025年の経済成長率は、6.7%で、アップルがインドで生産することになった。インドの人口は中国を超え、製造業の、トランプ関税をかける輸入代替政策から、人口ボーナスを利用して、外資導入、特に、アフリカへの商品供給力を伸ばし、アフリカ市場への輸出競争力をつけるつもりである。中国の高度成長が、10年続いたが、インドも6%以上の高度成長期に入ったようである。
インドは、米国世界関税政策、米国の対中国貿易縮小、EU・ウクライナ対ロシアの戦争を尻目に、製造業の開放に踏み切り、巡航経済成長の高速道路に入ったようである。国際的に、なにも問題ないため、2030年以降、米中経済戦争が終了、ともに、経済成長はせず、インドが、進出した外資とともに、製造業を、低価格インドソフト産業によって、AI高度化し、世界市場に進出してくる。地球温暖化とともに、インド風熱帯化文明となり、暑気払いのインドバラエティーが世界で盛んになるかも。中国は、社会主義こんこんちきで、面白くなく、日本企業も投資しようがないが、インド映画の集団舞踊もええじゃないかで、「インドの夢」を語ろう会に賛同する日本企業は多くなっている。
東南アジア諸国は、コロナから、サービス業が回復し、自律成長軌道に入っている。ADBアジア開発銀行の予測では、2024年は成長率4.8%、25年は4.7%、インフレ率は、3.2%、3%である。域内の問題は、中国の南シナ海進出に対し、フィリッピン政府が、前政権の中国寄り立場から、対決型になり、漁船、中国海警船との衝突が増え、日本は、巡視船をフリッピン政府に借款している。今年も、追加、建造する。
ミャンマー軍事政権は、2023年は、反軍勢力の政府軍攻撃が強まり、3方向から、首都ネピドーは、包囲されて、国軍兵士の降伏も多く、徴兵令を強化しているが、隣国に逃れている。中国の軍事支援が、国軍本営に届いているのかわからないが、空軍の空爆は続いている。反軍3勢力に、携帯ミサイルが届くようになれば、国軍機械化部隊による軍事的優位は薄れる。国軍は、兵弾つきて、ネピドーから、市民が避難するような事態になりそうだ。トランプ氏の関税賦課は、一律10%になる見込みはある。
中国
中国は、不動産業界の主要企業が、債務超過に陥り、不動産投資は止まり、全国の都市住宅価格は、下落が続いている。台湾侵攻問題で、海外企業直接投資は減少傾向にあり、米国の半導体国内回帰政策で、中国に米先端品が輸出されず、中国先端商品に搭載できず、輸出が減少している。中国は、伝統的雑貨・衣類製造は、米国市場が制限されても、アジア、欧州、経済制裁を受けるロシア連邦には、依然、輸出力は強い。各種ドローン、5G対応携帯やEV等の世界最先端、高付加価値製品は、輸出に摩擦がでてきた。
2025年は、製造大国25の完成年であるが、習主席には、その目標は達成できない。その輸出輸入経路である一帯一路も、相手国に、断られる事例も出ている。2025年、不動産市況の回復、不動産投資の底打ちはせず、国有銀行、地方銀行の不良債権処理は、手つかずのようで、金融破たんが発生するまで、その抜本的処理は行われないだろう。
トランプ関税戦争は、30%に引き下げたが、任期中は、高関税、中国船舶の入港税徴収はやめないだろう。中国の黒字は激減、米国債の保有も激減する。他方、米国以外との貿易拡大を交渉して、米国依存はしなくなる。中国は、外交、国防、貿易で、2国間で協定を結ぶ主義だったが、トランプ米国経済との分断化となり、EU、日本、ASEANとも、貿易の多国間協定を結び、WTOを機能させる方向をとるだろう。いわゆる社会主義的制約はとりはらい、自由貿易主義をとる。
日本
日本は、岸田首相が、政治資金規正法で、自民党の有力者をはずし、2024年9月までの、総裁選で、選出されないのは明らかで、政権誕生以来、インフレ、円安、安倍氏暗殺、岸田氏暗殺未遂事件があり、国民生活は、毎月3%の必需品値上げで、2023年春闘で賃上げはなく、非正規の最低賃金は十円玉程度の時給を決めた程度の所得では、すべての家計は、節約、倹約生活を1年以上続けていたことが、四半期GDPの消費需要の減少に表れている。岸田政権は、2024年6月から、1年間、月4万円の減税をするというが、インフレが日本では、2%台になり、中小零細の賃金が3%を越えるのは、2024年は出来なかった。総裁選は、岸田氏は降りて、石破氏が選出された。内閣を立ち上げると、すぐさま、衆議院解散に踏み切り、与党は過半数をえられず、予算案は、国民民主党等の選挙公約を取り入れる形で、修正され、2025年3月末成立した。2024年8月の令和米騒動が勃発、例年5キロ2000円の米が、2倍以上で販売される状態が、現在もつついている。そのため、CPIは、毎月3%台を続伸、2025年第1四半期、実質GDPは-0.2%である。2025年春闘の賃上げは吹き飛んでいる。石破首相が、トランプ関税に、国難発言をしたが、内政は火の車となり、7月の参議院選は、惨敗するのは確実である。
今週(2025年5月19日~5月23日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、5月13日から16日まで、トランプ大統領は中東3カ国訪問、取引をしました。5月14日スイスで、米中の貿易交渉が行われ、米国は145%関税を115%引き下げ、30%とし、中国は同様に引き下げ、10%としました。5月16日、トルコの仲介によって、3年ぶり、イスタンブールで、ロシアとウクライナの外務次官級の直接交渉があり、双方の停戦条件を主張しあい、1000人の捕虜交換が成立しました。
今週のイベントは、19日から22日まで、ジュネーブで、WHOの総会が開かれます。パンデミック条約を採択する予定です。米国は、脱退したうえ、米国の薬価を引き下げました。新型コロナ禍では、米企業の感染症ワクチン開発が大いに役立ちましたが、米企業は、新薬開発を恐れがあります。20日カナダで、22日まで、G7財務相・中央銀行総裁会議があります。
経済統計は、次の発表がありました。
予測値 実現値
5月12日 日4月景気ウオッチャー調査 44.7 42.6
日3月国際収支 5500億円 2兆7231億円
13日 米4月CPI 2.4% 2.3%
15日 日4月工作機械受注額
米4月小売売上高 0.0% 0.1%
4月鉱工業生産指数 0.1% 0.0%
16日 日1~3月期実質国内総生産 -0.2% -0.2%
GDPデフレータ
3.2% 3.3%
3月鉱工業生産指数 -0.3% 1.0%
経済統計は、次の発表があります。
予測値
2025年5月19日 中4月小売売上高
4.9%
米4月景気先行指数 -0.8%
20日 日4月全国コンビニエンストア売上高
中5月最優遇貸出金利
21日 日4月貿易統計 2420億円
22日 日3月機械受注統計
-2.2%
4月全国スーパー売上高
米5月米製造業購買担当者景気指数PMI
23日 日4月全国百貨店売上高
4月全国消費者物価指数
3.5%
第8回目 2025年5月26日
資産市場における行動理論
要点
・4. 3 債券・株式現物・先物市場一般均衡論
・4. 4 債券期間構造理論
4. 3 3資産現物・先物一時的一般均衡理論
前回の確実性下の貨幣一般均衡モデルを、不確実性下2期間貨幣一時的一般均衡モデルによって、債券・株式の2資産市場を考え、債券・株式の現物・先物価格を決定します。このモデルは、Grandmont,
J.-M., “On the Short Run Equilibrium in a
Monetary Ecomomy,” 1974, およびGreen,J.R.,“Temporary General Equilibrium in a
Sequential Trading Model with Spot and Futures Transactions,”1974を合体し、筆者の論文、貨幣があり、現物・先物取引のある交換経済における一時的一般均衡モデル
(Nishimura,K.,‟Temporary
General Equilibrium in Multi-period Forward Markets,”)がもとになっています。
2資産現物・先物市場において、投資家は、資産価格不確実性に対して主観的確率分布をもち、確実性下の予算制約式と同様に、自己清算制約式のもとで、与えられた現物価格・先物価格に対して、2期間の最適化をし、市場均衡条件をみたす市場均衡解で、資産を交換し、期間2の先物契約をします。主観的確率分布を仮定することが、数学的で、準備がなければ、分かりません。他は、確実性下と同じ設定になります。例として、投資家の効用関数をコブ・ダグラス型として、前回の確実性下の問題と比べつつ、分布関数によらない最適解を求めました。
資産市場における消費者の行動と計画
消費者は、2期間の永久債の賦存量b0∈R+ をもつ。ここで,b0は確実に予見できるものとする。計画時の期首に、消費者は負債をもっていないとする。また、消費者は、市場が開かれる前、株式k0 ≧
0をもつ。
行動と計画
2期間の債券の流列を、b=(b1,b2)∈R+2、株式の流列を、k=(k1,k2)∈R+2とする。今期の先物市場における債券先物契約をcb2とする。消費者は、cb2>0であれば、期間2の期首に債券を受け取る。cb2<0であれば、その逆である。同様に、今期の先物市場における株式先物契約をck2とする。消費者は、ck2>0であれば、期間2の期首に株式を受け取る。ck2<0であれば、その逆である。
消費者は、期間1において、現物資産市場において、将来債券および株式保有計画を決定する。その後、資産先物市場において、債券および株式先物契約を結ぶ。期間1において、消費者が現物市場と先物市場での取引を決定することを行動(action)と呼び、a1=(b1,k1,cb2,ck2)∈R+2×R2で表す。次に、期間2の現物市場において、消費者が取引を決定することを計画(plans)と呼ぶ。期間2の計画をa2=(b2,k2)∈R+2で表す
。
期間1において、市場価格ベクトルは、p1 =(pb1,pk1,qb1,qk1)∈ R+4/{0}であり、ここで、1は、貨幣の価格であり、p1は、債券・株式の現物価格であり、qは債券・株式の先物価格である。期間2の市場価格ベクトルは、p2=(pb2,pk2)∈R+2である。
効用関数
消費者が、資産流列(b1,b2,k1,k2)を選択する際に、期間1の資産選択行動の成果(b1,k1)は、確実性下にあり、期間2の資産選択行動の成果(b2,k2)は,不確実性下にあるとする。消費者の資産流列に対する選好は、von Neumann-Morgenstern の期待効用最大化の仮説をみたす。
予想形成
期間2の現物価格の予想は、先物市場価格qに対して、各期間の現物価格の確率分布ψ(q)を対応させる。これを将来価格の予想形成という。
仮定 4.4 ψ(q):R+2 /{0}→ M(R+ )。
(1)予想形成ψ(q)は、M(R+)が確率測度の弱収束の位相をもつとき連続である。
(2)すべての q ∈R+2 /{0}に対して、int co
supp ψ(q)≠φ
(3)すべてのq ∈R+2 /{0}に対して、ψ(q)(int R+2)=1。
(1)は、確率分布ψ(q)の連続性を、(2)は、投資家の主観的均衡のための必要十分条件を、(3)は、1点予想を排除する仮定である。最適債券量を価格の関数で求め、von Neumann-Morgenstern効用関数uに代入し、予想価格分布ψ(q)による期待効用vを求める。
仮定 4.5 v= u1+∫R+ u2(b2*(p1),k2*(p1))dψ(q)。
現物市場に対する予算制約式
消費者は、 現在においても将来においても、プライス・テーカーであるから、期間1において、価格ベクトルp1を所与として、 pb1・b1+pk1・k1≦pb1・b0+pb1・k0に制約された行動(b1,k1)を選択しなければならない。次に、期間2で不確実性下にあるため、消費者は、期間2で実現する現物価格p2を所与として、計画(b2,k2)を立てる。期間2の予算制約集合は、pb2・b2+pk2・k2≦pb2・b1+pk2・k1と表す。
選好ルール
期待効用関数vは、市場価格p1 を所与として、任意の行動a1,a1′に対して、成果の空間で定義された選好関係≿cと次の関係があるとする。
p1を所与とし、任意の行動a1、a 1′∈β1(p1 )に対して、v(p1,a1)≧v(p1,a1′)であるならば、そのときにかぎり、a1 ≳p1c a1′とする。
先物市場に対する予算制約式
現物市場の最適化問題4.1から、最適債券量b1*、最適株式量k1*が求められた。先物市場では、自己清算取引戦略(qb2,q k2)・(cb2, ck2)=0が予算制約式となる。これにより、自己清算取引戦略であれば、いかなる契約価格q=(qb2,q k2)であっても、富W2=pb2・(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2)はヘッジされる。
仮定 4.6 (qb2,q k2)・(cb2, ck2)=0。
先物市場における消費者の予算制約式は、
β2c(p2)={(b2,k2)∈A2∣pb2・b2+pk2・k2≦pb2・(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2)}と表す。
期間2の期首における支払い可能条件を次のように仮定する。
仮定 4.7 任意の(pb2,pk2)∈suppψ(q)に対して、pb2・(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2)≧0。
現物・先物市場における消費者の最適化
消費者の最適化問題は、次のように設定される。価格ベクトルp1と賦存量(b0,k0)を所与として、予算制約式のもとで、期待効用関数vを最大にする行動(b1,k1)および計画(b2,k2)を決定する。以下、効用関数は、コブ・ダグラス型を仮定し、テキストにある、問題4. 4,問題4.
5、問題4. 6をそれぞれ、次の例題で計算する。この最適化問題は、ダイナミック・プログラミングによって解く。ステップ1では、次の問題を解いて、現物市場における行動(b1,k1)を決定する。
例題 4. 1 ( pb1,pk1)、
(b0,k0) を所与として、
max
u1=b1・k1、subject to pb1・b1+pk1・k1=pb1・b0+pk1・k0 。
{b1,k1}
解 u1=b1・k1=b1(pb1・b0+pk1・k0-pb1・b1)/pk1
=-pb1(bb1-pb1・bb0+pk1・bk0) 2+(pb1・bb0+pk1・bk0) 2
pk1 2 pb1 4 pb1 pk1
効用関数が最大になるb1、k1は、
b1*=pb1・bb0+pk1・bk0 、 k1 *=pb1・bb0+pk1・bk0 。
2 pb1 2 pk1 □
先物市場における最適解は、2段階で求められる。第1段階は、例題4.
2のように、期間2の価格p2を所与とし、期間2の予算制約式の下で、効用関数u2を最大化することにより、期間2の計画(b2,k2)を決定する。そして、例題4. 2の解b2*、k2*を期待効用関数vに代入し、第2段階の例題4.
3に進む。
例題 4. 2 p2≫ 0、 b1*、k1*≧0を所与として、
max
u2=b2・k2 ,subject to pb2 b2+pk2・k2=pb2(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2)。
{ b2,k2 }
解 u2=b2・k2=b2{pb2(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2)-pb2・b2}/pk2
=-pb2{b2-pb2(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2)} 2
pk2 2 pb2
+(pb2(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2) )2
4
pb2 pk2
b2*=pb2(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2)、k2* =pb2(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2) 。
2 pb1 2 pk1 □
ステップ2では、次の問題を解いて、最適債券・株式の最適契約(cb2*,ck2*)を求める。
p2 を基準化すると、解が陽表化できる。
例題 4.3 債券・株式先物価格qを基準化して、q=(1,qk2)≫0のもとで
max ∫b2*・k2*d ψ(q),subject
to q・c= 0 。
{ cb2,ck2}
解 L=∫b2*・k2*d ψ(q)-λq・c
=∫{(pb2(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2))}2 d ψ(q) -λq・cとおく。
4 pb2pk2
∫{pb2(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2)}d ψ(q)=λ
2pk2
∫{pb2(b1*+cb2)+pk2・(k1*+ck2)}d ψ(q)=λqk2,q・c=0。
2 pb2
さらに、債券・株式予想価格p2を基準化して、p2=(1,pk2)≫0とする。例題4.3は、次のようになる。最適解は、E[1/ pk2]およびE[pk2]に依存し、その分布関数形に依存しない。
例題 4.4 債券・株式予想価格p2を基準化して、p2=(1,pk2)≫0とし、債券・株式先物価格qを基準化して、q=(1,qk2)≫0のもとで
max ∫b2*・k2*d ψ(q),subject
to q・c= 0 。
{ cb2,ck2}
解 (b1*+cb2)E[1/ pk2]+(k1*+ck2)=λ
2
(b1*+cb2)+(k1*+ck2)E[pk2]=λqk2、λを消去して、
2
(b1*+cb2)+(k1*+ck2)E[pk2]=qk2{(b1*+cb2)E[1/ pk2]+(k1*+ck2)}。
(cb2,ck2)・(1,qk2)=0は、cb2=qk2 ck2であるから、上式に代入して、
(b1*+qk2 ck2)+(k1*+ck2)E[pk2]=qk2{(b1*+qk2 ck2)E[1/ pk2]+(k1*+ck2)}。
{qk2+E[pk2]-qk22 E[1/ pk2]}ck2=qk2(b1*E[1/ pk2]+k1*)-(b1*+k1*E[pk2])。
ゆえに、最適先物解は、
ck2*={qk2(b1*E[1/ pk2]+k1*)-(b1*+k1*E[pk2])}/{qk2+E[pk2]-qk22E[1/pk2]}
cb2*=qk2 ck2*。 □
4. 4 債券期間構造理論
ライフ・サイクル理論にもとづくならば、各年齢の消費者は、残りの生存期間に得る所得を平均化して、一定の消費額を決め、残りを貯蓄する。さらに、資産選択理論にもとづき、消費者は、貯蓄を安全資産と危険資産に分けて、資産運用を計画する。ただし、資産選択理論は、安全資産と危険資産の配分を決めるが、消費者が、その比率で、安全資産と危険資産を、それぞれの市場でどのようにして獲得できるかは示していない。本教室では、4.8で、各資産市場均衡を理論的に考察しているので、資産選択理論を資産市場の一般均衡とつなぐ。現実に、利用可能な需要関数を求める。
経済理論では、異時間の交換比率として、利子率がもちいられる。現実の資産市場では、債券と株式の金融商品が取引され、市場均衡債券価格および株式価格が決まる。債券価格と株式価格は、実際に受け払われる単位価格である。債券利子率および株式収益率と債券価格および株式価格との対応関係を定義する。すなわち、貨幣で取引される現実の資産市場を、経済理論市場で均衡を考察するために、変数を変換する。
危険資産のうち、債券と株式の特性を経済理論で分かっている特性と、個別企業の株式価格および経営成績・財政状態の報告書から導く特性を説明する。
債券利回りと債券市場価格の関係
第6回目において、単利の最終利回りRnは
Rn = C+(F-P)/n
P
複利の最終利回りRn
P(1+Rn)n=C(1+Rn)n-1+C(1+Rn)n-2 +…+C(1+Rn)+C+F
によって、定義した。各期間の短期利子率は、通常異なるから、残存期間n、第i期間の予想利子率をri、長期利子率をRnとする。
金融理論において長期利子率Rnと各期間の短期利子率riとは、関係があるとする立場と関係はないとする立場がある。前者は、LutzおよびHicksが主張した利子率の期間構造論であり、後者はCulbertsonの主張したヘッジ(掛け繋ぎ)理論といわれる。
Lutzの要点は、市場関係者の完全予想を仮定し、Rnはriの平均であり、期間構造は利回り曲線によって決定される。HicksはLutzの理論を引継ぎ、不確実性下、予想短期利子率を先物短期利子率に置き換えて、Lutz理論が成立すると主張した。現代の期間構造理論は、Hicksの流動性プレミアム理論にしたがっている。
HicksはLutzの予想理論を受け継ぎ,以下を仮定する.
・ 将来の債券価格は不確実であり,評価損を先物で回避する.
・ 長期貸付は期間1の直物貸付けと残りの期間の先物貸付からなる.
予想短期利子率は,先物短期利子率に代えられ,次のように定義される.
先物短期利子率 fi = ri +Li(i = 2, …, n)
予想短期利子率 ri
流動性プレミアム Li(L2<L3<…<L n)
単利の場合,長期利子率は
Rn=R1+(r2+ L2)+…+(rn+ Ln) = 1 ∑(R1+ri)+ 1 ∑Li (1)
n n
n
Lutzとの違いは、流動性プレミアムの平均が加わることである。
(1)式の左辺は、長期利子率であり、右辺は、長期利子率を先物短期利子率で表した平均利子率である。長期債券市場と各期の先物債券市場は、期間1の直物貸付けと残りの期間の先物貸付で構成された平均長期利子率とで裁定取引が行われ、市場均衡では、(1)式の裁定取引式が成立すると説明される。
ヘッジ理論は、自己の負債Bの満期時点が来るとき、その満期時点に資産Aを合わせて、B=Aとすれば、途中の短期利子率が変動しても、返済不能にならない。
債券投資リスクの測定
債券投資は、原資産が、市場利子率の変化に従い、発行クーポンが変化する。既発債は、残存期間のもとで、市場利子率の変化で利回りが再計算される。残存期間と利回りを並べると、カーブができ、その形状で、利回り変動のリスクを図ることが、実務的に行われている。債券利回りと価格は、反比例するが、その弾力性をデュレーション、コンべくベクシティを計算する。市場リスクと信用リスクを計算することができる。
1) イールド・カーブ(yield curve)の形状
期間構造理論では、利回り曲線は、債券市場の予想形成によって、イールド・カーブ(yield curve)の形状は、縦軸に利子率R、横軸に満期期間(残存期間)yearをとると、4種類(図4.5)ある。実際、債券の種類は、満期期間(残存期間)、クーポン、公社債の発行主体、発行方法によって、多種多様であり、イールド・カーブが専門誌で日々公表されるほど、期間構造が分析上、重視されているとはいえない。Hicksの理論で、国債先物短期利子率を代入して、イールド・カーブを図示すると、市場では、先行き何年で、利子率が上昇すると予想しているか、すなわち、水平から順イールドに転じるかが推測できる。
2) デュレーションとコンベクシティ
市場利子率が変化すると債券価格の変化はどの程度かを測る指標がデュレーションである。デュレーションDは、(1+R)がパーセント変化したときの債券価格Pのパーセント変化として、Pのパーセント変化/(1+R)のパーセント変化を計算する。この比を債券価格の(1+R)弾力性と定義する。(読み方が、分子の分母弾力性となることに注意)
D=- dP /P 。変形して、 dP =-D P (1)
d (1+R)/(1+R) d (1+R) 1+R
デュレーションの値が大きくなると、弾力性が大きい。利子率の変化に対して債券価格の変化が大きいことを意味する。
最終利回りの計算式P(1+Rn)n=C(1+Rn)n-1+C(1+Rn)n-2 +…+C(1+Rn)+C+F を市場利子率Rで置き換える。
P= C + C +…+ C + C+F (2)
1+R
(1+R) 2 (1+R)n-1 (1+R)n
取引する債券のクーポンC、満期期間n、額面Fは、決まっているから、投資家の評価する利子率Rが、債券市場で決まる。(2)式を1+Rで微分すると
dP =-{ C +…+ (n-1) C + n(C+F) }
d (1+R)
(1+R) 2 (1+R)n (1+R)n+1
= -1 { C +…+ (n-1) C + n (C+F) } (3)
1+R 1+R (1+R)n-1 (1+R)n
(1) 式と(3)式を比較して
D={ C +…+ (n-1) C + n(C+F) }。 (4)
(1+R)P (1+R)n-1P (1+R)n P
デュレーションDは,満期までの年数の加重平均であり、債券の平均回収期間を表している。デュレーションの特性は、(4)式から、
デュレーションの値
残存期間n 長い 項数が増えるから、大きい
クーポンC 大きい 分子の債券価格Pが大きくなるから、小さい
利子率R 大きい 分母の各項の1+Rが大きくなるから、小さい
債券投資戦略にデュレーションは応用することができる。
コンベクシティ(Convexity)
さらに、近似精度を上げるために、価格変化に対してテーラー展開式を用いるコンベクシティ(Convexity)がある。
(2)式の債券価格関数を、現在利回り1+R0のまわりで、テーラー展開すると、
ΔP= dP Δ(1+R)+ d2P
Δ(1+R) 2+…+ dn―1P
Δ(1+R) 2+Rn (5)
1!d (1+R) 2!d (1+R) 2 (n-1)!d (1+R) n―1
Rnは剰余である。 (3)式を微分して、
d2P
= 1・2C +…+ (n-1) C + n(n+1) (C+F)
d (1+R) 2 (1+R) 3 (1+R)n (1+R)n+2
(d2P/d (1+R) 2 )/P をCv:コンベクシティ(Convexity)と定義する。(5)式から、
Cv= d2P
1 = [ 1・2C +…+ (n-1) C + n(n+1) (C+F) ] 1
d (1+R) 2 P (1+R) 3 (1+R)n (1+R)n+2 P
テーラー展開式(5)をPで割り、第二項まで取ると、
ΔP≒ dP Δ(1+R)+ d2P
Δ(1+R) 2
P 1!d (1+R) P
2!d (1+R) 2 P
=- D Δ(1+R) + Cv Δ(1+R) 2
1+R 2
これは、債券価格の変化率は、デュレーションをコンべクシティで近似できることを表している。
第2項は、正であり、利子率の変化が大きければ、価格変化率は正に大きくなる。コンべクシティが大きい債券ほど、価格上昇の効果が大きいと期待でき。
3) 市場リスクValue at Risk(VaR)
(2)式に定義したように、債券価格Pは、債券の満期期間までの利息と償還元本の現在価値Pである。満期時点Tで、債券の価格変動ΔPは、ある水準-xを下回るという確率事象が確率αで生じるとき、債券の水準100(1-α)%の期間TのVaRと定義する。
Pr[ΔP≦-x]=α
満期時点tに依存して、割引利子率Rtは、市場で決まる。イールド・カーブは、満期期間を横軸に、割引利子率Rを縦軸にとって、描いた曲線である。実際は、満期期間は、離散的に決められるから、連続的なイールド・カーブは市場データからえられない。有限個の市場利子率データから、イールド・カーブを推測し、その変動モデルを作成する理論がある。
イールド・カーブ変動モデルから、デュレーション・コンべクシティを計算することができる。また、デュレーション・コンべクシティから、VaRを求めることができる。
4) 信用リスク(債務不履行リスク)
債券は、信用リスク(債務不履行リスク)があり、格付機関が、債券を格付けしている。銀行では、各貸付金に対して、その貸付金が債務不履行におちいった場合、損失を5段階に評価し、貸倒引当金を準備する。その貸付金評価モデルといえる。
信用リスクを計量するには、統計学の知識をもちい、倒産確率を推定する。倒産確率をもったまま、倒産確率過程のモデルを作成する。
債券の信用リスクは、無リスク資産である国債と事業債の利回り格差(イールド・スプレッド)は、信用リスクの期待収益を表しているとみる。イールド・スプレッドを推計するモデルが考えられてい。
本教室では、先物債券市場は、ヘッジ理論に従っている市場均衡論を説明している。①期間構造をいれた多期間モデルで、資産市場の一般均衡論の立場から、期間構造が決まる理論がある。さらに、オプション理論は、デルタ・ヘッジ戦略にしたがった裁定取引式が成立する。②短期債券市場と長期債券市場において、市場均衡すれば、期間構造論の主張する(1)式の裁定取引式が成立するのかを理論的に示す試みはある。③また、現実市場のデータから、期間構造論のイールド・カーブを推定する試みもある。④一般的には、期間構造論は離散期間であるが、オプション理論では、ブラック・ショールズ連続モデルが基本であり、瞬間的利子率をもちいる期間構造モデルがある。資産市場の一般均衡論の立場から、連続一般均衡モデルに拡張して、期間構造を示すことはできる。
①の離散時間で,一時的一般均衡理論から,現物・先物資産市場均衡を示すことは、私のモデルで、提案している。②については、オプションの連続モデルで、金利については、平均回帰する確率微分方程式をもちいて、期間構造を示すことは、各モデルがある。③は、それらのモデルに従い、イールド・カーブを推定している。④については、連続的一般均衡理論になるが、確率微分方程式による動学一般均衡理論は、開発中である。
本教室では、2期間のオプション理論を例示した。連続時間のオプションは、ブラック・ショールズ連続モデルを要約しただけである。理論的には、株式オプションは、期間構造がない資産である。債券は、期間構造をもつので、理論的には、複雑になる。①および②の債券の期間構造の決定理論は、多期間、連続時間のオプション理論を紹介し、それらを応用して示す予定である。
今週(2025年5月26日~5月30日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、19日から22日まで、ジュネーブで、WHOの総会が開かれました。パンデミック条約を採択されました。20日カナダで、22日まで、G7財務相・中央銀行総裁会議がありました。トランプ関税は議論されず、団結を強調しました。トランプ大統領は6月15日~17日G7サミットに参加、6月1日EUに50%の関税を課すことを表明しました。また、海外に製品工場を持つアップルに、米国回帰しなければ、25%関税をかけると脅し始めました。IBMの中国研究拠点は2024年閉鎖していますが、その製品、DELLの中国製品に30%かけるということなのか、不明です。
トランプ大統領は、関税交渉が膠着状態になり、国内の反トランプ研究拠点を資金ストップをはかり、閉鎖させる意向のようです。研究資金を断たれる研究者は、米国から脱出を図っています。日本は頭脳流出の時代もあった。米国の医療医薬、半導体、量子PC、AI、核融合等の先端研究者を獲得すべく、石破首相の1兆ドル米国投資すると首脳会談でトランプ氏に言っていたが、逆に、日本に研究投資1兆ドル投入し、米国からの頭脳流出の受け皿にする。EUも引き合いがあるので、トランプ・ビッグバーゲンをただどりする方針である。日本の貧弱な研究環境では、そのバーゲンに反応する政府系研究機関、企業研究機関はないが、1兆ドルをへたるブル(米牛)を飼うより、日本のブル(和牛)の方が育つと思う。不動産屋トランプが人を育てないのが見えていないソフト・バンクと中東3カ国のファンドは、3兆ドル米国投資するというが、アメリカの研究機関の将来はない、トランプ・ベアが、研究費は削減し、研究者を脅しまくっている状況では、話だけで合わせていた方が、損失しない。第1期トランプ政権で、ソフトバンク・中東ファンドの投資は失敗している。
今週のイベントは、27日ASEAN首脳会議が27日までクアラルンプールであります。29日経団連定時総会で筒井義信氏が新会長に就任します。30日アジア安全保障会議が6月1日までシンガポールであります。
経済統計は、次の発表がありました。
予測値 実現値
2025年5月19日 中4月小売売上高
6.0% 5.1%
4月鉱工業生産指数 5.8% 6.1%
米4月景気先行指数 -0.8% -1.0%
20日 日4月全国コンビニエンストア売上高 9762億1900万円
中5月最優遇貸出金利 3.00%
21日 日4月貿易統計 2200億円 -1158億円
22日 日3月機械受注統計
-2.2% 1302億600万円
4月全国スーパー売上高 1兆668億4608万円
米5月製造業購買担当者景気指数PMI 49.9 52.3
23日 日4月全国百貨店売上高 4232億円
4月全国消費者物価指数
3.5% 3.6%
経済統計は、次の発表があります。
予測値
2025年5月26日 日3月景気先行指数 107.7
一致指数 116
27日 米3月耐久財受注
-8.2%
29日 米3月実質GDP -0.3%
GDPデフレータ
3.7%
3月個人消費 1.8%
30日 日4月完全失業率
2.5%
4月有効求人倍率 1.26倍
5月東京都区部CPI 3.5%
4月鉱工業生産指数 0.2%
米4月個人所得 0.3%
4月個人支出 0.2%
4月PCEコアデフレータ
2.5%
31日 中5月製造業PMI 49.5
第9回目 2025年6月2日
4.5 株式の収益率と株式市場価格
4.6 株式オプション価格の二項過程モデル(離散確率過程)
4.7 Black-Scholes オプション価格の決定論(連続確率過程)
要点
・ 株式の収益率と株式市場価格
・ 株式オプション価格の二項過程モデル
4.5 株式の収益率と株式市場価格
各種の株式収益率を定義し、株式投資の指標としての役割をのべる。 企業の経営成績は損益計算書、企業の財政状態は貸借対照表で情報開示される。投資家は、これら財務諸表から、総資本事業利益率(ROA: Return On Asset)および自己資本利益率(ROE: Retun On Equity)投資判断の指標を導いている。ただし、会計期間が1年であり、四半期で仮計算される企業もある。国民経済計算と同様に、速報と確報がある。
財務指標と株価の関係
ROA
事業利益
ROE 資産
税引き後利益
EPS 自己資本 ×
税引き後利益 × 資産
株数 自己資本 自己資本
株価 × 株数 レバレッジ(てこ率)
株価 BPS
EPS
PER
株価
1株当たり純資産(BPS)
PBR
表において、上下の比率をかける(×)とその前の比率になる。株価=EPS×PER。
ROEおよびROAは、財務諸表の損益計算書と貸借対照表のデータによる比率である。PERとPBRはともに株価が分子であり、分母は1株当たり税引き後利益、1株当たり純資産をそれぞれあてる。株価は取引日ごとにデータが得られるが、分母は前期の損益計算書と貸借対照表のデータである。相場の変動により、営業日で変化するのはPERとPBRであり、これらは、株価の市場評価を表す比率として株式投資の参考指標に使われる。投資家は自己資本あるいは資産を期間内有効に使って、利益を上げる比率として、ROEおよびROAを意識するから、経営者が株主総会でそれらを経営目標として意識しているならば、決算でその結果を示す。
米国では、経営者は、利益至上主義であるから、ROEおよびROAは、株主に答える経営目標である。日本の経営者で利益至上主義は、前ゴーン日産社長やソフトバンク社長であるが、少数である。ゴーン氏はレバノン生まれ、孫氏は在日韓国人である。日本の企業も国際化し、外国人経営者も増えているが多くはない。ROEおよびROAの比率を経営目標として、意識する人はあまりいない。業界横並び的配当政策と、その控えめな配当に、見合った経営報酬を得ることで満足し、会社やっていますという社長は多い。
株式市場における投資理論は、株価と1株当たり税引き後利益または1株当たり純資産の比率を参考指標にするように、株価は、配当率EPSまたは純資産比率BPSに依存して決まると考える。株式市場の株価形成の決定的理論は、ほとんどないが、企業の投資理論は、今期以降の配当系列と実物資産の将来最適資本量を計算することによって、今期以降の投資計画が決まることを示す。株式市場の投資家は、次期以降の利益と投資計画を株価に織り込むことで、日々、株式市場において、株式を売買し、株式保有の最適資産選択を構成している。
債券オプションには、債券市場価格形成の一般均衡理論を織り込む理論があるが、株式市場価格形成の一般均衡理論は、理論化されていない。株価形成を説明する、主要な2つの要素、利益予想と純資産の最適量の評価が株価形成に影響する株価決定論がないためである。
4.6 株式オプション価格の二項過程モデル
Black-Scholes[1973,J.P.E.81,石村貞夫・石村園子『金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式』東京図書、部分訳第11章190
-199頁]の評価公式は、株式市場およびオプション市場に対して、 7条件を仮定している。
Black-Scholesの金融市場は効率的な完全競争市場である。しかし、オプション市場は、経済学の市場機構は設定されない。オプション理論は、「金融工学」の理論であるということが強調される。したがって、貸付市場および債券・株式市場の市場均衡価格は、オプション理論では、所与とされる。
オプションは、株式市場で、将来のある期日に、ある企業の株価が想定以下、また以上になると、投資家は、損失が出るので、その場合は、買いまたは売りが放棄できる契約がり、現時点で、放棄のオプションに対する権利を、ある価格で売買する。先物契約は、損失が出る場合も契約を履行しなければならない。
オプション商品があれば、先物契約よりは、投資家は、損失価値を放棄できる。契約の相手側は、逆に、損失価値を負担するから、権利放棄前払い金を高くしたい。双方にとって、合意できるオプション代金(価値)を決めたい。現物・先物市場は、市場参加者の売買の動機が経済学的な法則に従うが、オプション市場は、現物・先物市場取引を前提として、それらの価値を所与として、損切り契約ができるようにする。そのような虫の良い商品が、現物・先物市場で取引された商品をもとに、どのように、作成されるかが、オプション理論である。その中心戦略は、掛けつなぎ(Hedge)である。オプション市場参加者は、将来期日での、ある資産の権利行使価格を想定する。将来期日において、予想価格分布にしたがって、資産市場価格が実現するが、オプション取引参加者は、どのような資産価格が実現しても、そのオプション価値が変動しないことを期待する。
掛けつなぎの(ヘッジ)戦略は、どのような資産価格が実現しても、純資産価値=資産価値-負債価値が非負(純資産価値≧0)となるように、資産および負債を現時点で、構成する。純資産価値=0であれば、損も得もしない。
オプション商品は、損失を0にする契約であるから、ヘッジ戦略を取っているが、商品が1種類、オプションだけでは、反対側の商品がない。そこで、現時点で現物商品を購入させ、満期日契約商品(オプション)とで、ポートフォリオを組み、純資産価値≧0となるように、ヘッジする。すなわち、同一原資産である(現物・オプション)商品をポートフォリオに組むことで、ヘッジするのである。
Black-Scholesでは、
「原資産を株式とし,時点tにおける株価をx(t)とする.オプションの値をw(x,t)とする.オプションは,株式の買い建て1株とそのオプションの売り建てを同時に行うヘッジ・ポジションをとる.すなわち,時点tにおいて,x(t)×1-w(x,t)×オプション数=0となるように,オプション数Cを決めれば,任意の価格(x(t),w(x,t))で相殺される.」
とある。
前述の先物理論において、同時期の債券と株式で、自己清算条件、仮定4. 6(qb2,q k2)・(cb2, ck2)=0を投資家に付けていることは、同様なヘッジしているのである。価格変化で、将来賦存量の価値変動を、先物契約によって、2種類以上の商品で、1商品の売りに対し、他の商品の買いに「掛けつなぎ(満期到来の資産に、同時期の負債を対応させる。)」、変動をゼロにしている。
二項過程の1期間モデルにもどって、コール・オプション1単位の売りにその株式δ単位を購入するポートフォリオを考える。δをヘッジ比率という。二項分布で,S′T<K<STとする。投資家が、デルタ・ヘッジ戦略をとるならば、「満期時Tのポートフォリオ(1,δ)の価値は、いかなる資産価格(CT,ST)でも、同じであるから,(-CT, ST)(1,δ)=(0, S′T)(1,δ)とする方程式から、δ*=CT/(ST-S′T)。株式のヘッジ比率が決まる。ここで、満期時Tのコール・オプションの価値CT=Max[0,ST-K]および株式価格ST、Kは権利行使価格する。数値例では、確率0.5で、ST =120円とS′T =80円、権利行使価格はK =100円であり、二項分布の平均値は、0.5×120+0.5×80=100である。権利行使価格は平均値に設定されている。
さて、δ*は決まったが、現時点でのコール・オプションの価値Cは決まらない。そこで、現時点のポートフォリオの価値-C×1+S×δ*を資金市場において、利子率rで、満期Tまで運用すると、ポートフォリオの価値-CT×1+ST×δ*に等しくなるはずである。なぜなら、価値が等しくなければ、現時点での資産運用を投資額の低い方へ投資する裁定取引が働き、価値が等しくなるよう調整する。
将来収益が同じであるが、企業財務構成が異なる、2つの企業が、市場で異なる企業価値が成立すると、裁定取引によって、企業価値が同じになるように、市場で評価が調整され、同一の企業価値になるという説明をもちいる。
ゆえに、(1+r)(-C×1+S×δ*)=-CT×1+ST×δ*から、
C*=(CT×1-ST×δ*)/(1+r)+S×δ*
のように、コール・オプション価値C*が求められる。
テキストでは、
①俊野雅司・大村敬一『ゼミナール オプション 仕組みと実際』東洋経済新報社,1993年,pp. 94-68
②Sharp,W.F., Investment, 1978 (岩田暁一『先物とオプションの理論』東洋経済新報社,1989年,pp. 122-124)
③Cox, J.C., Ross, S.A.,Rubinstein,M. “OptionPricing: A Simplified Approach,”J.
F. E 7(1979)229-2631
による、二項過程モデルを紹介している。
①モデルのポートフォリオは、ヘッジド(hedged)・ポートフォリオ:「コール1単位の売りと株式x単位の買いを組み合せ」でポートフォリオを生成する。
デルタ・ヘッジ:満期時点で、どんな株価およびコール価格に対しても、ヘッジド・ポートフォリオの収益を同じにする。
②および③モデルは、コピー(replicate)・ポートフォリオ:コールの収益と、資産市場で他の商品と組み合わせたポートフォリオの収益が一致するポートフォリオが生成できれば、コールの収益のコピー(replicate)・ポートフォリオという。
テキストで示すように、①、②および③は、みな、デルタ・ヘッジしているから、コール・オプションおよびプット・オプションの価値公式が同値なのである。
オプションは、現物・先物市場をもとに、証券取引所・証券会社で、5つ以内の権利行使価格が提示され、以上のヘッジモデルから計算されたオプション価値で売買する仕組みである。通常の市場環境では、権利行使価格が先物市場価格の幅に入っており、満期時の確率分布は、個人の予想分布でなく、証券取引所・証券会社の決める対数正規分布である。いくらヘッジされた商品であっても、市場環境の激変では、契約の権利行使価格は、幅をはずれることがある。基本的には、収益を期待する商品ではないから、ヘッジか池での指摘されるように、ヘッジ幅から、著しくかい離すれば、ヘッジ機能を果たさない場合がある。経済学の立場から言えば、オプションは、先物市場に直接影響を与えるというより、先物市場から、派生した商品であると認識した方がよいだろう。
今年度の教室は、オプション理論の入門から、展開の成果を説明することを考えている。先物価格は、離散的確率過程と連続確率過程で動きを数学モデルでとらえる。入門の1期間二項確率過程をn期間に拡張し、オプション価格を決定する。テキストにあるBlack-Scholesは、連続確率過程であり、原論文の要約である。オプション理論は、株式の場合、連続確率過程を伊藤過程から変えることしか、Black-Scholes理論の展開は乏しい。株式価格決定・変動の経済学理論の発達がないことも影響している。
他方、債券は、債券が満期を持つので、債券先物価格または先物金利の期間構造論がある。債券価格の確率過程は、平均回帰性をもつマーチンゲールを仮定し、期間構造論を乗せることができる。債券は、満期まで保有すれば、定期的に利札が分配され、満期期間に償還されるから、オプションがない商品であり、オプションと商品構造が似ている。債券オプション理論は、金融論の期間構造理論をもとに、理論展開が、株式オプションよりは、広い。
今年度は、債券オプション理論の展開を説明することは、間に合わないが、先物価格の確率的動学理論とも関連するので、後期の『金融論』で、債券の期間構造論の確率動学化を説明する。
今週(2025年6月2日~6月6日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、26日ASEAN首脳会議が27日までクアラルンプールでありました。29日経団連定時総会で筒井義信氏が新会長に就任しました。30日アジア安全保障会議が6月1日までシンガポールでありました。トランプ大統領が演説会で、赤いMAGA帽子の横に、「47 49」を書いていた。47は『正しい道を歩んでいる』49は、『新たなサイクルの始まり』を表すそうです。前CIA長官は、SNSに「87 47」(排除 トランプ)を書いて、削除した。トランプ氏は気にしているのかな?日本語的には、「47 49」は「シナ(China)死苦」と読める。
今週のイベントは、3日韓国大統領選挙の投開票があります。5日欧州中央銀行理事会があります。6日ispaceが月面着陸予定です。
経済統計は、次の発表がありました。
予測値 実現値
2025年5月26日 日3月景気先行指数 107.7 108.1
一致指数 116 115.9
27日 米3月耐久財受注
-7.9% -6.3%
29日 米3月実質GDP -0.3% -0.2%
GDPデフレータ
3.7% 3.7%
3月個人消費 1.8% 1.2%
30日 日4月完全失業率
2.5% 2.5%
4月有効求人倍率 1.26倍 1.26倍
5月東京都区部CPI 3.5% 3.6%
4月鉱工業生産指数 0.2% 0.7%
米4月個人所得 0.3% 0.8%
4月個人支出 0.2% 0.2%
4月PCEコアデフレータ
2.5% 2.5%
経済統計は、次の発表があります。
予測値
2025年6月2日 米5月ISM製造業景気指数 49.2
3日 中5月財新製造業PMI 50.7
米4月耐久財受注(前月比) -6.3%
4日 米5月ISM非製造業景気指数 52
5日 日4月毎月勤労統計 2.6%
米4月貿易収支 -1173億ドル
6日 日4月全世帯家計調査 1.6%
日4月景気一致指数
4月景気先行指数
米5月失業率
第10回目 2025年6月9日
要点 5.最適資産選択理論
5.1 最適資産選択理論
1) 1安全資産と1危険資産
2) 2危険資産
3) 1安全資産と2危険資産
5.1 最適資産選択理論
・各資産を収益率で比較し、ポートフォリオ(資産の一覧表)を作成する。
・各期待収益率に対し、リスク(分散)を最小にするポートフォリオ(有効フロンティア)を作成する。
・投資家は資産の収益率の確率分布を選び、収益率の実現値に対して効用をもつ。
・投資家は、有効フロンティア上で、期待効用を最大にするポートフォリオを選択する。
今回は、証券投資の教科書で看板の一つである、資産選択理論あるいは平均・分散分析を、もっとも簡単な貨幣・債券の2種類の資産がある場合、債券・株式の2危険資産および貨幣・債券・株式の3資産の場合を説明する。
消費者は、給与、賞与を定期的にえると、ライフ・サイクル理論で、毎月、貯蓄額を決める。第6回目の練習問題1では,ある個人が第1期において得た100万円の所得を2期間にわたって全部支出する。個人の効用関数は、u =C1C2〔u:効用水準,Ci:第i期の支出額(i=1,2)〕で示され,個人の第1期における貯蓄には5%の利子がつくものとする。個人は、2期間の予算制約式C1+S1=900,000、C2=1.045S1のもとで、個人は効用最大化を図る。これが、ライフ・サイクル理論である。
ライフ・サイクル理論で決まった貯蓄額を他の資産に投資する際、将来価値変動しない特性のある貨幣と、確率的に価値変動する債券の分け方(割分)を決定する。これを資産選択理論という。
ライフ・サイクル理論は、予算制約式のもとで、消費者の効用関数を最大化する消費量を求めるが、資産選択理論は、「期待収益率に対して、ポートフォリオの分散を最小化する有効フロンティアのもとで、期待効用関数を最大にする最適な投資割分を選択する」。
ポートフォリオ(資産の一覧表)の作成
これまで、金融商品は、現預金、債券、株式の3資産の特性を数値で評価した。ここでは、現金(貨幣)、利付債、株式の3資産を取り上げる。1期間(月間、年間)の投資収益率を定義する。1年後の利息は確定しているが、1年後の配当、1年後の利付債単位価格および1年後の株式1株価格は予想値である。
貨幣の投資収益率m =1年後の現金1円-現在の1円 = 0
現在の1円
利付債投資収益率b =1年後の利息+(1年後の利付債単位価格-現在の利付債単位価格)
現在の利付債単位価格
株式の投資収益率s=1年後の1株当りの配当+(1年後の株式価格-現在の株式価格)
現在の株式価格
1) 1安全資産・1危険資産モデル
投資家は、貨幣と債券の2種類のポートフォリオを選択する。以下は、ポートフォリオの収益率Rを定義し、その期待値(平均値)μRと分散σR2(標準偏差σR)を求める。貨幣の収益率は0であり、利付債の利息(クーポン)率をr=利息/現在の債券価格、capital gain or loss率G=(1年後の利付債単位価格-現在の利付債単位価格)/現在の利付債単位価格とする。貨幣と債券の2種類のポートフォリオ(2資産の一覧表)の場合、予想値があるのは債券価格のみであり、それが含まれる値上がりまたは値下がり率Gは、確率変数とする。確率変数Gの性質は、期待値(平均値) μgおよび分散σg2(標準偏差σg)で表される。μg=0およびσgは一定である。
貨幣と債券のポートフォリオの収益率をRとする。2資産に投資した割合を、それぞれ、A1、A2≧0とする。A1+A2=1である。ポートフォリオ収益率R=A1×0+A2×(r+G)=A2×(r+G)の期待値と分散を計算する。
期待値μR=E[R]=E[A2×(r+G)]=A2 E[r+G]=A2 {E[r]+E[G]}
=A2 {r+0}=A2 r (1)
分散 σR2=E[R-E[R]]2=E[A2×(r+G)-A2 r]2=E[A2G]2
=A22 E[G]2 =A22σg2 (2)
以上の計算は期待値Eの公式を使っている。
定数rのとき、E[r]=r。
E[r+G]=E[r]+E[G]。
E[A2×(r+G)]=A2 E[r+G]。
有効フロンティアの作成
有効フロンティアとは、各期待収益率μRに対し、リスク(分散σR2)を最小にする債券の割合A2を求める。
(1)からA2=μR/ rであり、(2)式に代入すると、σR2=A22σg2=(σg2/ r2) μR2である。投資家がポートフォリオから、期待する期待収益率μRを決めると、割分A2=μR/ rが決まり、そのときの分散は(σg2/ r2) μR2となる。
テキスト図5.4の期待収益率と標準偏差の平面上に、描くと、直線μR=(r/σg) σRとなる。この直線の右側では、各期待収益率μRに対する標準偏差σRがより大きいことが見て取れる。この直線上がリスク(分散σR2)を最小にする債券の割合A2が描く直線であり、有効フロンティアという。
投資家の期待効用
投資家が、有効フロンティアのどの期待収益率を選ぶかは、von Neumann-Morgensternの「期待効用最大化の仮説」にしたがう。
期待効用最大化の仮説
「各投資家は、期待収益率の実現値R=rに対して、効用関数U(R)をもち、効用関数の期待値E[U(R)]が最大となる確率分布を選ぶ」
投資家の分類
投資家は、効用関数U(R)によって、主に、3つのタイプに分類される。すなわち、危険回避者、危険中立者、危険愛好者である。テキストpp. 74-75に、それぞれの効用関数を特定化し、その期待効用を計算している。危険中立者はリスクに無関心であるので、効用関数の期待値を取るとリスクの指標である分散が入らない。他の2者は、分散が入っている。
図5.3に示しているように、危険回避者、危険愛好者はともに円の方程式であり、危険回避者は北西方向に同心円が行くにつれて、期待効用が高くなる。危険愛好者は北東方向である。危険中立者は、水平線となり、上に行くほど期待効用が高い。
経済学では、危険回避者を想定することが多い。危険愛好者は、投機者である。分散あるいは標準偏差を経済行動の最適化にもちいるのが、資産選択理論である。
有効フロンティアのもとで、期待効用最大化
投資家は、有効フロンティアμR=(r/σg) σRのもとで、期待効用関数を最大にする最適な投資割分A2=2r/(r2+σg2)を選択する。この計算は、テキストp75にある.図5.3に示しているように、危険回避者の場合、北西方向の円と有効フロンティアの接点を求めればよい。
危険愛好者の場合は、点(r, σg)が利付債にすべて投資する場合であるから、この点を選択する。危険中立者は、
E[U(R)]=E[R]=μR=A2 r
であるから、μR= r、A2 =1のとき、期待効用は最大になる。ゆえに、危険愛好者と同じく、利付債にすべて投資する。
2) 2危険資産モデル
・2危険資産の有効フロンティアを求める。
・有効フロンティア上で、期待効用を最大にするポートフォリオを求める。2危険資産を仮定し、株式の収益率をS、債券の収益率をBとする。収益率R=A1S +(1-A1)B と定義する。収益率の分散σR2 は、
σR2=E[R-E [R]]=(σS2+σB2-2 ρSB σSσB )A12+
2 (ρSB σSσB -σB2)A1+σB2
=(σS2+σB2-2 ρSB σSσB ){A1+(ρSB σSσB -σB2)/Δ}2
+σB2-(ρSB σSσB -σB2)2/Δ (8)
と表わされる。ここで、Δ=σS2+σB2-2ρSBσSσBである。この分散は、A1の値を変化させることにより、最小値σR2 *が求まる。
σR2*= σS2σB2 (1- ρSB2)
Δ
また、そのときのA1の値は、A1*=(σB2 -ρSB σSσB )/Δである。最小値σR2 *のときの平均値μR*は、μR*=μB+A1*(μS-μB)で表されるから、 (8)式は、双曲線の方程式に変形する。
σR2=Δ{A1-A1*}2+σR2*=Δ(μR-μR*)2/(μS-μB)2+σR2*。
(μR-μR*)2=(σR2 -σR2*)(μS-μB)2 (9)
Δ
となる。双曲線の形(金融数学2)に、(9)式を変形すると、次の式になる。
σR2 -
(μR-μR*)2 =
1 。
σR2* σR2*(μS-μB)2 /Δ
最適ポートフォリオを求める図解
横軸にリスクを表す、標準偏差σRをとり、縦軸に期待収益率μRをとる。図5. 5のように、有効フロンティア(9)は、双曲線である。危険回避者の期待効用曲線は,(4)式より、中心(0,2)の同心円である。有効フロンティアと期待効用の無差別曲線は、点(σR**,μR**)において接する。この点が、最適なポートフォリオである。接点の求め方は、(9)式を全微分して、双曲線上の接線の傾きを求め、(7)式の傾きと一致させて、σRを消去する。
解答 (9)式を全微分する。
2(μR-μR*)dμR=2σR (μS-μB)2 dσR
Δ
dμR= σR (μS-μB)2
dσR (μR-μR*)Δ 。
(7)式の傾きは、
dμR= - σR
dσR μR-2 。
ゆえに、σR (μS-μB)2 = - σR
(μR-μR*)Δ μR-2 。
(μR-2)(μS-μB)2=-(μR-μR*)Δ
{(μS-μB)2+Δ}μR= 2(μS-μB)2+μR*Δ
μR**= {2(μS-μB)2+μR*Δ}/{(μS-μB)2+Δ}。
(9)式にμR**を代入する。
(μR**-μR*)2=(σR2 -σR2*)(μS-μB)2
Δ
σR2=(μR**-μR*)2Δ+σR2*(μS-μB)2
σR**=√{(μR**-μR*)2Δ+σR2*(μS-μB)2}。
収益率R=A1S+(1-A1)Bであるから、μR**=A1μS+(1-A1)μBより、
A1**=(μR**-μB)/(μS-μB)が最適ポートフォリオである。
3) 1安全資産・2危険資産モデル
・2危険資産の有効フロンティアを求める。
・3資産の場合、安全資産があれば、分離定理が成立し、 (貨幣、債券)モデルと同様に、有効フロンティアを直線にできる。
貨幣、債券、株式の3種類のポートフォリオを投資家が選択する。以下は、ポートフォリオの収益率Rを定義し、その期待値(平均値)μRと分散σR2(標準偏差σR)を求める。利付債の収益率BをB=r +Gbとする。新たに、株式を追加する。Dは株式配当率、株式のcapital gain or loss率Gsとし、ともに、確率変数である。株式収益率をS=D+Gsとする。利付債収益率Bは、期待値μB、分散σB2であり、株式収益率をSは、期待値μS、分散σS2である。共分散はσSB=ρSBσSσBである。計算の簡単化のため、2つの確率変数の相関係数ρSBは、統計的独立性を仮定するので、ρSB=0である。(テキストでは、ρSB≠0である。)
2危険資産の有効フロンティア
株式と債券のポートフォリオの収益率をRとする。2資産に投資した割合を、それぞれ、A1、A2≧0とする。A1+A2=1である。ポートフォリオ収益率R=A1×S+A2×Bの期待値と分散を計算する。σSB=ρSBσSσB =0を使うと簡単になる。
期待値:μR=E[R]=A1 E[B]+(1-A1)E[B]=A1μS+(1-A1)μB
分散: σR2=E[R-E[R]]2=E[A1S+A2B -(A1μS+(1-A1)μB)]2
=E[A1(S-μS) +(1-A1) (B-μB)]2
=A12σS2+2 A1(1-A1) σSB+(1-A1) 2σB2
=(σS2+σB2)A12 -2σB 2A1+σB2
有効フロンティアの作成
有効フロンティアは、各期待収益率μRに対し、リスク(分散σR2)を最小にする債券の割合A1を求める。
分散:σR2=(σS2+σB2)A12 -2σB 2A1+σB2の最小値は、完全平方化して、
σR2=(σS2+σB2){A1-σB2/(σS2+σB2)}2+σS2σB2/(σS2+σB2) 4.16
となる。
A1*=σB2/(σS2+σB2)のとき、分散の最小値σR2*=σS2σB2/(σS2+σB2)をとる。そのときの平均値は、
μR*=A1*μS+(1-A1*)μB=μB+A1*(μS-μB)である。
4.16式は、(μR*,σR2*)を使って、変形するならば、双曲線の方程式になる。点Bと点Sを通る曲線が有効フロンティアになる。すなわち、
σR2=(σS2+σB2)(A1-A1*)2+σR2* (1)
μR-μR*=A1μS+(1-A1)μB -{A1*μS+(1-A1*)μB}=(A1-A1*)(μS-μB)より
A1-A1*=(μR-μR*)/(μS-μB)
(1)式に代入し、整理すると
σR2 - (μR-μR*) 2 = 1
σR2*(σS2+σB2) σR2*(μS-μB) 2
この曲線は、図5. 5に描いている。危険回避者の最適ポートフォリオは、円の期待効用曲線との接点になる。テキストでは、数値例で、双曲線の方程式を求めている。
次に、投資家が貨幣、債券、株式の3種類のポートフォリオを選択する場合を考える。3資産の場合、安全資産があれば、安全資産と危険資産の分離定理が成立し、2資産モデルと同様に、有効フロンティアを直線にできる。
貨幣、株式と債券のポートフォリオの収益率をRとする。3資産に投資した割合を、それぞれ、A1、A2、A3≧0とする。A1+A2+A3=1である。貨幣を安全資産とすると、危険資産である債券と株式の最小分散は、貨幣の保有割合に影響されないという「安全資産と危険資産の分離定理」が成立する。
テキストにしたがうと、貨幣、債券、株式の3種類のポートフォリオの収益率RはR=A2S+A3B=(1-A1){αS+(1-α)B}、ここで、α=A2/(A1+A2)とおく。その平均と分散は
μR=(1-A1){αμS +(1-α) μB}、
σR2=(1-A1) 2 E[Rα(S-μS )+(1-α)(B-μB)]2
=(1-A1) 2{(σS2+σB2) α2-2σB 2α+σB2}
A1とαが変数分離されているため、分散を最小化するとき、危険資産間の割合αを決定し、危険資産だけの有効ポートフォリオの軌跡が描ける。
次に、危険資産有効ポートフォリオ上の点Aをとるとき、原点と点Aを通る直線0Aが有効フロンティアになる。
μA=αμS +(1-α) μB、σA2=(σS2+σB2) α2-2σB 2α+σB2とおく。μR=(1-A1) μA、σR2=(1-A1) 2σA2より、原点と点Aを通る直線は、μR=(μA/σA)σR と表せる。
危険資産有効ポートフォリオ双曲線と点Aを通る直線0Aは、2点で交点をもつが、直線の傾きが上がるにつれ、2点は直線と双曲線の接点Mに達する。接点Mにおいて、αは一意に決まり、A1も一意に決まる。投資家は、直線0M上で、期待効用曲線と接する点を最適ポートフォリオとする。テキストpp.81-82に計算している。
グラフの点座標(σR,μR)で、第一座標は、横軸で、標準偏差、第二座標は、縦軸で、期待収益率を表す。合成資産Mは、
点(σRM,γ*/σRM)である。
ここで、γ*=√{(ΔμR*)2+ΔσR2*(μS-μB)2}/ΔσR2* 。
σRM=Δγ*μR*/{Δγ*2-(μS-μB)2}。
A1*=σB2/(σS2+σB2)を代入して、
μR*=A1*μS+(1-A1*)μB=μB+A1*(μS-μB)
=μB+ (μS-μB) σB2/(σS2+σB2)。
σR2*=σS2σB2/(σS2+σB2)。
線分0M上に、危険回避者が期待効用の無差別曲線との接点で、最適ポートフォリオが決まる。危険愛好者および危険中立者は、点Mが最適ポートフォリオである。
5. 2節に、以上の3資産モデルを実践する場合を示している。銀行・証券会社が、投資家のリスク性向を判定する場合も、応用できる。
最適資産選択理論を投資実践に応用する方法は、期待効用関数を仮定することがむつかしい。図5.3の3つの期待効用曲線をみると、3資産の有効フロンティアは、線分0Mである。危険回避者は、線分と円との接点を選ぶ。危険中立者、危険愛好者は、M点を選ぶ。したがって、危険回避者は、線分0Mの内分点を選択することになる。
線分0Mを、機械的に、五等分する。危険回避者の投資家の均衡点Eを、機械的に、5リスク・ランクとして、投資家は、標準偏差のランクから、自分の望ましい分点を選択する。選んだ最適資産選択比率(A1´ *,A2 ´ *,A3´*)にしたがって、投資家は、手持ち投資資金から、貨幣、債券、株式を市場価格で購入する。
5章のまとめ
資産選択理論は、経営学部、商学部において、証券論の一部に、必ず、その章がある。経済学部の金融論では、ミクロ経済理論から、消費者の貯蓄を資産配分する場合、資産選択理論で説明する。他方、金融論は、金融政策の有効性を問題にすることが多く、日本銀行が政策判断をする経済モデルは、マクロ計量経済モデルが主流である。マクロ経済モデルで、貨幣以外の資産を取り込んだ理論には、Tobinの資産市場一般均衡論(J.Tobin, “A
General Equilibrium Approach to Monetary Theory,” Journal of Monetary, Credit,
and Banking, Vol. 1, No. 1, 1969, pp. 15-29)、Sargentのマクロ経済モデル(T.J.Sargent, Macroeconomic Theory Second
Edition, 1989, ChⅠ, pp.7-49)がある。私は、ふたりのマクロモデルを合体した、金融システムのある開放マクロ貨幣経済モデル(追手門学院大学追手門経済・経営研究第18号2011年3月)を構成し、均衡方程式を導いている。このモデルでは、国内3資産、海外3資産市場を明示化している。
従来のマクロ金融理論では、IS=LM・AS=AD分析が教科書になっている。この程度のマクロ理論の認識で、資産は貨幣のみで、中央銀行は貨幣供給を増加させる拡張政策手段と、公定歩合を引き上げる緊縮政策手段を使って、最終政策目標は、景気局面において、GDP成長率、失業率、物価上昇率、為替レートのいずれかの目標数値を取ることが、アナウンスメント効果になっているだけで、目標を達成するマクロ理論的根拠はない。
2019年から、私の金融論教室では、IS=LM・AS=AD分析を開放マクロモデルに拡張したマンデル=フレミングモデルに、債券市場および為替市場を陽表化したMFEXモデルを示している。本教室の6. 5に、不完全雇用モデルを示し、図解している。中央銀行が最終目標を金融緩和におき、貨幣供給量を増加させれば、市場均衡式がシフトし、新均衡がえられることが理解でき、計算可能である。
マクロ貨幣経済モデルに、リスク(分散)を考慮する資産選択理論を導入する試みは、意外にない。貨幣市場に、予想物価を導入した理論はない。貸付資金、債券・株式市場のマクロモデルはない。この方向は、現在、SNAまたは資金循環表にもとづく、制度部門別主体がリスクを考慮する資産市場均衡モデルを研究している。つまり、IS=LM・AS=AD分析では、経済主体は、国民と政策主体の政府・中央銀行であり、資産は貨幣のみ陽表化されている。そこで、国民を制度部門に分割し、ストック資産市場を国内多資産、海外多資産市場市場で開放モデルに構成し、資産均衡を求める。この方向は、産業連関表分析に対応する金融連関表を作成することになる。
この立場に立つと、国民と政策主体の政府・中央銀行のマクロ理論は、制度部門別のミクロ理論で説明することになる。つまり、ミクロ一般均衡理論で、制度部門別のフロー・ストック市場均衡の存在が証明されれば、マクロ理論は存在しない。このモデルを、動学モデルにすることができれば、この経済で、政策主体がその政策手段をもちいて、政策目標を達成できるかどうか、計算できることになる。
さて、国民と政策主体の政府・中央銀行のマクロ理論で価格予想を導入するのは、外生的で困難であった。予想形成は、統計学的な予想形成を借用することが多かった。ミクロ一般均衡理論においても、平均分散の最適化をした消費者が、資産市場において、最適比率にもとづいて、資産を交換するミクロの一般均衡の存在は定式化されてこなかった。これは、私の『多期間一般均衡モデルの確率的動学』晃洋書房、2018年3月、第11章で、示している。すなわち、投資家が最適平均分散投資比率を決めたら、その比率で、資産の売買の個別需要関数を求めることができる。その応用が、今回のリスク・ランクの計算である。
債券市場に、中央銀行が政府の委託を受け、新規国債供給をし、満期国債を償還する働きや、貨幣供給量または公定歩合の政策手段で、予想物価に作用し、現物・先物金融市場に関与することを定式化し、現先資産市場の均衡の存在を示すモデルになる。
今週(2025年6月9日~6月13日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、3日韓国大統領選挙の投開票がありました。李在明氏が当選しました。5日欧州中央銀行理事会がありました。6日ispaceが月面着陸に失敗しました。
今週のイベントは、13日東京都議会議員選挙が告示されます。
経済統計は、次の発表がありました。
予測値 実現値
2025年6月2日 米5月ISM製造業景気指数 49.2 48.5
3日 中5月財新製造業PMI 50.7 48.3
米4月耐久財受注(前月比) -6.3% -6.3%
4日 米5月ISM非製造業景気指数 52 49.9
5日 日4月毎月勤労統計 2.6% 2.3%
米4月貿易収支 -640億ドル -616億ドル
6日 日4月全世帯家計調査 1.6% -0.1%
日4月景気一致指数 115.4 115.5
4月景気先行指数 104 103.4
米5月失業率 4.2% 4.2%
経済統計は、次の発表があります。
予測値
9日 日1~3月期実質GDP -0.7%
GDPデフレータ 3.3%
5月景気ウォッチャー調査 44.0
4月国際収支 -1400億円
中5月消費者物価指数 -0.2%
5月貿易統計
10日 日5月工作機械受注額
11日 米5月消費者物価指数 2.5%
13日 日4月鉱工業生産 0.7%
第11回目 2024年6月16日
要点 5.2 最適資産選択にもとづく資産購入への応用
5.3 CAPM理論(Capital Asset Pricing Model)
5.2 最適資産選択にもとづく資産購入への応用
期待効用は各自の効用関数で決まる.債券投資信託を1種,株式投資信託,バランス投資信託を選ぶ.合成資産Mを計算する.図4.13において,期待収益率の縦軸0μMを5等分し,機械的に効用関数の接点を5点作る.そのうち,収益率を運用・管理会社の手数料以上(例えば0.02)にする.各自のリスクの許容度に応じて,残りの収益率から,貨幣と合成資産Mの割合A2,A3,A4,A5を選択する.
リスク・ランクにしたがって,資金を配分する.資産選択論の立場から,危険愛好者は許容度5,点Mである.危険中立者は許容度3とする.危険回避者は,2から3になる.
市場で売買する
市場で,購入する場合は,貨幣と合成資産Mの割合A2,A3,A4,A5では購入できない. A2=2/5の割合を選択する場合,2/5は債券,3/5はバランスと株式の合成資産Mである.さらに,Mの配分割合を計算する.3/5をその割合に分ける.
予算は,拠出額であるから,W=1万円であれば,債券投資信託,バランス投資信託,株式投資信託の3種類,現在の基準価格をP1,P2,P3とする.それぞれの購入量(口数)をb1,b2,sとする.
配分割合は,定義により,A2=(P1×b1)/W, A3=(P2×b2)/W, A4=(P3×s)/Wの関係があるから,3種類の投資信託は,
A2=2/5,A3=(3/5)(2/3)=2/5,A4=(3/5)(1/3)=1/5にそれぞれ配分する.
(2/5)10,000=P1×b1,(2/5)10,000=P2×b2,(1/5)10,000=P3×sが成立する.
b1=(2/5)10,000/P1,b2=(2/5)10,000/P2,s=(1/5)10,000/P3
5.3 CAPM理論(Capital Asset Pricing Model)
W.F.Sharpeは,個別資産の収益率を市場収益率で説明する資本資産評価モデル(Capital
Asset Pricing Model)を提案した[W.F.Sharpe,
Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk,
Journal of Finance, Sept. 1964, No. 3].市場収益率は,日経平均やTOPIXなどの指標の収益率である.(CAPMはキャップエムと発音する.)岩田暁一『先物とオプションの理論』東洋経済新報社,1989年,pp. 37-41に,その要約がある.
日本証券アナリスト協会から、出版されている、津村英文、榊原茂樹、青山護『証券投資論[第2版]』Ⅳ資本市場理論、日本経済新聞社、1991年、榊原茂樹、青山護、麻の幸弘『証券投資論[第3版]』第4章資本市場論、日本経済新聞社、1991年、小林孝雄、芹田」敏夫『新・証券投資論[Ⅰ]理論編』第3章CAPM、第4章マルチファクター・モデルとAPT、日本経済新聞出版社、2009年のうち、CAPMの結果のみを以下に要約している。
シャープ=リントナー・モデルと呼ばれる資本資産評価モデル(Capital
Asset Pricing Model)は、資本市場に次の仮定をおく。
仮定1
すべての投資家は、危険回避者であり、期末の富の期待効用を最大化する。投資家は、期末の富または投資収益率の平均と標準偏差にもとづいて、最適ポートフリオを選択する。
仮定2 資本市場では、
(ⅰ)すべての投資家はプライステーカーとして行動する。
(ⅱ)すべての証券は分割可能であり、完全な流動性をもつ。
(ⅲ)取引コストおよび税金はない。
仮定3
証券の空売りはできる。
仮定4
すべての証券の賦存量は期首で所与である。
仮定5
すべての投資家は将来の投資収益率の平均、標準偏差、共分散の予想は同質予想をもつ。
仮定6
すべての投資家は、同一の利子率で、制限なく貸借できる。
これらの諸仮定は、本テキスト4. 6節にあるオプション理論の仮定と共通の仮定が多い。この証券市場では、新規の証券発行がない、証券の投資家同士の、証券「交換市場」である。経済学では、この種の一般均衡モデルは、リスクや予想がない場合、数理経済学者によって、一般均衡の存在が証明されている。交換市場の場合は、二階堂副包(H. Nikaido、On the
Classical Multilateral Exchange Problem, Metroeconomica 8, No. 2(1956): A
Supplememtary Note to [8, No. 2(1956)] Metroeconomica 9, No. 2(1957)がある。
数理経済学の一般均衡理論は、不確実性下の危険資産市場均衡論に発展させられていなかった。資本資産評価モデル(Capital Asset Pricing Model)は、米国学者が常にやるように、理論的均衡は求められないが、資産価格形成を実用的な技術、計量経済分析技術と結び付ける工夫をした。実際、平均分散の3資産最適化であれば、仮定1のすべての投資家である危険回避者はOMの内分点が最適解であり、M点は、危険中立者と危険愛好者の最適解であるから、M点を市場均衡点にすることはできない。
現在は、一般均衡理論は、不確実性下の危険資産市場均衡論を取り扱える。しかし、仮定2のすべての投資家は、プライステーカーであるから、最適ポートフォリオをもつ危険回避者は、最適割合を5.2節最適資産選択にもとづく資産購入への応用のように、市場価格に変換しなければならない。
CAPMは、市場価格で計量分析判定すると、否定されている。そのため、計量経済学の多変数回帰分析等を使用する、「資本資産の価格形成の裁定理論」(Arbitrage Theory of Capital
Asset Pricing Theory for Risky Asset)が1977年、Stephen Rossによって発表された。
CAPMの有用性と、APTの実用性を論じるべきなのか、不確実性下の危険資産市場均衡論を取り扱えると考える立場から、本年度は、比較考察はせず、本テキストの結果を掲載している。日本証券アナリスト協会の立場から、少なくとも、理論的に整合性を欠くが、発見的な実用性は失われないのかもしれない。
安全資産がある場合,前節の3)の場合のように有効フロンティアが市場で計算される.安全資産の収益率(リスクフリー・レート)rfと有効フロンティアの接点M(σM,μM)を市場ポートフォリオという.点Mでは,市場の資産の需要と供給が一致している.この2つの点を結んだ直線を資本市場線(CML:Capital Market Line)という.資本市場線上のポートフォリオを点P=(σP,μP)とする.すべての投資家が危険回避者であれば,資本市場線上の点を選択する.
資本市場線の傾き μM - rf をリスクの市場価格という.標準偏差をリスクとすれば,
σM
リスク1単位あたりの超過収益率(プレミアム)を表す.
個別資産Aの収益率を市場収益率で説明する資本資産評価モデル(Capital Asset Pricing Model)にもどる.資産Aと市場ポートフォリオMとのポートフォリオPを考える.その収益率をR=A1A +(1-A1)M と定義する.収益率の分散σR2 は,4.4, 2)の(3)式から
σR2=E[R-E [R]]2=(σA2+σM2-2 ρAM σAσM )A12+ 2 (ρAM σAσM -σM2)A1+σM2
と表せ,点Mにおける,ポートフォリオPの接線の傾きは
dμ =dμ d A1 = (μA-μM)・ σM = μA-μM
dσ d A1
dσ σAM-σM2 ρAMσA-σM
と計算できる.これは,資本市場線の傾きに等しいから,
μA-μM = μM - rf
ρAMσA-σM σM
μA-μM = ρAMσA -σM (μM - rf)
σM
μA-μM =ρAMσA (μM - rf)-(μM - rf)
σM
μA-rf=ρAMσA (μM - rf)= σAM(μM - rf).
σM σM2
この式は資本資産評価モデルといわれる.
βA= σAM を資産Aのベータという.
σM2
リスクβと期待収益率μとの関係を図5.8に表している.直線μA-rf = βA(μM - rf)を証券市場線(Security Market Line)という.
市場でCAPMが成り立つ場合,証券市場線は個別証券の割安,割高を評価する規準となる.証券市場線は市場均衡線を表すから,資産Aの期待収益率と均衡期待収益率差をジャンセンのαという.図5. 9において,資産Aは,α>0であるから,過小評価されており,「買い」である.
今週(2025年6月16日~6月20日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、13日東京都議会議員選挙が告示されました。13日未明イスラエルがイランの核施設を空爆、軍首脳・核開発科学者を殺害しました。13日夜イランは弾道ミサイルで、テルアビブ等を攻撃しました。14日イスラエルはイラン南部ブシェール石油ガス施設を無人機で攻撃しました。
今週のイベントは、15日主要7カ国首脳会議が17日までカナダ西部アルバータ州で開かれます。16日日銀政策委・金融政策決定会合が17日まで開かれます。17日米連邦公開市場委員会が18日まで開かれます。18日ロシア・サンクトペテルブルク国際経済フォーラムが21日まであります。20日国債市場特別参加者会合が財務省であります。2025年に入って、超長期債の利回りが1%以上上昇しているためか、30年債・40年債の超長期債発行計画を見直すと観測されています。
経済統計は、次の発表がありました。
予測値 実現値
9日 日1~3月期実質GDP -0.7% -0.2%
GDPデフレータ 3.3% 3.3%
5月景気ウォッチャー調査 44.0 44.4
4月国際収支 -1400億円 -328億円
中5月消費者物価指数 -0.2% -0.1%
5月貿易統計
7500億元
10日 日5月工作機械受注額
1287億1600万円
11日 米5月消費者物価指数 2.5% 2.4%
13日 日4月鉱工業生産 0.7% 0.5%
経済統計は、次の発表があります。
予測値
6月16日 中5月小売売上高 5%
5月鉱工業生産指数 6%
17日 日政策金利 0.5%
米5月小売売上高 -0.7%
5月鉱工業生産指数 0.1%
18日 米政策金利 4.5%
5月景気先行指数 -0.1%
日5月CPI 3.5%
第12回目 2025年6月23日
要点 6.資産形成計画と運用・管理
6. 1 イベント分析の枠組み
・イベント分析表
・世代開始年齢と所得
・制度金融の利用
6.2 イベントに基づく資産形成計画
1) 世帯のイベント表の作成
2) 各世代のイベント表の特徴
① 若年世代23歳~32歳の金融行動
② 壮年世代33歳~65歳の金融行動
③ 老年世代66歳~85歳の金融行動
6.資産形成計画と運用・管理
これまで、第2章制度金融、第3章金融市場と金融商品の特性、評価方法を学んだ。
第4章では、家計のライフ・サイクル理論にもとづく、消費・貯蓄、消費・借入決定を問題として、2期間モデルで、解答を得た。物価と貨幣が入る、貨幣一般均衡理論で、価格の予想を入れた場合、現物市場と先物市場の主体的均衡を求めた。貨幣、債券、株式の3資産市場において、現物と先物の最適問題を解いて、市場均衡条件を求めた。さらに、多期間債券の期間構造の問題と、株式オプション価格の決定を先物価格2項過程で求めた。先物価格連続確率過程のもとで、Black-Scholesオプション価格の決定論を要約した。
第5章では、最適資産選択理論にもとづき、1)貨幣と債券、2)債券と株式、3)貨幣、債券と株式の資産に、投資家の富を、それぞれ、案分した割合で投資するとき、総合収益率の平均と分散が計算され、分散が最小になる案分割合を求めた。所与の市場価格で、各資産に、最小分散の割合にしたがい、投資する額が、簡単な変換式で求められる。
第6章では、第2章から第5章までの知識を応用して、家計のライフ・サイクル理論にもとづき、具体的に、計画を立て、資産を売買し、管理する方法を学ぶ。
6.1 イベント分析の枠組み
家計のライフ・サイクル理論にしたがうと、家計は、世帯主の現年齢から、終生まで、生涯消費・貯蓄計画および資産形成計画を立てる。この分野で、相談に応じる専門家は、FP技能士である。生涯計画の展望は、重要な節目のイベント表を作成し、その表に、経済計算を推測し、表を完成すると、各年齢で、所得を稼ぎ、節目のイベントを成功させることになる。日本では、中間所得階層が多く、少額であるが、様々な生涯イベントに対して、貯蓄し、資産形成できる。政府は、個人の少額つみたて資産形成に対して、収益・利息に課税せず、追加投資できる少額つみたて非課税制度を各種つくっている。
このような家計の資産形成計画主義は、経済学が普及した世界各国の家計において、経済学史的、普遍的に、普及は、全くしていない。大多数の開発途上国では、中間所得層が薄く、生活困窮者の子沢山と昔から言われるように、子供は働き手であり、家計の所得を増やすことができる。大金持ちの子沢山は、それと同様に、資産が多すぎて、一族に資産分配を図っているのである。
開発途上国では、国の方針を決定する国家機構が、国内外で不安定であり、内紛、内戦、対外戦争に対応するために、国の生産・所得・支出の重要部分を、国防・治安予算に、つぎ込まざるを得ず、国民の大多数は、生活困窮者であり、しかも、子沢山である。一部の資産家に富が集中している。そのような国においては、家計の労働・所得が、毎月不安定である。国内金融機構は、国外の支援国・国際金融機構の支援に依存しており、国民の大多数の生活困窮者は、個人の資産形成は不可能である。高・中所得国では、ほぼ、国内外で、制度的に安定して、中所得者層も多く、個人の生涯人生計画が立てられる。
日本銀行の金融政策:10年間、政策金利セロ金利くぎ付け、通貨供給量を裁量する弊害
国家権力を担う政党・政治組織が選出される過程は、いろいろあるが、日本は民主主義によって選出されている。自民・公明連立政権は、10年近く、政権を担っている。デフレ脱却、インフレ化、所得上昇で、失われた30年から、経済成長軌道に、復帰するはずだった。東京オリンピック延期開催あたりから、腰折れし、金融緩和のまま、恥ずかしながら、ウクライナ戦争による世界インフレさえ、世界中央銀行のゼロ金利政策から、政策金利の政策手段を復活できず、経済・金融はへたってしまった。FRBと日銀の政策金利差が拡大し、資金流出し、110円から、145円へ超円安に移行した。輸出産業は、莫大な利益を上げるはずが、自動車関連半導体不足、検査不正も発覚、生産中止を余儀なくされた。他の輸出産業も同様で、輸出はふるわない。人件費の安い中国を始め、逆輸入型のサプライチェーンは、超円安で、輸入インフレに陥り、さらに、ウクライナ戦争の原油・LNGインフレで、貿易赤字となり、世界金利差と慢性的貿易赤字で、ダブルの円安要因は逆転しようがない。2025年6月23日でも、145円/ドルである。金利差はFRB4.5%日銀0.5%で、4%差がある。2024年9月から、農業政策の米の生産調整失敗で、市場でコメ不足の投機が発生し、米価が2倍に上昇、米価超インフレが、国内インフレに波及、CPIは3%を毎月超えているが、日本銀行は、その間、政策金利手段は行使せず、0.5%で固定している。
このまま、超円安が定着すると、逆輸入型のサプライチェーンは、採算があわず、中国・東南アジアから、撤退、日本は、人口減少に入ったため、国内生産は人手不足で回帰すらできない。超円安は、大企業に、最先端の研究をする人材が、海外流出する状況を作っている。大谷選手のような海外評価が数十倍高いトップランナーが、米国で、雇用される状況は、頭脳流出の機会が増えていることを示している。日本国内企業は、同業種、同職種の世界的賃金比較で格差が開き、海外要因で、従業員の賃金抑制を持続可能ではいられない。また、超円安は、海外労働者が来なくなる事態を招いている。日本が、国際比較低賃金国になれば、国際賃金格差は、均等化する逆転現象が起きかねない。
所得予想が困難な日本経済
日本経済は、実質賃金がここ10年マイナスであり、近年2~3年持続している2%台のインフレにもかかわらず、賃金率が硬直的であるため、資産形成計画に、その予測の見直しをせざるを得なくなっている。中所得階層が格落ちし、低所得層に入り、中所得者の生活水準が下がり、子供がもてなく、単身家計が増加している。つまり、永続従業員の年齢に応じた家族手当を充当しできない企業が、すでに、発生している証拠である。家族構成員数が増加すれば、新規家族の消費が増加し、それを養う所得増が必要である。家族が子離れするまで、壮年世代の年収が増加するのは、住居・扶養家族手当が支給できる企業に勤めていることを暗黙に示している。実際は、日本企業は、終身雇用制を維持できなくなり、壮年世代の40歳台で、家族手当に相当する部分は、支給していない。企業に忠誠を誓う従業員はいなくしているのである。日本は、コロナ期に、経済活動が減少すると、連続して、出生率は低下、高齢者の死亡率は、コロナ対策が終了後、増加する、本格的な人口減少期に突入している。政府は、人口減少事態に、予算、社会保障負担増で、政策を取りだした。
家族構成員数と住居・扶養費増加の考慮
資産形成計画は、制度的には、本教室の第2章に見られるように、非課税制度が拡充されている。それ等を利用すれば、若年、壮年、老年世代の主要なイベントは、中間所得層の年収の範囲で、目標は達成で来るだろう。家族の構成員が何人まで増やすことが可能なのかは、全く考慮していない。専業主婦の2人、子供1~2人、それ以上の家族構成を考慮すると、所得はどれだけ必要なのかという問題である。低所得者の場合は、共稼ぎ世帯になり、実勢に適合した、共稼ぎ優遇所得課税のもとで、イベントの内、養育費・教育費は、国・自治体子育て支援給付金および教育費給付制度を利用するようになる。
人口減少時代が、顕在化する日本では、低所得者・子沢山世帯において、資産形成は、老後の安心程度となり、家族の就学・就業イベントは、人口減少社会保障制度利用を考慮するようになる。今後、資産形成論で取り扱う事例になるだろう。
資産形成計画は、開始年齢で、終了期間までの期間が大きく異なる。本教室では、若年世代、壮年世代、老年世代の3世代を想定している。若年世代は、20歳~32歳、壮年世代は、33歳~65歳、老年世代は66歳~85歳である。20歳は自己の責任において金融取引ができる年齢である。
若年世代の10年イベント表
若年世代の10年間は、仕事に習熟することと、家族をもつかどうかが主な目的になりなる。すなわち、この世代は、年間の所得水準が低く、10年間で、毎年の昇給が1歳上がるごとに月1万円以下上がる。23歳で基本給月23万円が、24歳で月24万円である。
海原氏イベント表において、23歳で、ボーナス・残業込み、年収300万でスタートすると仮定する。次年度は、12万昇給する生活を切り詰める貯蓄は寂しいので、社会性を広げるために、短期1年間の消費生活を充実する、たとえば、車、旅行、趣味、スポーツ等のために、半年で使い切る貯蓄、および住宅購入の頭金を貯蓄する財形住宅貯蓄を夏冬ボーナスで年間50万円、残金があれば、結婚資金にする。30歳で結婚すると仮定する。
海原氏イベント表
就職 結婚
年齢海原氏23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
妻 28 29 30
収入 300 312
324 336 348 360 372 384 396 408
消費支出 240 249.6 259.2 268.8 278.4 288 297.6
307.2 316.8 326.4
住宅頭金 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
合計
290 299.6 309.2 318.8 328.4
338 347.6 357.2 366.8
376.4
収支差額 10 12.4 14.8 17.2
19.6 22 24.4 26.8 29.2
31.6
世代開始年齢と所得
33歳は、本文にある山川家のイベント表の開始年齢である。日本銀行の関連会社から、毎年、最も廉価な『明るい暮らしの家計簿』が発行されている。山川家の生活設計プランが142ページに2006年まで、掲載されていた。年功序列制度では、入社10年で、ミスをしなければ、最初の係長という管理職になれる。しかし、1年間の評価で格下げになることもある。33歳は、その年齢であると理解していた。後は、課長、部長で、それぞれ、5~10年で、昇格する。これが年功序列制度の昇格波乗り3段階といい、その波ごとに、モデル賃金カーブが上昇する。
2006年まで、日本銀行関連会社では、山川家を標準家計としていたのだが、資産形成計画は、預貯金だけであり、先行きの物価上昇率は年1.0%、預金金利は、年0.2%、住宅金利は年3%を想定してあった。しかし、2007年から、このページはなくなった。リーマン・ショックもあり、日経は1万円を割り、預金金利は0.01%であり、貯蓄は現金を残すに等しい。日本は、安倍政権の誕生以来、日経平均は戻し、日銀の過剰緩和から、預金利子率、債券利回りは低下したままである。2023年4月、黒田総裁は任期満了で、退職、植田新総裁が着任した。
米国は、FRBの利上げとともに、資産市場が正常化しだした。コロナ禍で、FRBは、金融緩和し、再び、米株式市場は上昇した。しかし、2021年後半、インフレーションが始まり、2021年12月から、ウクライナ状勢が悪化、食糧・エネルギー価格の上昇が始まり、2022年2月ウクライナ開戦後は、食料価格が上昇しだした。これらの事象は、経済回復期の供給制約のインフレーションではない。通常のインフーションに2~3%追加され、各国中央銀行は、高インフレーションを抑制するために、金利を上昇させだした。持続的インフレーション下で、株価が低下し、景気を減速させるスタグフレーションになりそうな気配がある。
2024年6月17日、日本の預貯金利子率はほどんど0.025%であり、6月13日日本国債市場は、新発10年国債の利回りは0.965%である。日本株式市場は、2024年6月13日3万8720.47円である。為替市場は156.8円で推移している。この資産市場の状態で、山川家の主なイベントである、教育、子供の結婚、老後の安心、住宅ローンの返済を計画的に、達成する資産購入、運用、管理をすることを考える。テキストでは、どこで、住宅を取得するか、選択した現地で、取得費を帰属家賃と比較して、計算する。
最後に、65歳は、退職年齢であるが、山川さんは60歳退職であった。年金開始は65歳だから、つなぎの5年間、働かないと退職金を食いつぶしてしまう。団塊世代から、この空白期間が始まった。政府も退職者の雇用について、65歳定年は掛け声だけで、強制性がないので、だらだらと空白期間が続いている。地方都市では、中堅企業以上が、東京本社になっている例が多く、山川さんのようなサラリーマンはそれほど多くはいない。子供も手を離れ、持ち家であれば、2階建ての4LDKは、老夫婦二人には、2階部分はいらなくなる。2LDKで十分なのである。2階は、階段から落ちると骨折するので、掃除にも上がらなくなるのが普通である。退職金で余裕がれば、2階をなくし、老夫婦の利便性を考えた、自宅介護可能に、改築することを勧める。
日本の基本エネルギー計画では、今後十年、全世界化石燃料火力発電を全廃することになっていないから、化石燃料インフレーションは、10年間悩まされる。改築時に、屋根に太陽電池と蓄電池をつけ、一部、外部買電にすると、今回の電気代に悩まされることはない。その間、EV車つき家庭内IOTで、この10年間、完全自動化・管理システムが、日本全国の建物で、設置される流れになるだろう。安全・安心の住宅、賃貸住宅、職場、商業施設、公官庁、教育施設、医療施設になる。コロナ禍で、政府は公官庁、教育施設、医療施設等のデジタル化で情報共有を目指すだけでなく、完全自動化・管理システムを究極的に構築することになるだろう。
令和時代が始まり、山川さんは、現役のサラリーマンである。退職後の85歳まで、資産形成計画を立てるのであるが、退職後の住宅と住む市によって、現在、社会保障のサービスが行き届かない格差は、存在するだろう。現在、市の財政基盤が、潤沢であり、社会保障制度の施設が完備し、医者も多く、介護の人材も十分あれば、問題ないが、経済的活力が湯水のように湧き出し、市の財政基盤が潤沢でありつづけるかどうかは、しっかり、考慮する必要がある。
制度金融の利用
各世代の固有のライフイベントが決まり、生涯の資産形成計画が、大まかに決まってくる。サラリーマンの場合、退職後、国の基礎年金および事業体の厚生年金、企業年金を制度的につみたてた結果の給付を受け、自己資産の取り崩しで、老後の生活を支える。若年世代は、生涯期間が長く、ライフイベントは不確実である。自己積立資金も少ない。毎月、定額的に、給与天引きで、制度金融を利用する。運用方法は、定額購入のいわゆる「ドルコスト平均法」で購入する。壮年世代は、生涯期間が中間期間に当たり、ライフイベントも明確になっている。資産形成の基本は、毎月、定額的に、給与天引きで、制度金融を利用する。ただし、年間拠出額が増えているので、多様な金融商品選択でき、運用経験も10年以上ある。運用方法の「ドルコスト平均法」は、日本・米中景気変動、経済金融政策の変更に注意しつつ、制度金融は、引出ができない場合が多いから、選択する資産購入の一部、停止,他の資産に運用を振替る「リバランス法」が必要になる。
6.2 イベントに基づく資産形成計画
若年世代、壮年世代、老年世代の金融行動の目的を設定し、山川家と高原家それぞれの場合、イベント表の仮定と推計法を例示します。収支差額を、制度金融を利用した貯蓄配分表に投資し、運用結果を評価する期末貸借対照表を作成しました。
1) 世帯のイベント表作成手順
収入の流列の推計
物価上昇率を決めて、世帯主の所得の推計をする。23歳から32歳まで、毎年、3%で所得上昇、ボーナスは年2回、4か月分を標準とする。33歳から45才まで、2%で所得上昇、46歳から55歳まで1%上昇、56歳から60歳まで、1割減で、フラット化する。61歳から65歳までに再就職する。年収は現役の6割とする。
65歳から年金受給を推計する。
公的年金 生涯平均年収の5割(65歳から)
企業年金
確定給付企業年金の場合、平均年収の2割(60歳から10年間年金)
確定拠出企業年金の場合、拠出総額の2倍(最大)
確定拠出個人年金iDeCo 拠出総額の2倍(最大)
財形貯蓄 拠出総額の2倍(最大)
支出の流列の推計
家族の主要なイベントを想定し、イベントの目標額を見積もる。
住宅ローンを推計する。
主なイベントの年間必要額(月額)を計算する。
イベント表に数値をいれる。
収支、差額を計算する。差額を期首退職対照表に繰り入れ、期間資産変動、負債残高を記入して、期末貸借対照表を作成する。
2) 各世代のイベント表の特徴
①若年世代23歳~32歳の金融行動
若年世代の10年間は、仕事に習熟することと、家族をもつかどうかが主な目的になりなります。すなわち、この世代は、年間の所得水準が低く、10年間で、毎年の昇給が1歳上がるごとに月1万円以下上がる。23歳で基本給月23万円が、24歳で月24万円です。
海原氏イベント表において、23歳で、ボーナス・残業込み、年収300万でスタートすると仮定します。次年度は、12万昇給する生活を切り詰める貯蓄は寂しいので、社会性を広げるために、短期1年間の消費生活を充実する、たとえば、車、旅行、趣味、スポーツ等のために、半年で使い切る貯蓄、および住宅購入の頭金を貯蓄する財形住宅貯蓄をし、残金があれば、結婚資金にします。30歳で結婚すると仮定します。
イベント分析の枠組み
海原氏イベント表
年齢 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32
28 29 30
収入
300 312 324 336 348 360 372 384 396 408
消費支出 240 249.6 259.2 268.8 278.4 288 297.6
307.2 316.8 326.4
住宅頭金 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
合計 290 299.6 309.2 318.8
328.4 338 347.6
357.2 366.8 376.4
収支差額 10 12.4 14.8
17.2 19.6 22 24.4
26.8 29.2 31.6
イベント表の仮定と推計
収入の推計
海原氏の初任給は年収300万円(ボーナス込み)とします。基本給22万×12=264万、ボーナス基本給×4(ヵ月)=88万円を想定しました。諸税を52万円としています。毎年、12万円昇給があるとしています。
支出の推計
消費支出は、年収の8割とし、短期の消費生活充実に使います。
住宅取得計画
住宅頭金は、年50万円貯蓄します。33歳、期首財形住宅貯蓄500万円が目標です。住宅取得の目的がなければ、NISA制度を利用します。目的は、結婚資金等です。
収支差額表 期末貸借対照表
年齢 収支差額 資産 (財形 iDeCo 預金) 負債 純資産
23 10 50 10 0
0 60
24 12.4 100 22 0.4
0 122.4
25 14.8 150 34 3.2 0
187.2
26 17.2 200 46 8.4
0 254.4
27 19.6 250 58 16
0 324
28 22 300 70 26
0 396
29 24.4 350 82 38.4
0 470.4
30 26.8 400 94 53.2
0 547.2
31 29.2 450 106 70.4
0 626.4
32 31.6 500 118 90
0 708
合計
208 500 118 90 0 708
運用計画と非課税制度利用
就職を期に、企業年金iDeCoに加入し、毎月1万円、会社から1万円で、指図運用します。残金が発生しますが、預金か、NISAで運用することを想定します。
第2章の非課税制度を運用計画に適用すると次のようになります。
住宅資産形成 財形持家融資制度低利融資(財形住宅貯蓄550万円)夏冬ボーナス月天引
老後の安心 企業年金iDeCo 毎月給与から天引
その他 NISA5年間1名年120万円まで非課税 (120万円)差額の自己運用
② 壮年世代33歳~65歳の金融行動
壮年世代33歳から65歳までの金融行動の目的を説明します。33歳から48歳まで2人子供の教育資金と36才まで住宅取得の頭金・建設資金が貯蓄の主な目的です。前者は、子供の入学時に順次、取り崩します。
2000年に入って、日本経済は、金融システムの再編があり、大手金融機関、中小金融機関は統合され、企業も再編されました。そのため、非正規雇用が増加し、正社員の賃金カーブも40歳以上ではフラット化してきました。
大学に、キャリア教育が導入され、企業は、企業の採用後、社員教育をしてきたコストを大学教育に求めるようになってきたと理解していました。まさに、学生は、正真正味の即戦力となる厳選採用でした。2008年の世界的なリーマン・ショックも発生し、壮年世代は、年収のダウンで教育資金どころではなく、大学進学の塾費用まで減らした家庭も多かったでしょうか。子ども手当、授業料無料化を公約する民主党政権が誕生した背景は、教育費の負担ができず、学生は、奨学金で授業料を支払い、生活費はアルバイトだったことも、大きく選挙結果に表れています。現在、教育資金は、貯蓄できるほど、30歳代の所得は、回復しているとも思えません。政権を転覆した自公が、教育負担の公費政策で、教育負担が減る仕組みを作りました。したがって、教育資金は、低所得者、子だくさん家庭ほど、貯蓄して、準備する必要が軽減されています。一般的に、高校進学時の一時金30万円+大学入学金・授業料400万円が教育資金の目安です。大学の奨学金制度や日本学生支援機構のサイトから、各種奨学金の額と給付条件を調べて、目標額を設定する方が具体的でいいです。
ちなみに、私は学部学生の間は、父の所得が高かったため、奨学金を受給していません。当時の入学金・授業料は、はるかに低かった。阪急電車の通学定期も安かった。大学院入学後は、学生援護会の奨学金を確か、5年間受給しました。返済額120万円だったと思います。大学院退学と同時に、追手門学院大学に教員として採用されてからは、教員のため、在職証明を8年以上出して、制度改正で12年に延長され、ついに、返還免除されました。この間、海外を飛び回り、毎年、ますます、命がけになりましたが、死ねば、この借金が残るのが気になっていました。海外旅行はVISA、アメックスを持っていきました。東西冷戦終結し、命がけでなくなりましたが、結婚後は、家族のことがあるので、普通は3千万円でしょうが、団体生命保険5千万円をかけて、海外旅行保険5千万円とで出かけました。
住宅取得の頭金・建設資金は、主要な貯蓄目的になりますが、その目標額と取得時期は、各家庭で目標が違うでしょう。住宅ローンの返済に入った世代では、余分の貯蓄差額は、老後の安心になります。しかし、中小企業では、高齢少子時代で、需要が減少、市場が縮小し、廃業していく事業継承リスクが目立ち始めた昨今、退職金が出せない企業が増えています。廃業する見込みの企業にとっては、退職金制度は、負債でしかありません。また、転職すれば、退職金は算定が勤続年数0年に戻るので、あてにできず、自己積立にできる確定拠出年金iDeCoに加入するのが、老後の安心になります。
イベント分析の枠組み
山川家イベント表
年齢 33 35 36 44 46 48 56 60 61 65 66 68
30 32
33 41 43 45 53 57 58 62
63 65
8 21
5 20
収入 500 520 530 605 615 625 500 500 350 350 230 300
支出 300 312 318 363 369 375
300 300 280 280 230 270
住宅ローン 143.6 …
143.6
住宅頭金50 50
教育費 43.75 … 43.75
合計 393.75 405.75 505.35 550.35
556.35 443.6 443.6 280 280 230 270
差額 106.25
110.25 24.65 48.65 62.65 56.4 56.4
70 70 0 30
イベント表の仮定と推計
収入の推計
モデル賃金カーブを次のように想定する。33才で、手取り年収500万円とする。42才まで、年10万円増加する。43才から55才まで年5万円増加する。56才から。60才定年まで500万円であり、61才から65才まで350万円で再雇用される。物価上昇率は想定しない。モデル賃金から、計算したわけではないが、66才から、企業年金70万円と基礎年金+厚生年金160万円を受給する。68才から。妻の基礎年金78万円が支給される。
基礎年金の受取額は、厚生労働省のHPから毎年分かる。厚生年金は、モデル賃金カーブからシミュレーションするが、簡単ではない。賞与からも保険料を支払うようになっている。各業界で、各年齢の所得を計算したサイトがあるので、モデル賃金カーブを作成、利用する。
支出の推計
消費支出
山川家では、現役時代は、収入の6割を消費支出にあてる。61才から65才まで収入の8割、66才、67才は、年金を全額消費する。夫婦で基礎年金を受給する68才から年金の9割を消費する。
財務計画
収支差額は、その他とする。山川家のローン契約前は、教育資金と住宅準備金の貯蓄が主な使い道であるが、ローン返済が始まると、貯蓄と返済が使い道になる。テキストには、資金運用をしない年間教育資金を計算している。住宅取得計画は、住宅を選定する時間を多くとり、山川家では36歳から60歳まで、年3%、25年ローンを元利均等払いで組んでいる。
住宅取得計画 どこに住宅を求めるか。最近は、減反農政も終了し、都市農家の廃業に伴い、農地売却が増加、供給増になる現象が目立っている。親子2世帯同居ではなく、子供は賃貸で、親は住宅地に住んでいる過渡期の状況である。親の住宅は、手放す例がぽつぽつ、新興地で見られるし、地方でも見られ、建て替えも増加している。高齢・少子時代から、本格的な人口減少時代に、入っているので、町を観察していると、新規開業しても、続かず、廃業してしまう。地元農家資本の店もほとんど廃業した。客がいなくなっているのだ。住宅取得者は住宅用地の超過供給の状況があるので、宅地であれば、既成の住宅地は、候補の一つになる。さらに、百年に一度、二百年に一度、五百年に一度とか、災害の強度が大きくなっている昨今、地域災害史とハザードマップは、しっかり、検討することが大事である。
さて、地球温暖化によって、その災害強度が、二百年に一度レベルに上昇している。その回数は、毎年起きてもおかしくない。もし、災害により住宅が被害にあうと、保険でカバーできなければ、二重ローンは、老後の安心をつぎ込むことになる。(住宅供給公社が開発したなら、被害後、再建費用は軽減される。)また、保険会社も、想定できる災害の種類と実際のデータ増加に伴い、住宅の被災確率を計算しているから、新築住宅に保険をかけると、災害確率の高い住宅地は、保険料を高くするだろう。
災害で、JRの地方線では、最近の集中豪雨で、線路や橋が流され、各社では復旧工事費が捻出できず、自治体と廃線の方向しかないところもある。国有鉄道に時代では、線路、路肩、関連鉄橋工事は、国の予算で復旧できた。JRが民間会社となり、鉄路の維持管理費は、各社持ちになっている。JR本体の財政では、災害復旧工事費は、賄いきれないのだろう。すでに、沿線の人口減少で、採算割れもしている。地方の高齢社会では、運転免許の返上に伴う、代替交通の確保がなければ、高齢生活は維持できない。
収支差額表
教育資金計画
16年間目標積立額700万円、毎年の積立額43.75万円とする。最近は、出生率低下を阻止する国・自治体の少子対策で、子供手当、授業料無料化等による、生活費・教育費公費扶助・補助がつき、自己負担が軽減されている。年収と子供の能力・将来を勘案して、教育資金計画を立てることになる。年収不足で、さらに無計画だと、子供の成長期に、教育資金を政府金融機関で借り入れることになる。しかし、大学進学は、少子対策による、奨学金等の支給条件の多様化で、低所得者層の教育費を支給するようになってきた。
住宅取得計画
33歳、期首財形住宅貯蓄350万円、残り3年間頭金年間50万円、25年間借入額2,500万円、年間返済額143.6円元利均等払い(利息43.6万円、元金100万円)とする。
老後の安心
残額を老後の安心とする。
以下の収支差額表は、イベント表の抜粋である。期末貸借対照表は、33歳から48歳までである。
収支差額表 期末貸借対照表
年齢 教育資金 差額
年齢 財形 積立 預金
固定資産 負債 純資産
33 43.75 106.25 33 400 43.75
106.25 550
35 114.25 34 450 87.5 212.5 750
36 24.65 35 500 131.25 326.75 958
48 43.75 62.65 36 175 351.4 3000
2500 1026.4
49 118.4 37 218.75 380.05 3000 2400 980.05
55 120.4 38 262.5 412.7
3000 2300 1375.2
56 56.4 39 306.25 449.35 3000 2200
1555.6
60 56.4 40
350 490 3000 2100 1740
61 70 41 393.75 534.65 3000 2000
1928.4
62 70 42 437.5 583.3 3000 1900 2120.8
65 70 43 481.25 635.95 3000 1800
2317.2
66 0 44 525 690.6 3000 1700 2515.6
67 0 45 568.75 747.25 3000 1600
2716
68 30 46 612.5 805.9 3000
1500 2918.4
47 656.25 866.55 3000 1400
3122.8
48 700 929.2 3000 1300 3329.2
運用計画と非課税制度利用
第2章の非課税制度を運用計画に適用すると次のようになる。
1子の教育費 旧ジュニアNISA(18歳まで)子1名年80万円
(400万円)
新NISA制度では、廃止。両親1800万円×2の枠で積み立てる。
2住宅資産形成 財形持家融資制度低利融資 (財形住宅貯蓄550万円)
3老後の安心 財形年金貯蓄元利合計550万円まで、非課税 550万円
新NISA成長投資枠、年240万円まで非課税
新NISAつみたて投資枠、年120万円まで非課税 合計1,800万円
夫婦で(3,600万円)
1 山川家イベント表から,毎年,教育資金を43.75万円,16年間,貯蓄する.教育資は,新NISAのつみたて投資枠が,最も適している.
2 住宅ローンは,頭金が3年残っているので,その間,住宅の選択に入り,36才から,住宅ローンを開始し,25年間返済し,60才で返済を終える.
3
収支差額が毎年発生するが,その総額は,非課税枠内に入る.まず,老後の安心のために,iDeCo,残りは,つみたて投資枠か、成長投資枠にする.
③ 老年世代65歳~85歳の金融行動
老年世代65歳から85歳までの金融行動の目的を説明する。老年世代になると、公的年金を受給できるが、公的保険を支払う義務が生じる。公的年金から公的保険を天引きする。生活に不足する分は、資産形成と退職金から、取り崩すことになる
資産形成と退職金は、目減りしないように、新NISAつみたて投資枠または成長投資枠を利用しつつ、運用を続けることになる。山川氏と代わって、退職した高原氏のイベント表を作成する。
イベント分析の枠組み
高原家イベント表
年齢 66 67 68 69 70 71 72 73 85
64 65
66 67 68 69 70 71 82 83 84 85
収入 270 270 270 270 270 270 270 270 270 135 135 135
年金
116 116 194 194 194 194 194
194 194 103
103 103
取り崩し 154 154 76 76 76 76 76 76 76 32 32 32
支出 270 270 270 270 270 270
270 270 270 135 135 135
イベント表の仮定と推計枠組み
公的年金および厚生年金は、算出方法が公開されているので、正確であるが、将来予測はできない。現在給付高をそのまま使う。企業年金も拠出額は、算出可能だが、運用額は、資産管理会社の通知で分かる。老後の安心も、銀行・証券会社で拠出額と運用額が分かる。
収入の推計
公的年金(-控除)公的保険(国保,介護)=公的年金収入
実例
公的年金収入=基礎年金(779,300円×2)-公的保険(国保270,309円総所得200万円2人簡易計算,介護126,720円第8段階)=1,161,571
厚生年金(779,300円基礎年金と同額とする)
年金手取り額 1,940,871円=公的年金収入+厚生年金=1,161,571円+779,300円
企業年金(確定拠出年金):23歳から60歳まで、拠出月数=12カ月×38年=456カ月、企業拠出総額=2万円×456=912万円、企業年金(確定拠出年金)運用額=拠出総額×1.2倍=912万円×1.2=1094.4万円
老後の安心拠出総額=2,285万円 運用額(平均2%)=2,285万円×1.02=2330.7万円
退職時資産:金融資産=企業年金1094.4万円(退職金に相当)+自己資産2330.7万円=3425.1万円
支出の推計
消費支出
高原氏は、平均寿命85歳で終わるように、見込んでいるから、支出を年270万円とすると、2,700,000-1,940,871=759,129 となり、年約76万円不足する。高原氏の資産は、運用額で、3425.1万円であるから、3425.1万円÷20=171.255万円であり、十分、賄える。
収支差額表 期首貸借対照表
年齢 取り崩し 資産 現預金 投資信託 固定資産 負債 純資産
66 154 2234 0
3000 0
5238
67 154
2084
0 3000 0
5084
以下の表は、テキスト本文pp.100‐101にある。
運用計画と非課税制度利用
金融資産取り崩しで、年間76万円取り崩すので、その額を年金化する方が、運用のわずらわしさから、開放されるだろう。この問題は、次回、以降で、取り扱う。実物資産である自宅については、その資産価値は、日本の住宅では、通常、建物は耐用年数30年で、0になる。個人住宅では、減価償却引当金を積み立てていないためそうなる。固定資産の内、建物の価値は0円である。退職後、20年間、さらに、住むわけであるから、リフォームが必要になるかもしれない。
第2章の非課税制度を運用計画に適用すると次のようになる。
高原家イベント表から、NISAが、最も適している。一人、NISAつみたて投資枠年120万円または成長投資枠240万円まで非課税であり、5年間で、投資枠は360万円×5=1,800万円である。夫婦で、合計3,600万円可能である。収支差額が毎年取り崩し76万円である。ただし、どちらかが死亡すると、投資信託と株式では、相続時点での評価が異なり、現物を相続しても、相続人の投資枠制限がかかる場合がある。
今週(2025年6月23日~6月27日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、15日主要7カ国首脳会議が17日までカナダ西部アルバータ州で開かれました。13日イスラエルがイランを空爆、核施設と革命防衛隊司令官・関係者を攻撃しました。そのため、トランプ大統領は、G7会議、首脳会談を1日で切り上げ、イスラエル・イラン戦争に対応するため、帰国しました。16日日銀政策委・金融政策決定会合が17日まで開かれ、政策金利は0.5%で据え置きでした。17日米連邦公開市場委員会が18日まで開かれ、政策金利上限は4.5%に据え置きでした。18日ロシア・サンクトペテルブルク国際経済フォーラムが21日までありました。ロシア政府は140カ国が参加したと報道、欧米からの参加企業は少なく、インドネシアと包括的パートナーシップを結びました。ロシア中央銀行は政策金利が21%から20%に下げ、西側の予想通り、2025年上期GDP成長率が下がり、経済相はロシア経済が景気後退に入ると言っています。高金利で、民間消費ローン、住宅、自動車ローンは減退し、民間投資はなく、民間企業の手持ち流動性がひっ迫、年間徴兵16万人と軍需産業に労働者が吸収され、民間企業活動は低下が続いている。20日国債市場特別参加者会合が財務省でありました。2025年に入って、超長期債の利回りが1%以上上昇しているためか、30年債・40年債の超長期債発行計画を見直すと観測されていました。結果、超長期債の発行計画を3兆2000億円減額、短期債を増額発行、総額は維持する。
今週のイベントは、22日東京都議選投開票があります。24日NATO首脳会議がオランダで25日まであります。アジアインフラ投資銀行年次総会が、北京で26日まであります。夏季ダボス会議が天津で、26日まであります。
経済統計は、次の発表がありました。
予測値 実現値
6月16日 中5月小売売上高 5% 6.4%
5月鉱工業生産指数 6% 5.8%
17日 日政策金利 0.5% 0.5%
米5月小売売上高 -0.7% -0.9%
5月鉱工業生産指数 0.1% -0.2%
18日 日4月機械受注 -4.9% 6.6%
5月通関ベース貿易収支 -8978億円 -6376億円
19日 米政策金利 4.5% 4.5%
20日 日5月CPI 3.5%
3.5%
5月全国スーパー売上高 1兆915億8404万円
5月全国コンビニエンストア売上高 1兆162億800万円
米5月景気先行指数
-0.1% -0.1%
経済統計は、次の発表があります。
予測値
24日 米3月経常収支 -4435%
日5月全国百貨店売上高
25日 日4月景気先行指数 103.4
景気一致指数 115.5
26日 米3月実質GDP -0.2%
3月GDPデフレータ 3.7%
3月個人消費 1.2%
5月耐久財受注 0.8%
27日 日5月完全失業率 2.5%
5月有効求人倍率 1.26倍
6月東京都区部CPI 3.3%
5月全国百貨店売上高
米5月個人所得
0.2%
5月個人支出
0.2%
5月PCEデフレータ 2.6%
第13回目 2025年6月30日
要点
6.3ドルコスト平均法
・制度金融の利用枠のもとでのドルコスト平均法
・(1)海原さんの場合
・(2)山川家の場合
・(3)高原家の場合
6.3ドルコスト平均法
制度金融の利用枠のもとでのドルコスト平均法
会社員の制度金融利用枠は、企業に制度がある場合、財形住宅、財形年金、確定拠出年金DC、個人加入できるiDeCoの制度がある。個人貯蓄では、成長投資枠NISA、つみたて投資枠NISAの制度がある。
これまでの各節で、段階的に計算してきたイベント目標額を企業加入制度、個人加入制度によって、利用枠を決める。新入社員は月別、山川家、退職者は年別で、貯蓄・投資額が決まる。制度別は、拠出額が決っている。実践では、月別の貯蓄・投資額を金融商品に割り当てる。企業加入制度では、資産管理・運用会社が指定され、金融商品も指定されている。個人加入制度では、任意に契約できるが、資産管理・運用会社を替えることは、コストがかかる。
したがって、これらの制度枠利用は、月別、資産管理・運用会社が決まっていることが前提である。その上で、投資者は、その会社の提供する商品を選択することになる。資産選択理論を利用すれば、自分の期待収益率とその分散の傾向(期待効用関数)を自覚し、提供商品リストから、自分の傾向に適合する割合が決まる。毎月、第11回目の実践の式を使い、市場で購入する。ただし、有効フロンティア計算のためのデータ取得は、月1回、月次データをデータ表に記録するだけでも、根気がいる。今回の本文のおわりに、選択した6つ投資信託の期間(2019/1/27~2025/5/27)の基準価格データを掲載している。
ドルコスト平均法
勤労者であれば、毎月の制度利用の天引き額が決まっており、さらに、ボーナス月の自主的投資額25万円が、基本の投資額である。不定期の収支差額は、各月の予備的資金として、流動性の高い預金等に半年をめどに、月々の収支を調整する。。不定期の収支差額を定期的な資産形成に回すのは、日常生活を犠牲にすることが多いので、やめた方がいい。
ドルコスト平均法:ドルコスト平均法は、毎月、決まった商品を定額資金で購入する投資方法である。
ドルコスト平均法は、「時間分散法」といわれる。投資期間が6カ月あれば、その期間、1回から数回、市場動向を読んで安い時、蓄積資金全額で、投資信託を購入する場合と、月割りの時間均等に6回、その投資信託を定額購入し、時間を分散する場合とでは、時間分散・定額購入した場合の方が、6カ月後の運用成績がよい。
制度利用の天引きならば、その額を毎月27日に、運用会社の口座に自動振替し、一つの商品に定額投資する。これは、自動的に、毎月時間分散・定額購入のドルコスト平均法を適用していることになる。公務員の給料日、年金者の年金支給日は15日、民間会社では、20日締め、25日が給料支給日、小規模業者では、給料支給日は月末が多い。毎月27日を選ぶのは、給料支給日後を選んでいるためである。ボーナス月の25万円は、各金融商品の値動きが低調な、ボーナス月の15日か中旬に投資する。
2種類以上の商品を、(標準偏差σ、平均収益率μ)の平均・分散法で選択しているのであれば、各商品に割り振った資金で、定額購入する。たとえば、2種類の投資信託、日興-DCインデックスバランス(株式60)とSBI-EXE-iグローバルREITファンド(2024年1月SBI-EXE-i全世界REITファンドと改称)を資産選択理論で最小分散の最適割合を決める。
5.2節 最適資産選択にもとづく資産購入を応用する。配分割合Aは,定義により,A=(P×b)/Wの関係式がある。実際の商品の標準偏差σ、平均収益率μは計算されていて、理論上、最適配分割合は、それらの標準偏差σ、平均収益率μに依存する。ここでは、最適割合Aを二分の一とし、毎月2万円が制度利用の拠出金Wであれば、それぞれの投信を毎月1万円定額購入する。定期購入時の投資信託の基準価格をPとすれば、その投資信託の購入口数は、b=A W/Pである。
長期少額投資の基本戦略
10年以上の少額投資の基本戦略は、平均分散法(状態分散法)で、最適化した、複数の商品を選び出し、ドルコスト平均法(時間分散法)で、毎月、時間を分散して、決めた商品を定額購入していくことである。商品の選択は、変更は可能であるが、頻繁の変更は、ドルコスト平均法ではなくなる。投資期間6カ月の間は、投資信託商品の基本価格が激変しない限り、毎月、決めた商品を定額購入する。
(1)海原さんの場合
第12回目に戻ると、海原氏の年齢により、スタートする収支差額と期末貸借対照表は、テキストにある。運用は考慮していない。新入社員は、貯蓄配分表を作成する。企業加入制度は、および個人加入制度は、例として、SBI証券とインターネット銀行を契約したとする。インターネット証券・銀行の場合、スマホ取引が可能であり、売買の指示が即時的である。取引手数料も安い。インターネット証券・銀行の場合、登録すれば、保有資産の評価額を随時見ることができる。
新入社員の場合、企業の拠出額は、月1万円とする。SBI証券のサイトにおいて、iDeCoの商品リストを見る。投資信託受託証券は、すでに、分散投資になっているので、個人でさらに資産選択をする必要はない。商品は、主に、日本債券、日本株式、外国債券、外国株式に分類される。後は、それらのミックスである、バランス型になる。
現在、海原氏は、現在、27歳だとする。結婚を30歳に控えている。
海原氏の戦略(2020年版資産形成論)
運用計画
計画は夏冬ボーナスそれぞれ25万円を積立て、財形は、250万円ある。iDecoは、月1万円で、これらは、天引き貯蓄だから、運用計画が残る。財形および取り崩しはできない。預金は、予備的動機にもとづく。
海原氏が27歳の場合、2019年7月から、2020年3月まで、財形に、日興-DCインデックスバランス(株式60)を当てる。iDecoは、SBI-EXE-i全世界REITファンドにする。預金は、16万円あるので、NISAで運用すると、総合食品スーパーなどで、株主優待制度と配当が1~2%を超える株式を購入できる。その期間中、商品割引の特典がつく最小の株数以上を購入する。今回、チャンスは、コロナ暴落で、16万円で買える。
投資信託の選択
証券会社のサイトは、セキュリティ対策で、年間チャートのグラフは、オープンでなくなり、ログインを要求されるようになった。Google等、検索から、以下のファンド名で、直接、日々の基準価格の1年間チャートがみられるサイトを選ぶ。
本教室は、海原氏、山川氏および高原氏の選択する投資信託を、以下の6種類の投資信託しとし、債券、インデックスバランス(株式20、40、60)、全世界REITおよびJ-REITである。
SBI-EXE-i先進国債券ファンド
日興-DCインデックスバランス(株式20)
日興-DCインデックスバランス(株式40)
日興-DCインデックスバランス(株式60)
SBI-EXE-iグローバルREITファンド(2024年1月SBI-EXE-i全世界REITファンドと改称)
ニッセイ-DCニッセイJ-REITインデックスファンドA
口数の計算法
10,000(円)投資額:(対) 基準価格(円)=x(口数):(対) 10,000(口数)
x口数={10,000(円)投資額÷基準価格}×10,000(口数) (1)
実際のデータを使い、10,000円の投資額で、SBI-EXE-iグローバルREITファンドの基準価格13,536では何口買えるのか、(1)式に代入して計算すると
SBI 2017/10/27 7,387=10,000÷13,536×10,000
7,387口買える。半年、計算すると、次のようになり、期末合計は45,515口になる。
2017/10/27 11/27 12/27
1/29 2/27 3/27 口数合計
SBI 13,536 13,665 13,816 13,498 12,544 12,202
口数 7,387 7,317
7,237 7,408 7,971 8,195 45,515
期末評価額は
3月総評価額=口数合計÷10,000×基準価格
=45,515÷10,000×3月末基準価格(12,202円)
=4.5515×12,202円=55,537円(評価損4,463円)
となる。このファンドは、基準価格が下落していったので、評価額は損失がでているが、反比例して、口数が増加する。
2019年、この教室の始まる前、SBI証券のサイトにおいて、選んだのが、次の2本である。選択理由は、信託報酬率が1%以下、投資総額が多い、長期間の実績がある。
日興-DCインデックスバランス(株式60)
SBI-EXE-iグローバルREITファンド(2024年1月SBI-EXE-i全世界REITファンドと改称)
コロナの影響が出たのは、2020/3/27からであり、特に、SBI-EXE-iグローバルREITファンドは、下落が大きい。この場合、売却できないから、ドルコスト平均法では、そのまま、買うか、SBI-EXE-i先進国債券ファンドに、相場が反転するまで、切り替える。しかし、リートの特徴は、株式より、急激に落ちるが、賃料は2年間固定されているので、下限に到達すると、反転は、株式より大きい特徴がある。実証でも、確かめられている。
同様に、財形の日興-DCインデックスバランス(株式60)も。戦略の変更をしなくても、コロナは乗り切れている。
2024年7月以降の戦略
年2回、20万円を財形住宅貯金とする。海原氏は27歳なので、財形は、DCインデックスバランス(株式60)に、ボーナス月、7月および12月に、それぞれ、20万円投資する。iDeCoは、月1万円である。半年ごと、ドルコスト平均法で、DCインデックスバランス(株式60)またはSBI-EXE-i先進国債券ファンド、SBI-EXE-iグローバルREITファンドのいずれかを選び、毎月1万円投資する。
成長投資枠NISAの日本株式を月1万円購入する。日本経済は正常化途上にあるが、2024年に入って、日本の消費者物価は2%以上のインフレに入り、株式価値もインフレに財務諸表が連動するため、日経平均は35000~40000円の幅を動きだした。景気動向、業績相場とは違う、インフレ会計上の株式価値の評価シフトに過ぎない。日本経済がインフレ期に入っている証明になる。
景気動向、業績を勘案して、成長性のある株式で、正常化すれば、上昇が期待できる銘柄を1社選ぶ。年間12万円およびボーナス月の投資額がある。従来のNISAは、5年期限があったが、成長投資枠NISA では、無期限になった。20%以上、値上がりすれば、売却し、利益を確定、同じ銘柄か、成長性ある銘柄に、ボーナス月は、全額投資する。
(2)山川家の場合
運用計画と非課税制度
非課税制度
第2章の非課税制度を運用計画に適用すると次のようになる。
1子の教育費 つみたて投資枠NISA (400万円)
2住宅資産形成 財形持家融資制度低利融資 (財形住宅貯蓄550万円)
3老後の安心 財形年金貯蓄元利合計550万円まで、非課税 550万円
つみたて投資枠および成長投資枠NISA3600万円非課税
夫婦で(拠出額3600万円)
合計 財形 1100万円
NISA 3600万円
教育資金計画
山川家イベント表から、子2人16年間目標積立額700万円、毎年の積立額43.75万円である。教育資金は、つみたて投資枠NISAが、最も適している。
住宅取得計画
33歳期首財形住宅貯蓄350万円、残り3年間頭金年間50万円を貯蓄し、36歳から、25年間借入額2,500万円、年間返済額143.6円元利均等払い(利息43.6万円、元金100万円)とする。
住宅ローンは、頭金が3年残っているので、その間、住宅の選択に入り、36才から、住宅ローンを開始し、25年間返済し、60才で返済を終える。老後の安心
収支差額が毎年発生するが、その総額は、非課税枠内に入る。まず、老後の安心のために、iDeCo、残りは、つみたて投資枠および成長投資枠NISAにする。
企業加入制度iDeCoは、企業の拠出額を2万円とする。標準月収が増加すれば、拠出額は増加する。新入社員が月1万円としたよりは、山川氏は、商品選択は少なくとも2本可能である。
山川家の戦略
投資信託の選択
教育資金運用
つみたて投資枠NISAおよび成長投資枠NISAは、日興-DCインデックスバランス(株式40)または(株式60)およびニッセイ-DCニッセイJ-REITインデックスファンドAをそれぞれ、3.6万円および1万円で毎月購入する。引出期に近づく場合、そのときの株式市場相場で、利益が減少するから、利益を確定し、変動の少ないSBI-EXE-i先進国債券ファンドを購入する。
老後の安心
DCおよびiDeCoは、それぞれ、2万円、日興-DCインデックスバランス(株式40)または日興-DCインデックスバランス(株式60)を毎月購入する。退職期が近づくと、一時金にするか、個人年金化するか、選択する。
(3)高原家の場合
高原氏の安心運用資金は、運用無しで、2,285万円である。上述のドルコスト平均法で、元本が減少しない投資信託を半分以上、10年間、75歳まで、変動の少ない、バランス型(株式20)またはSBI-EXE-i先進国債券ファンドの投資信託で運用する。残りは、10年間、元本維持型の定期預金またはSBI-EXE-i先進国債券ファンドの投資信託で、取り崩し資金にする。
妻が100歳まで長生きしても、資産の取り崩しは15年間で32×15=480であるから、資金は枯渇しない。
運用計画
金融資産取り崩しで、年間76万円取り崩すので、その額を年金化する方が、運用のわずらわしさから、開放されるだろう。実物資産である自宅については、その資産価値は、日本の住宅では、通常、耐用年数30年で、0になる。山川邸は、減価償却引当金を積み立てていないためそうなる。退職後、20年間、さらに、住むわけであるから、リフォームが必要になる。実際、実行した例でいうと、リフォームの内容は、エアコン、台所とくにIH調理機、洗面所・浴室、エコキュウト、トイレ、介護用手すり、バリアフリー、外回りは、PV設置、蓄電池、外装、外周りの手摺(介護認定されると、レンタル介護用品、介護設備費に市からの補助金がある。温暖化対策で、二重ガラス窓、外装等の断熱工事、PV設置に補助金が出る場合がある。)などである。高齢者住宅は、特に、火災のリスクのため、オール電化、熱中症対策に空調、停電のための蓄電池装備が望ましい。
リフォームと市からの補助
リフォームは、介護保険や市の補助金がつかえる。バリアフリーは、段差を滑らかにする補助材がある。廊下、家・外の階段は、老人の動線に配慮、手すりをつける。2階は、昇降機を付けることが、一番安全であるが、老人は、2階を使わせてはいけない。知り合いでも階段から落ちて、骨折した。老人の骨折は寝たきりになるもとである。浴室での転倒、のぼせ溺死対策で、手すりは必須であり、トイレも全面手すりで移動できるようにする方が安全である。便座の両側に手すり、立ち上がりに、つかまり手すりを付ける。便座の両側の手すりは、普通の人も、便秘気味であれば、手すりにつかまって、腰を浮かし、軽く、きばると、割とスムーズに大便が排出できる。大便の原料、食材は、野菜を多くすると、なめらかにできるが、それをしないと粘り便になるようだ。玄関は、踏台と手すりをつけるとよい。
退職金は、期首貸借対照表に、計上していないが、以上の老人用リフォーム資金に充てることが望ましい。高原氏は、20年間、妻は100歳までなので、住宅設備の更新等の予備費として、退職金の残りは、生活費に回さないことが望ましい。
高原邸は、退職金でリフォームを済ませているとする。
高原家の戦略
投資信託の選択
投資資金の半分以上は、10年間、引出がないので、日興-DCインデックスバランスは株式20か40で、収益を確保する。残りは、10年以内に、引き出すので、定期預金またはSBI-EXE-i先進国債券ファンドを購入する。
今週(2025年6月30日~7月4日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、22日東京都議選投開票がありました。昨年と衆議院選と同じ、自公が大幅に議席を減らした。このまま、参議院選に突入すると、参議院でも、自公過半数割れはほぼ確定。石破氏の選挙責任問題になり、首班指名はむつかしい。「楽しい日本」とか、本人の夢想を政策主張におき、世界の難局に対して、安心・安全に、国民のなりわい・諸活動を円滑に、日本社会・経済を、順風満帆に導いている自覚は見られない。トランプ氏も、安倍氏と比較すると、石破氏の国内政治基盤が弱いので、相手にしない。24日NATO首脳会議がオランダで25日までありました。石破首相はNATO首脳会議、欠席、外務大臣が出席しました。アジアインフラ投資銀行年次総会が、北京で26日までありました。夏季ダボス会議が天津で、26日までありました。
今週のイベントは、1日日銀短観が発表されます。国税庁から路線価が公表されます。3日参議院選が公示され、7月20日投開票されます。
経済統計は、次の発表がありました。
予測値 実績値
24日 米3月経常収支 -4435億ドル -4502億ドル
日5月全国百貨店売上高 4356億円
25日 日4月景気先行指数 103.4 104.2
景気一致指数 115.5 116.0
26日 米3月実質GDP -0.2% -0.5%
3月GDPデフレータ 3.7% 3.8%
3月個人消費 1.2% 0.5%
5月耐久財受注 0.8% 16.4%
27日 日5月完全失業率 2.5% 2.5%
5月有効求人倍率 1.26倍 1.24倍
6月東京都区部CPI 3.3% 3.1%
米5月個人所得
0.2% -0.4%
5月個人支出
0.2% -0.1%
5月PCEデフレータ 2.6% 2.7%
経済統計は、次の発表があります。
予測値
2025年6月30日 日5月鉱工業生産指数 1.5%
中6月製造業購買担当者景気指数 49.7
1日 日6月消費者動向調査 33.5
日銀短観大企業製造業先行 9
業況判断 10
大企業非製造業先行 29
業況判断 34
中6月財新製造業PMI 39.0
米6月ISM製造業景気指数 48.8
3日 米6月失業率
4.3%
5月貿易収支 -698億ドル
5月耐久財受注 16.4%
6月ISM非製造業景気指数 50.8
4日 日5月全世帯家計調査
1.3%
第14回目 2025年7月7日
要点 6. 3 ドルコスト平均法
・ EXCEL表計算
6. 4 リバランス法
・ドルコスト平均法継続中、何をすべきか
・リバランス法
6. 3 ドルコスト平均法
今回の本文の終わりに、6種類の投資信託の毎月27日(休日の場合、翌営業日)の基準価格を記入した投資信託基準価格表を載せている。投資信託基準価格表から、月次平均収益率をEXCEL表計算した月次平均収益率表を載せている。
EXCEL表計算
2019年1月~2025年6月までの6投資信託基準価格表から、投資信託の債券1、株式3、リート2の、t-1日の月次収益率を(Pt-Pt-1)/P t-1 とし、EXCEL表計算する。
EXCELのデータ分析・分析ツールから、基本統計量を選び、6投資信託の月次収益率の平均値と標準偏差を計算する。6投資信託の平均値と標準偏差を散布図に表す。以上のEXCEL表計算の手順を表すと次のようになる。
① 6つの投資信託の基準価格表から、月次平均収益率をEXCEL表計算し、月次平均収益率表を作成する。
② EXCELファイルにおいて、データ分析→分析ツール有効化する。
③ 分析ツールから、基本統計量を選び、6つの投資信託の基本統計量を計算する。6つの投資信託の標準偏差σと平均収益率μを表にする。
④ 6つの投資信託の標準偏差σと平均収益率μの散布図を作成する。
投資信託基準価格表の作成
EXCELシートを開いて、投資信託基準価格表(2019年1月~2025年6月)を作成する。
検索サイトにおいて、各投資信託を検索し、投資信託の基本データと、基準価格の時系列のチャートをみる。
投資信託基準価格表(2019年1月~2025年6月)
EXCELシート
ファイル HOME 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示
A B C D E F G H I
1 日付
SBI外債 日興20 日興40 日興60 SBIGREIT 日生JREIT
2 190128 11258
15501 18364 20949 13557 11153
3 190227 11446
15654 18758 21582
14170 11351
4
5
EXCELシートの1番行を右へ、AからJまでの7セル(空欄)に、順に、日付、6個の投資信託名を記入する。日付の列Aは、日付名190128から2025627を、行番号2番から91番まで、90個を記入する。SBI外債のデータをB列2番(B2)のセルからB列91番(B91)のセルまで記入する。同様に、日興20のC列から、日興40のD列、日興60のE列、SGIWREITのF列、日生JREITのJ列までデータを記入すると投資信託EXCEL表が作成できる。
今回の本文の終わりに、6種類の投資信託の毎月27日(休日の場合、翌営業日)の基準価格表を載せている。
EXCEL表計算の手順①~④にしたがって、①投信月次収益率表作成、②分析ツール有効化、③基本統計量の平均値、標準偏差の計算、(標準偏差、平均値)表を作成、④散布図を作成する。
① 投信月次収益率表(2019年1月~2025年6月)の作成
投資信託EXCEL表から、投信月次収益率を計算する。
投資信託EXCEL表と同じEXCELシートの1番行を右へ、L列からR列までの7セル(空欄)に、日付、6個の投資信託名を記入する。
EXCEL関数計算
t月次収益率を(Pt-Pt-1)/P t-1 とし、計算する。
EXCELシート
ファイル HOME 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示
✕ ✓ fx =(B3-B2)/B2
A ~ L M
N O
P Q R
1 日付 日付 SBI外債 日興20 日興40
日興60 SBIGREIT 日生JREIT
2 190128 190128
3 190227 190227 ✚ ⇒右へドラッグ
4 190327 190327
✚ ⇒右へドラッグ ✚
下へドラッグ↓
91 250627 250627
M列3行のセルを入力できるように、ポインターをアクティブにする。
EXCELシートの上辺に、関数欄[✕ ✓ fx]があり、右の記入欄に[=(B3-B2)/B2]の定義式を記入する。意味は、[=(11446-11258)÷11258]である。M列3行のセルに結果が計算されて出る。同様に、N列3行のセルをアクティブにする。関数欄[✕ ✓ fx]右の記入欄に[=(C3-C2)/C2]を記入、N列3行をポインターすると、計算結果がでる。
同様に、M列4行およびN列4行を、関数欄[✕ ✓fx][=(B4-B3)/B3]および[=(C4-C3)/C3]を記入、R列4行までドラッグすると、1行×6列のセルに、結果が連続計算される。
M列3行およびN列3行の2つのセルをドラッグして、アクティブにする。N列3行のセルの右下の隅にポインターを合わせると、ポインターが✚に変わり、そのまま、押さえて右に、R列3行までドラッグすると、1行×6列のセルに、結果が連続計算される。
M列3行から、斜め右下へR列4行まで、ドラッグし、長方形をつくる。R列4行の下の隅にポインターが✚に変わると、そのまま、押さえて下に、R列91行まで、さぁーとドラッグすると、88行×6列のセルに結果が連続計算され、投信月次収益率表が作成できる。
本文の終わりに、投資信託EXCEL表の次に、以上のEXCEL 計算した6種類の投信月次収益率表(2019年2月~2025年6月)を載せている。
② EXCELデータ分析→分析ツールの有効化
EXCELの上辺のデータ欄をクリック、データ欄がその下に展開する。その右端に、データ分析を付ける作業をする。
EXCELのファイルから、オプションのアドインをクリック、通常は、無効なアプリケーションの中で、分析ツールが無効になっているので、分析ツールの前の四角□にチェック・マーク☑を入れて、有効にする。
注意:分析ツールを有効にすることを、各種EXCEL分析解説書を調べ、数か月使わないと、何度も忘れた。私は、各種のEXCEL分析解説書をもっているが、読者はなかなか、3000円程度はするので、仕事でEXCEL分析する人以外、本屋で立ち読みするか、検索して調べるしかない。
分析ツールを有効化した後、EXCELファイルの上辺に、[データ]の項があり、クリックすると、右端に[データ分析]の項がつく。それをクリックすると、EXCELファイルの右下に、次のデータ分析の「窓」が出る。
データ分析 ? ×
分析ツール(A) OK
分散分析:繰り返しのない二元配置 キャンセル
相関 ヘルプ(H)
共分散
基本統計量
指数平滑
F検定:2標本を使った分散の検定
フーリエ解析
ヒストグラム
移動平均
乱数発生
基本統計量を選んで、OKをクリックすると、次の基本統計量の「窓」が出る。
基本統計量 ? ×
入力元 OK
入力範囲 $M$3:$M$91 キャンセル
データ方向 ◎ 列(C) ヘルプ(H)
○ 行(B)
☑先頭行をラベルとして利用(L)
出力オプション
○出力先(O): $A$95
◎新規ワークシート(P)
〇新規ブック(W)
☑統計情報(S)
□平均の信頼度の出力(N) %
□k番目に大きな値(A)
□k番目に小さな値(M)
③ 基本統計量作成
6種類の投信月次収益率表(2019年2月~2025年6月)から、基本統計量の窓で、平均値と標準偏差を計算する。6つの投資信託の標準偏差σと平均収益率μを表にする。
基本統計量の「窓」の中で、入力範囲に、セル番地を[$M$3:$M$91]のように入力する。先頭行をラベルとして使用に✓する。出力範囲に、セル番地を[$A$100]のように入力する。統計情報にチェック✓を入れる。OKをクリックすると、出力セル番地[$A$100]に、2列のセルを使って、次の基本統計量が表示される。
|
SBI外債
|
|
|
|
|
平均
|
0.002881
|
|
標準誤差
|
0.001803
|
|
中央値 (メジアン)
|
0.004056
|
|
最頻値 (モード)
|
0
|
|
標準偏差
|
0.016913
|
|
分散
|
0.000286
|
|
尖度
|
0.226904
|
|
歪度
|
-0.27729
|
|
範囲
|
0.082768
|
|
最小
|
-0.04227
|
|
最大
|
0.040499
|
|
合計
|
0.253555
|
|
データの個数
|
88
|
|
信頼度(95.0%)
|
0.003584
|
入力範囲は、セル番地を[$M$3:$M$91]から、[$R$3:$R$91]としていく。出力範囲は、それぞれ、セル番地を[$A$100]から、2列ごとに、[$C$100]、[$E$100]、[$G$100]、[$I$100]、[$K$100]とする。
基本統計量から得た、6つの投資信託の標準偏差σと平均収益率μを表にすると、次になる。
|
SBI外債
|
日興20
|
日興40
|
日興60
|
SBIGREIT
|
日生JREIT
|
|
標準偏差
|
0.016913
|
0.012068
|
0.016902
|
0.023556
|
0.055292
|
0.041079
|
|
平均
|
0.002881
|
0.001576
|
0.003798
|
0.006115
|
0.005052
|
0.003265
|
④ 散布図の作成
WORDファイルの上辺 挿入をクリックする。グラフをクリックする。すべてのグラフから、散布図を選ぶ。X(横軸)の値に標準偏差値を、Y(縦軸)の値に平均収益率を記入する。散布図が表示される。
|
Xの値
|
Yの値
|
|
|
0.016913
|
0.002881
|
SBI外債
|
|
|
0.012068
|
0.001576
|
日興20
|
|
|
0.016902
|
0.003798
|
日興40
|
|
|
0.023556
|
0.006115
|
日興60
|
|
0.055292
|
0.005052
|
SBIGREIT
|
|
0.041079
|
0.003265
|
日生JREIT
|
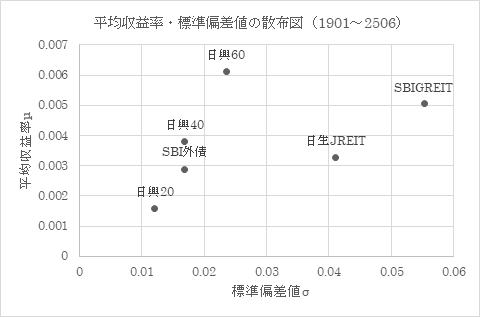
グラフエリアの右端に、✚のグラフ要素のボタンがある。グラフの上辺をタイトル、縦軸ラベルに平均収益率、横軸ラベルに標準偏差値を記入する。データラベルに投信名を記入する。目盛り線にチェックを入れる。グラフスタイルのボタンで、色を選び、黒にする。
昨年の散布図を掲載する。
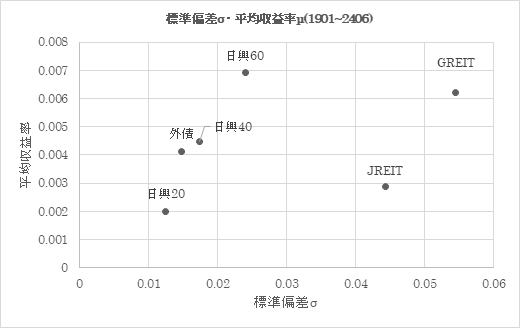
6. 4 リバランス法
ドルコスト平均法継続中、何をすべきか
契約証券会社サイトにおいて、若年世代および壮年世代は、毎月の拠出額は、少額定額設定である。投資戦略は、ドルコスト平均法で購入し、iDeCoでは、60歳まで、引出はできない。ある商品の全額を売却、他の商品にスイッチする戦略は、売却に手数料がかかり、購入も手数料がかかるので、ドルコスト平均法に反する。
個人貯蓄の制度利用の場合は、NISAか、またはつみたてNISAを契約する。投資信託の場合、株式の割合が高くても、平均分散化されているので、基準価格の変動は、激しくない。NISAは売却益の非課税が5年以内なので、目標上昇率が15%であれば、目標上昇率を達成すれば、売却し、利益を確定する。その後、再購入するか、別の商品を購入するのが、非課税制度利用の方法である。
購入した商品は、それぞれ、証券会社のサイトに登録できる。実際に、毎月、ドルコスト平均法で購入していれば、登録リストに、投資信託の評価額が表示される。個別の投資信託の日々の変動も見ることができる。
新NISA制度は、2024年から、施行開始でしている。海原氏、山川家、高原家の資産規模では、新NISA制度の枠でカバーできる。確定拠出型企業年金iDeCoの商品選択肢が狭い、積立満期が定年であるのと比較すれば、新NISA制度による運用商品の幅がひろく、運用期間が終身である。来年度の『資産形成論2025年』は、新NISA制度のもとで、家族の資産形成を計画、運用、管理する方法を考える。
リバランス法
著しく運用成績が変化すると、選択した資産構成比率に戻すために、成績のよい商品の一部を売却するか、他の商品に再配分し、資産構成比率を回復することをリバランスという。
資産形成論の理論では、中長期投資を定額的に、継続していく家計を想定している。しかも、資産投資を専業とする投資愛好家ではなく、危険回避者で、最小分散となる商品の組み合わせに投資する。
危険回避者である家計は、資産選択理論にしたがって、最小分散となる商品の組み合わせを決定し、各商品に最適資産選択率で、毎月か半年ごとの定額資金を割り当て、ドルコスト平均法にしたがい、半年から1年間、同じ商品を決定した額を購入する。
各商品の特性である、標準偏差と平均収益率は、経済活動共に、変動し、政府の経済政策および中央銀行の金融政策の変更で、時間を通じて一定ではない。
投資信託商品では、もともと、多数の商品で構成されているので、標準偏差と平均収益率の変化は、個別商品である個別株式よりは、ゆるやかである。しかし、経済活動の変動、対応する政府の経済政策および中央銀行の金融政策の変更で、ドルコスト平均法の最小管理期間を半年とすれば、投資信託商品の(標準偏差,平均収益率)は、許容範囲を超えるときがある。
購入する投資信託を売却、別の商品を購入すると双方の取引コストが高い。むしろ、想定した許容範囲を超えた(標準偏差,平均収益率)の商品は、購入を中断し、許容範囲内の商品を購入するスイッチの方が、取引コストは低い。
リバランスの時期
リバランスをする時期は、運用期間が短期~5年、中期5年~10年、長期10年以上で、違う。見直し期間が、短期~5年であるほど、商品の入れ替えは、回数が多くなる。
ドルコスト平均法のもとで、リバランスは、制度を利用している場合、口座から引出し、消費することは出来ないが、口座内で、売却した収益によって、他の商品を購入することができる。また、一方の資産の購入を中断し、他の資産を買うスイッチはできる。
・2以上の資産で、高い資産価格から、低い資産価格にスイッチする。
・長期的には、最終目標5年前(制度期限)で、リスクが低い資産に、シフトする。
・5年前まで、口数の増加を目標にするから、低い価格の資産にスイッチする。
本教室では、投資家は、各商品の平均収益率だけでなく、リスクを考慮する。平均分散の有効フロンティアと確定型証券の収益率からの直線との交点で、リスク資産の合成資産が決まる。投資家がその直線の最適点を選択するというのが、教科書的な投資戦略である。その戦略にしたがえば、バランス型投資信託を選択することになる。そして、時系列的には、ドルコスト平均法で、定額購入を半年継続する。
リバランスの状況が生じるかは、バランス型投資信託以外の投資信託を選択している場合になる。本講義では、2本あれば、変動が少ない方を買い続ける。半年たって、見直すと、それがリバランスに自動的になるのではないか。
海原氏、山川氏、高原氏、の運用計画を見ると、それぞれの目的で、1本に絞っているので、選択肢が2本以上ないと、ドルコスト平均法でのリバランスは、あまり効果はない。
[iDeCo]の[運用商品一覧]および[つみたてNISA]の[つみたてNISAの取扱商品]の範囲の中で、どのように運用管理すると、投資家の満足する成果が得られるのか。平均分散戦略とドルコスト平均法の関係は、平均分散戦略で商品のポートフォリオ(一覧表)を決め、それぞれの投資額を決め、毎月か、半年ごとに、ドルコスト平均法で、機械的に、定額購入していくことになる。
平均分散戦略で選択した商品ポートフォリオとリバランス法との関係は、商品の(標準偏差,平均収益率)は、許容範囲の設定にある。たとえば、商品の(標準偏差,平均収益率) 20%を、許容範囲と設定すれば、それを越えた商品は、リバランス法の対象商品になり、商品特性が変化したとみて、平均分散戦略に入れるか、再計算する。
リバランス法の実際例
投信月次収益率(2019年1月~2024年6月)
|
SBI外債
|
日興20
|
日興40
|
日興60
|
SBIGREIT
|
日JREIT
|
|
標準偏差
|
0.014877
|
0.012551
|
0.017448
|
0.024052
|
0.054488
|
0.044292
|
|
平均
|
0.004128
|
0.001999
|
0.004475
|
0.006914
|
0.006203
|
0.002869
|
(2019年1月~2024年6月)のデータで、各投信のσとμの20%上限
|
σ×1.2
|
0.017852
|
0.015061
|
0.020937
|
0.028862
|
0.065386
|
0.05315
|
|
μ×1.2
|
0.004953
|
0.002398
|
0.00537
|
0.008297
|
0.007444
|
0.003443
|
(2019年1月~2024年6月)のデータで、各投信のσとμの20%下限
|
σ×0.8
|
0.011901
|
0.01004
|
0.013958
|
0.019241
|
0.04359
|
0.035433
|
|
μ×0.8
|
0.003302
|
0.001599
|
0.00358
|
0.005532
|
0.004962
|
0.002295
|
2024年6月までの標準偏差と平均収益率の上限と下限をそれぞれ、20%で計算した。
2025年6月までの標準偏差と平均収益率は次の通りである。
投信月次収益率(2019年1月~2025年6月)
|
SBI外債
|
日興20
|
日興40
|
日興60
|
SBIGREIT
|
日生JREIT
|
|
標準偏差
|
0.016913
|
0.012068
|
0.016902
|
0.023556
|
0.055292
|
0.041079
|
|
平均
|
0.002881
|
0.001576
|
0.003798
|
0.006115
|
0.005052
|
0.003265
|
標準偏差は、上限および下限の範囲内に入っている。平均収益率は、SBI外債および日興20が下限より低い。他の4範囲内に入っている。リバランスの対象は、SBI外債および日興20ということになり、購入をストップする方がよい。
2021年後半から、FRBが金融緩和を停止、資産購入を計画的に削減し、金利も上昇させる、金融政策の重大な変更に着手した。2番目の散布図をみると、その政策変更効果が、6種類の投資信託に現れている。まず、外債と日興20(債券の割合が大きい)が、標準偏差を上げた。Gリート、Jリートは標準偏差が下がり、収益率も下がった。しかし、JリートとGリートと比較すると、Jリートが下落した。日興40および日興60も、収益率を下げている。
『資産形成論2022年』では、次のように、リバランスをすべきである。外債と日興20は標準偏差の上昇が大きいので、購入を停止する。JリートとGリートは、Jリートの下落傾向は、底が見えないので、購入を停止する。日興40および日興60は、米国の金融政策の変更期間にもかかわらず、変化が大きくないので、そのまま購入を続ける。
外債および債券割合の多い投資信託、グローバルリートは、米国および世界金利の上昇期にあったため、金融政策の変更に、価格が再計算されたのである。しかし、日本リートは、日本の金融政策に変更は、現在もなく、Jリートの収益率が減少するのは、実需の減少、日本固有の地価の下落、建設需要の弱化、テナントの空き室率の高止まりが原因であり、長期金利は低く抑えられている。日本銀行は建設金利を低金利のままにしていながら、金融緩和の効果もないことを示している。リニア新幹線工事は、静岡県知事の建設妨害で、工事は進まず、大阪万博の各国パビリオン建設も着手していない。
『資産形成論2023年』では、リートについては、ニッセイJREITに収益性の底打ちが見えず、依然、標準偏差が、外債より、3.6倍あるので、ドルコスト平均法の定額購入商品リストから、外し、建設、テナント、住宅、マンション等の建設需要が上向くまで、購入を止めるべきである。その間、テナント料が分配されるので、トータル収益率は維持される。
『資産形成論2024年』では、SBI全世界REITは、マイナスの平均収益率になった。標準偏差も日興60と比較して、6倍ある。バランスの日興20よりは、SBI外債の方が、成績が良い。株式20程度ならば、外債のみの方が、バランスより、リスク価格:平均収益率/標準偏差がSBI外債0.27747、日興(株式20)0.15927で、高いことからも、成績が良い。
今週(2025年7月7日~7月11日)のイベントと市場への影響度
先週のイベントは、1日日銀短観が発表されました。国税庁から路線価が公表されました。3日参議院選が公示されました。7月20日投開票されます。
今週のイベントは、6日BRICS首脳会議がリオデジャネイロで7日まで開かれます。
先週の統計は、次の発表がありました。
予測値 実績値
6月30日 日5月鉱工業生産指数 1.5% -1.8%
中6月製造業購買担当者景気指数 49.7 49.7
7月1日 日6月消費者動向調査 33.5 34.5
日銀短観大企業製造業先行 9 12
業況判断 10 13
大企業非製造合先行 29 27
業況判断 34 34
中6月財新製造業PMI 49.0 50.4
米6月ISM製造業景気指数 48.8 49.0
3日 米6月失業率
4.3% 4.1%
5月貿易収支 -698億ドル -715億ドル
5月耐久財受注 16.4% 16.4%
6月ISM非製造業景気指数 50.8 50.8
4日 日5月全世帯家計調査
1.3% 4.7%
経済統計は、次の発表があります。
予測値
2025年7月7日 日毎月勤労統計 2.6%
日5月景気動向指数一致 115.9
先行 105.2
8日 日6月景気ウォッチャー調査 44.9
5月国際収支 -5244億円
9日 日6月工作機械受注額
中6月消費者物価指数 -0.1%
ホームページへ戻る